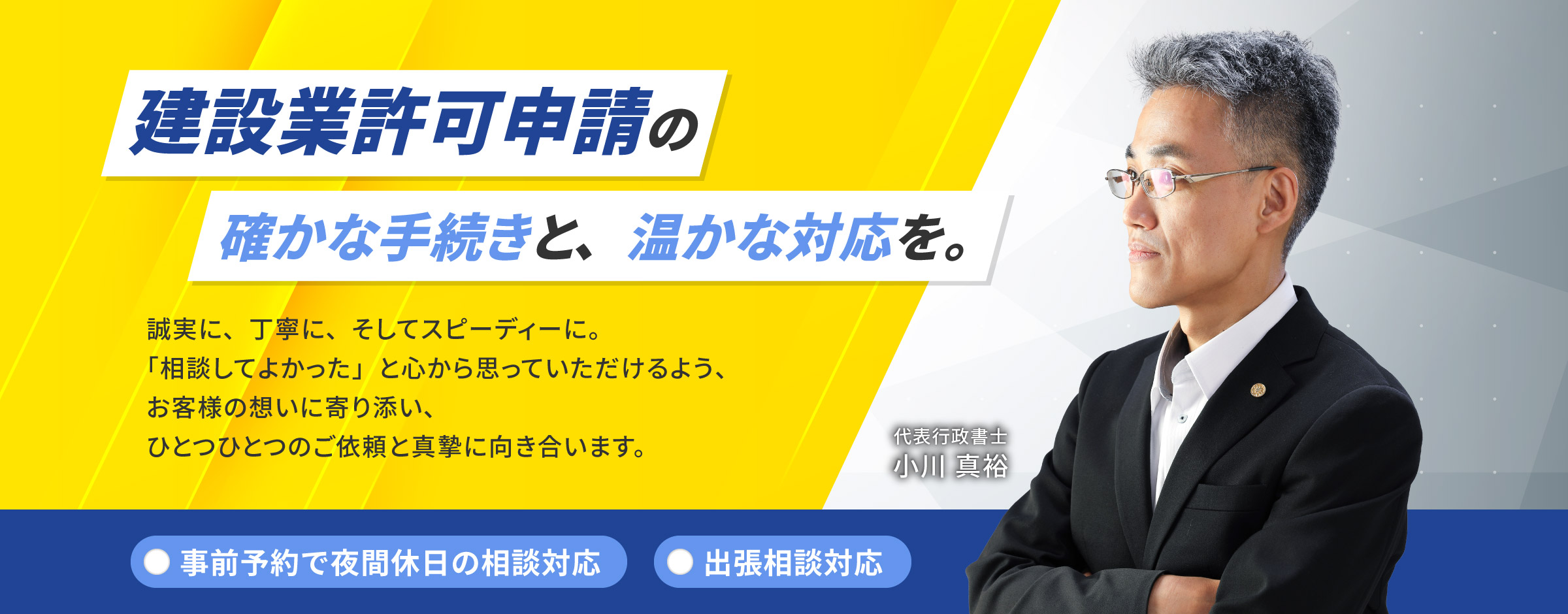
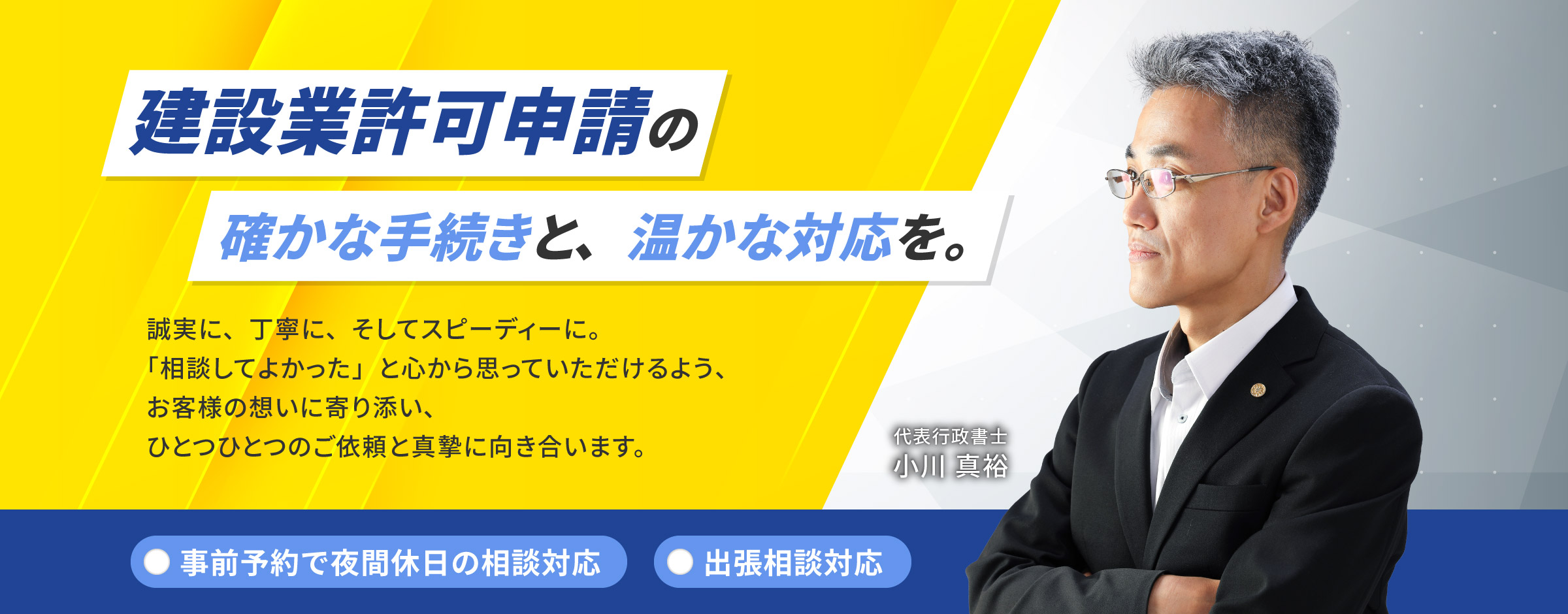
丸ごとお任せください。当事務所が解決いたします。

全て当事務所にお任せください!
当事務所が許可取得のために必要な要件を満たしているかの判断から、申請書類の作成及び添付資料の収集、担当窓口への提出まで許可取得に至るまでの一連の手続きを事業主様の代わりに行います。

請負金額の制約を受けずに工事を受注したい事業主様
未許可業者に課せられる500万円という上限が無くなることで請負金額に左右されず受注できるようになります。

新規受注、資金融資に繋げたい事業主様
建設業許可を取得することで発注者、元請、金融機関から社会的信用を得られ、新規受注・資金融資に繋がりやすくなります。

公共工事の入札参加を検討している事業主様
公共工事の入札参加には建設業許可の取得が必要です。許可を取得することで公共工事の入札参加が選択肢に加わります。
当事務所は「建設業許可申請」を得意とする行政書士事務所です。

許認可申請の中でも高難度の部類に属する「建設業許可申請」を当事務所は主業務として取り扱っております。
他の事務所で「営業所技術者の要件を満たす資格がない」「経営業務管理責任者の実務経験を証明する書類がない」といった理由で新規許可取得は無理と断られた案件も当事務所に是非一度ご相談ください。
建設業許可申請を得意とする行政書士が許可取得の道筋をあらゆる角度から探します。
「許可の早期取得」初回相談は無料、安心の「全額返金保証」

「一日でも早い許可の取得」「更新申請の期限が迫っている」といったご要望のお客様も当事務所にご相談ください。
営業時間外・土日祝日も事前相談で行政書士がお客様の元に駆け付けます。初回の相談料は無料です。
万が一不許可の場合はお預かりした費用を返却する全額返金保証制度を当事務所は採用しています。
許可取得後の長期的サポートプランの提案、「決算変更届」「更新申請」「経営事項審査」「入札参加資格」「CCUS登録」「グリーンサイト登録」もお任せください。

当事務所は許認可申請の代理・代行業務以外に、許可取得後のサポートプランもご用意しています。
現場作業で多忙を極める個人事業主様や設立間もなく組織再編に追われる法人様は事業年度終了毎に提出する義務が生じる「決算変更届」等に人員や時間を割く余裕はないかもしれません。
当事務所に任せて頂ければ「決算変更届」「経営事項審査」の書類の作成・提出からスケジュール管理まで全面的にサポートいたします。
建設業許可申請に係る報酬の地域最安値を目指します。

当事務所は広島県内全域の個人事業主様、法人成りした事業主様、小規模会社様との結びつきを最重要視しています。
行政書士に任せたいが初期費用はかけたくない、許可維持にかかる金額は安く抑えたいといった経営者の抱える事情に応えるためリーズナブルな料金設定にしています。
業種追加・更新申請・許可換え新規といったランニングコストも比較検討してください。当事務所は顧客から任せて良かったと思われる事務所を目指して全力で業務を遂行します。
公共工事の競争入札に参加するために申請必須となる「経営事項審査」の評点アップ。その他専門士業との連携・同業者ネットワーク。

建設業者であれば公共工事の受注も検討されると思います。当事務所は「経営事項審査」の書類作成だけでなく評点アップのサポート業務もおこなっています。
また、建設業許可申請以外の業務に関しては当事務所以外の実務経験豊富な士業事務所と連携をとって業務にあたります。
資格以外にも要件を満たす方法はいくつかございます。
内装仕上工事業ですと、資格の場合は「建築施行管理技士」「建築士」が該当します。資格以外で要件を満たすには指定学科を卒業しているか、技術検定試験に合格している場合は実務経験の年数を短縮することができます。
内装仕上工事業であれば「建築学」又は「都市工学」に関する学科を卒業していれば必要な実務経験が3年又は、5年に短縮されますので要件を満たすことになります。
又は、内装仕上工事業に関する技術検定試験の1次試験に合格していれば「技士補」の称号が付与され要件を満たすために必要な実務経験が5年に短縮されますので、要件を満たすことができます。
ご自身が条件を満たしていなくても、従業員の方やお知り合いで営業所技術者の要件を満たしている方がおられる場合はその方を営業所技術者として申請することは可能です。ご検討してみてください。
新しく採用予定の方を経営業務管理責任者として建設業許可申請をする場合、事前の準備を疎かにするとトラブルを招くおそれがあります。
手続きを失敗しないための注意点としては、建設業許可申請する前にご親戚の入社手続き、定款の変更等を事前に済ませておく必要があります。そのため入社前の段階でご親戚の建設業の役員経験5年分の確認書類を揃えておくことがとても重要です。確認書類が揃わなければ経営業務管理責任者として申請することができないからです。
具体的には必要期間分の「許可通知書」「所得税の確定申告書」「請負契約書」「注文書」といった書類になります。これらの書類を確実に揃えてから入社手続きを取ることをお薦めします。
その他の注意点としては、役員経験は常勤でしか認められず、非常勤では実務経験として認められませんので、合わせて確認しておくことです。
ご相談ありがとうございます。退職される前に準備しておくことはとても重要です。退職された後では会社の規定や関係性などによって建設業許可申請に必要な書類が揃えにくくなる場合があるためです。
退職前に揃えておくべき書類は経営業務管理責任者と営業所技術者の要件に関する確認書類になります。経営業務管理責任者であれば「役員経験」、営業所技術者であれば「実務経験」です。
経営業務管理責任者の「役員経験」の確認書類は具体的には必要期間分の「許可通知書」「所得税の確定申告書」「請負契約書」「注文書」といった書類になり、営業所技術者の「実務経験」としては「請負契約書」「注文書」などが該当します。
これらの書類を揃えておくことで開業と同時に建設業許可申請をすることができます。
ご安心ください。現在お使いの住居が建設業許可における営業所の要件を満たしていれば申請は可能です。
具体的には請負契約を交わす事務所スペースが独立していることや、事務机や電話などの備品が備わっていること、そして玄関や事務所のドアに会社名が掲示されていることなどが挙げられます。
これらの条件を満たしていれば自宅とは別に事務所を借りなくても、自宅を営業所として建設業許可申請をすることは可能です。
純資産が500万以上なくても可能性は残っています。
一般建設業許可の財産要件は①500万円以上の資金調達能力があると認められること。②自己資本の額が500万円以上あること。のいずれかを証明する必要があります。
お客様の場合は純資産が500万円以上ありませんので、貸借対照表以外の財産要件の証明方法としては次の証明方法があります。①預貯金が500万以上ある場合は金融機関から500万円以上の預貯金残高証明書(残高証明書)を発行してもらう。②金融機関から500万以上の融資可能証明書を発行してもらう。これらの方法で財産要件を満たすことができます。
注意点としては名義人は申請者で申請日前30日以内の日時であることが必要になります。
ご安心ください。一人親方のままでも建設業許可を取得することは可能です。
一人親方の場合は社会保険の適用除外対象となり、国民健康保険、国民年金、雇用保険は未加入で申請することが可能です。
尚、建設業許可の取得にあたり社会保険、雇用保険の加入が必須となるのは法人、5人以上の従業員がいる個人事業主になります。
法人登録していない個人店舗の従業員だとしても、勤務形態と勤続年数、経営業務の経験の有無で経営業務管理責任者として申請できる余地は残っています。
息子様が経営業務管理責任者の役員経験を満たすには「職制上の地位」と「経営業務の管理責任者の補佐経験」の二つの条件を満たす必要があります。
例えば、息子様がお客様の直属の補佐として業務に携わり、建設工事に関する①資金の調達、②技術者及び技能者の配置、③下請業者との契約等の経営業務に従事した経験を6年以上有していれば経営業務管理責任者として申請できる可能性があります。
その他のアドバイスとしては経営業務管理責任者の他、息子様が営業所技術者として要件を満たしているかの確認も必要です。
ご紹介した問い合わせ以外にも様々な問い合わせがあります。
「建設業許可のことを知りたいが誰に質問したらいいのかわからない。」
「建設業許可を取得したいが何をしたらいいのかわからない。」
どんな些細な悩み・疑問だとしても当事務所にお気軽にご相談ください。
行政書士小川真裕事務所ではお客様のお話を伺い、
建設業許可取得までの道筋をご提示させて
いただきます。
まずは下記のいずれからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ内容は面談予約、見積り依頼、業務内容、料金などどのような質問も受け付けています。
お電話の場合は充分に相談内容をお話しください。しっかりと相談内容をお伺いいたします。
お話を伺った後にヒアリングをさせていただき、相談を受けた時点での許可取得の見通しやアドバイス、ご依頼を受けた場合の手続きの流れ・費用の説明をいたします。どんな質問でも受け付けておりますので納得がいくまでお話しください。
面談を希望される場合は、お名前・ご連絡先携帯番号・面談希望場所・ご都合の良い曜日や時間帯をお知らせください。
事前に相談していただければ、面談は土日祝、営業時間外も対応いたします。メールでの面談予約も可能ですのでお気軽にメールをしてください。面談ではなくZoomを希望の方はお伝えください。
ご希望の面談場所に行政書士が伺います。
面談にかかる時間の目安はおおむね1時間を予定していますが、時間の制限はございませんので時計を気にせずゆっくりお話しください。
また面談日までに準備していただきたい資料を行政書士の方から事前にお伝えしますので当日までにご準備をお願いします。
ご相談内容をお伺いした上で、お見積書を提示いたします。
ご納得いただきましたら、ご契約となります。
着手金が必要な業務については、お見積書にて着手金のご案内をいたします。また、残金の支払い金額・時期についてもお見積書にて、提示させていただきます。
着手金の入金を確認後に業務に着手し、適宜業務の進捗状況をご報告します。契約後の相談に追加費用は発生しませんので気付き、ご不明点があれば随時お問合せ下さい。お問合せは電話、メール、LINE、Zoomいずれも可能です。
申請書類の受理後に、着手金を除いた残金の請求書を発行させていただきますので、銀行振込みにてお支払いください。
許認可申請であれば、お預かりした資料の返却、許可取得後に発生する義務・注意事項の説明および、関連資料をお渡しして業務完了とさせていただきます。