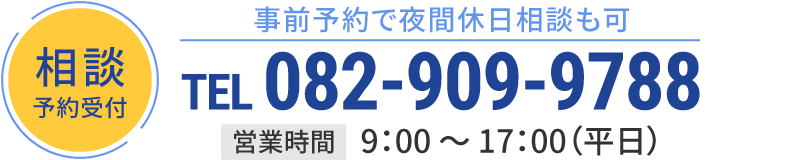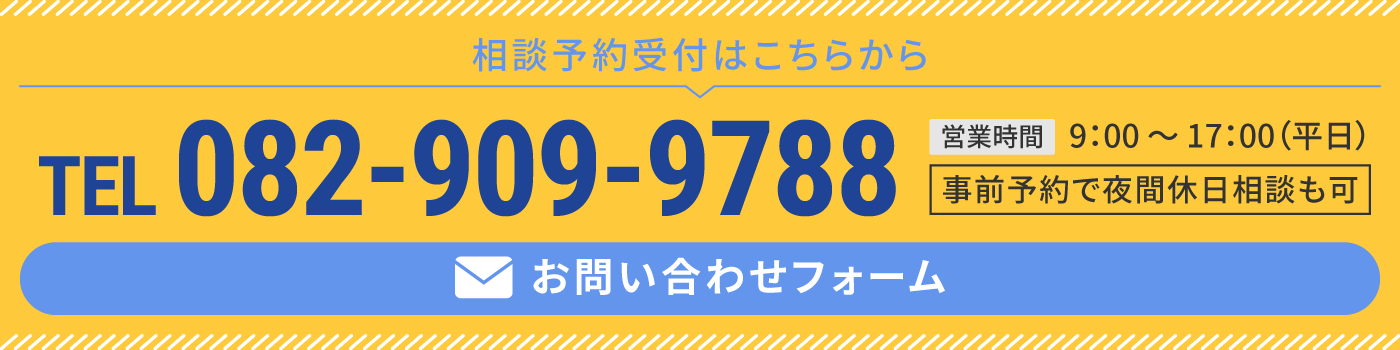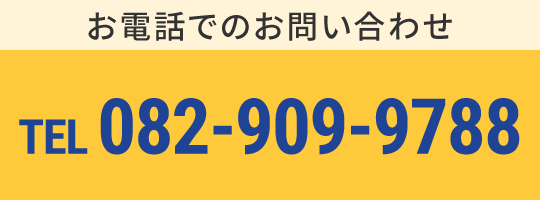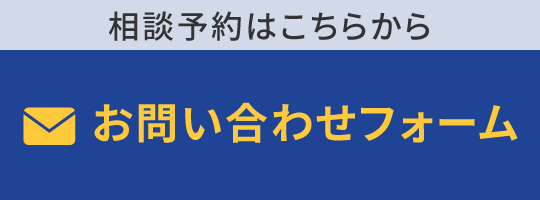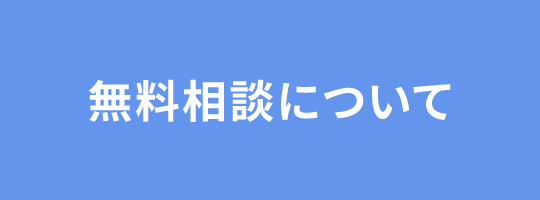このページの目次
建設業会計とは
建設業会計とは、長期の工事を主な事業とする建設業の特殊な商習慣に対応するために設けられた、建設業独自の会計処理のことです。一般的な会計とは異なり、長期工事の収益を計上する基準が「工事進行基準」か「工事完成基準」のいずれかを選択できる点や、「未成工事支出金」や「完成工事高」といった特有の勘定科目を使用する点が特徴です。建設業許可を取得する際には、この建設業会計に基づいた財務諸表の作成・提出が必要となります。
建設業会計が必要な理由としては、建設業では土木・建築工事の着工から引き渡しまで1年以上と工事期間が長期化することが多く、複数の決算期をまたぐのが一般的です。そのため、一般的な会計処理では収支状況を正確に把握することが難しくなります。 また、特殊な商習慣への対応や工事の進捗や完了のタイミングで収益と費用を計上する必要があるため、独自の会計ルールを設ける必要があったためです。
「工事進行基準」とは
工事進行基準とは、建設業などで用いられる請負契約における会計方法で、工事の進捗度に応じて売上や費用を決算期ごとに分散して計上するものです。
この基準では、工事の「工事収益総額」「工事原価総額」「工事進捗度」が合理的かつ信頼性をもって見積もれる場合に適用され、工事の収益性を早期に把握できるメリットがある一方、進捗度の測定や管理体制の整備が複雑になるデメリットもあります。なお、2021年4月からは「収益認識に関する会計基準」が導入され、従来の工事進行基準は事実上廃止されていますが、収益認識の考え方自体は新基準に引き継がれています。
「工事完成基準」とは
建設業許可における工事完成基準とは、工事が完成し、その目的物の引き渡しが完了した時点で、工事の収益と原価を一度に計上する会計方法です。つまり、工事が始まる前から完了までの期間全体で発生した費用は、工事が完成して引き渡した会計年度にまとめて売上とともに計上される方式です。
工事完成基準のメリットとしては、収益と費用が明確で、会計上の確実性が高い。工事が終了するまで売上が計上されないため、税負担を遅らせることで資金繰りに有利になる場合がある。 デメリットとしては期間業績の判定が難しく、工事の期間中の業績を正確に把握しにくい。工事期間が長期にわたる場合、途中でクライアントからの修正依頼などが発生しても、完了するまで赤字が明らかになりにくく、受注側の負担が大きくなることがあります。
「工事進行基準」と「工事完成基準」のどちらを採用するべきか
「工事進行基準」と「工事完成基準」のどちらを採用するべきかは、まずは長期大規模工事に該当するかを確認します。長期大規模工事の定義は、着工から完成までの期間が1年超、請負金額10億円超、または請負対価の1/2以上が引き渡し後1年以内に支払われる工事などです。該当する場合は工事進行基準の適用が原則になります。該当しない場合は、会計・税務における「成果の確実性」の要件を判断し、自社の実態や業務負荷を考慮して、工事完成基準か工事進行基準かを決定します。
「成果の確実性」とは
建設業許可における「成果の確実性」とは、工事収益総額、工事原価総額、そして工事の進捗度について、それぞれ信頼性をもって見積もることができる状態を指します。この確実性が認められる場合に、工事が完成する前の段階から収益を計上できる「工事進行基準」が適用可能です。
「成果の確実性」は、以下の3つの要素の確実性を評価するものです。
- 工事収益総額の確実性
最終的に、工事が完成することの確実性が必要です。 - 工事原価総額の確実性
工事契約の各段階での原価が、詳細に積み上げられ、実際の原価発生と対比して適切に見直せる状態が求められます。 - 決算日における工事進捗度の確実性
工事原価総額の信頼性があれば、進捗度の見積もりも信頼性をもって行えるとされます。
「成果の確実性」が重要が理由としては、建設業では、工事が長期にわたる場合があり、工事完了まで収益を計上できない「工事完成基準」では、期間の業績評価に不都合が生じることがあります。そのため、進捗に応じて収益を計上できる「工事進行基準」が原則とされており、その適用には、上記の「成果の確実性」が認められることが条件となるためです。
工事収益総額の確実性とは
建設業許可における「工事収益総額」とは、建設事業者が工事契約に基づいて受け取る対価の総額を指します。これは、会計上の概念であり、工事完成基準や工事進行基準を用いて収益を認識する際の基礎となる重要な要素です。具体的には、顧客との契約で定められた、工事を施工することで得られる収益の合計金額のことです。
建設業許可における「工事収益総額の確実性」とは、請け負った工事が確実に完成すること、そしてその工事で得られる収益総額が信頼性をもって見積もれることを指します。これは、工事の完成に必要な十分な能力が施工者にあること、および工事の完成を妨げる環境要因が存在しないことが前提となり、信頼性のある工事の収益(対価)を算定できる状態を意味します。
工事収益総額の確実性の具体的な内容としては、工事施工者にその工事を確実に完成させるための十分な能力があること、また、天災などの環境的な要因で工事が中断・中止される可能性が低いことが求められます。 工事契約における最終的な対価の金額や決済条件が確定しており、信頼性をもって収益が見込める見積もりができることが必要です。
この「成果の確実性」という要件を満たすことで、工事の進捗に応じて収益を認識する工事進行基準を適用できるかどうかが判断されます。要件を満たさない場合は、工事が完成した時点を収益認識のタイミングとする工事完成基準を適用する必要があります。
工事原価総額の確実性とは
建設業許可における「工事原価総額」とは、ある会計年度内に完成した工事に要した費用全体を指し、材料費、労務費、外注費、経費の4つの要素から構成されます。この金額は、工事の収益性と経営状況を評価する上で重要な指標であり、建設業許可の申請や更新時に提出する「完成工事原価報告書」に記載されるものです。
工事原価総額は、主に以下の4つの費用項目に分類されます。
- 材料費
工事に直接使用する資材(木材、鉄筋など)や部品の費用。 - 労務費
工事に携わる現場作業員の賃金、手当、福利厚生費などの人件費。 - 外注費
工事の一部を専門業者に委託した場合の費用。 - 経費
上記の費目以外で、工事の遂行に必要な費用(工具・機械のリース料、現場事務所の家賃、水道光熱費、現場管理者の人件費など)。
建設業許可における「工事原価総額の確実性」とは、工事契約に着手した後、工事の進捗に合わせて、各段階で発生する工事原価を詳細に積み上げ、その総額を信頼性をもって見積もり、さらに実際の原価発生と対比して適切に見直し・修正ができる状態にあることを指します。これは、決算時における工事原価の信頼性のある測定を可能にし、建設業許可申請の「成果の確実性」を判断する重要な要素の一つです。
工事原価総額の信頼性を確保するためのポイント
- 詳細な積上げ
工事原価見積総額は、工事の各段階における原価の積み上げとして構成されている必要があります。 - 進捗との対比と見直し
見積もりと実際の原価発生を比較し、定期的に見積もりを見直し、修正を行うことで、より確実な見積もりへと近づけることができます。 - 工事に関わるコストの正確な把握
材料費、労務費、外注費、経費など、工事に直接かかるすべての費用を正確に算出し、把握することが重要です。
建設業会計において、これらの条件を満たすことで、工事原価総額の確実性が認められ、「成果の確実性」が担保されることになります。
決算日における工事進捗度の確実性とは
建設業許可における「工事進捗度(工事進行基準)」とは、工事にかかった原価を基に、工事が全体に対してどれくらい進んでいるかを表す割合のことです。工事進行基準が適用される際に見積もられ、進捗度に応じて売上や経費を計上するために用いられます。
工事進捗度は一般的には、「原価比例法」という方法で算定されます。「原価比例法(げんかひれいほう)」とは、工事の進捗度を測定する方法の一つで、決算日までに発生した工事原価が、工事原価の総額に占める割合を計算し、その割合を工事の進捗度とするものです。この進捗度を用いて、工事進行基準に基づき、売上や経費を計上します。
- 決算日までに発生した原価を把握します。
- 工事にかかった原価の総額を把握します。
- 「決算日までに発生した原価 ÷ 原価総額」で算出し、その割合を工事進捗度とします。
原価比例法の重要性
- 工事の進捗度に応じて、工事収益や費用を計上するための「工事進行基準」を採用する際に、その進捗度を測定するために用いられる。
- 目的物の完成を待たずに、工事の進捗に応じて収益を計上することで、赤字決算を防ぎ、適切な期間損益を認識することができる。
- 工事の途中で原価総額などに変更があった場合、進捗度や収益額も修正する必要があり、定期的に見積りを更新して反映させることが重要。
建設業許可における「決算日における工事進捗度の確実性」とは、工事の進捗状況に応じて適切な収益を認識するために、工事の進捗度を信頼性をもって見積もれることを指します。これは、工事収益総額と工事原価総額の見積もりが信頼でき、さらに工事を完了させる能力や環境が整っていることが前提となります。
新収益認識基準とは
建設業許可における「新収益認識基準」とは、国際的な会計基準(IFRS15)に準拠して、収益をいつ、どのように認識・計上するかを統一的に定めた新しい会計基準です。具体的には、2021年4月1日以降に始まる事業年度から一部の大企業に適用が義務化され、従来の工事進行基準などに代わって導入されました。この基準では、契約内容を履行義務に分解し、履行義務が充足された時点で収益を計上します。
新収益認識基準の主なポイント
- 統一基準の導入
これまで企業ごとに異なっていた売上認識の基準を、国際的な基準(IFRS)と整合性の取れる形に統一された。 - 履行義務の充足
契約内容を分解し、顧客に対して「履行義務(約束した財またはサービスの提供)」が果たされたタイミングで収益を計上する、という原則が導入された。 - 工事契約基準の廃止
従来の建設業における工事契約の収益認識に関する工事進行基準や工事完成基準が、この新収益認識基準に統合され、廃止となった。 - 工事進行基準からの変更点
従来の工事進行基準における会計処理は、新収益認識基準の「一定期間で充足するもの」という考え方に引き継がれてた。また、進捗度の見積もりが困難な場合は、従来の工事完成基準ではなく、新たな会計処理として「原価回収基準」が適用される場合がある。 - 適用対象
新収益認識基準は、大会社、上場企業、上場準備会社に対しては強制適用になる。中小企業など適用対象外の企業は任意適用となる。
新収益認識基準が与える建設業への影響
新収益認識基準は、これまで主流だった工事進行基準を廃止し、顧客との契約で「履行義務」を充足した時点で収益を認識するという5ステップアプローチに基づいた会計処理に移行するため、建設業の収益計上タイミングや財務諸表の透明性が変化します。これにより、国際会計基準との整合性が高まり、資金調達や与信管理の向上、海外展開の促進といったメリットが期待される一方、契約内容の見直しや会計システム、社内体制の構築、経理担当者の教育など、企業側での対応が必要となります。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。