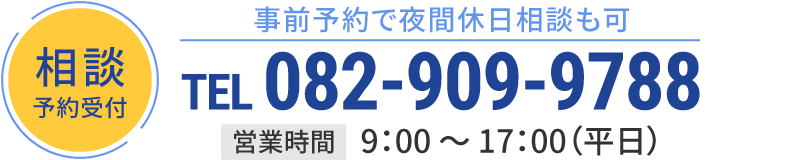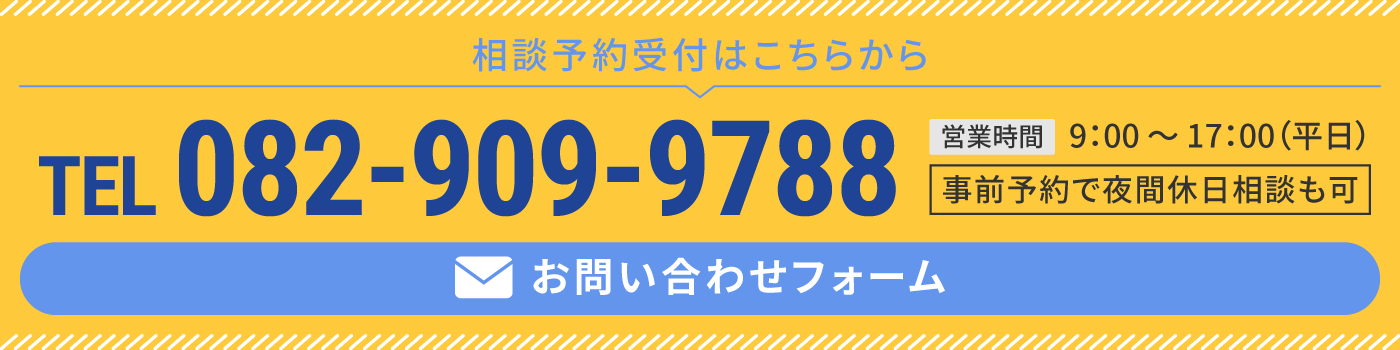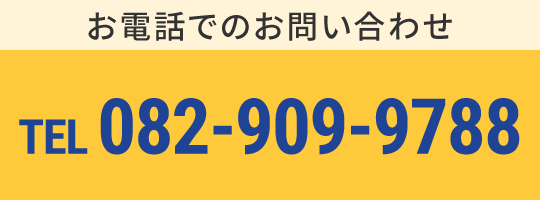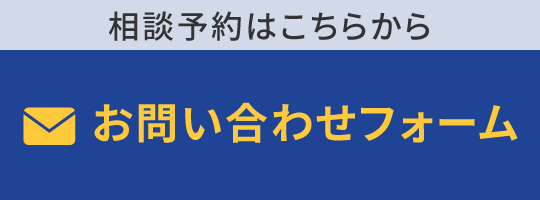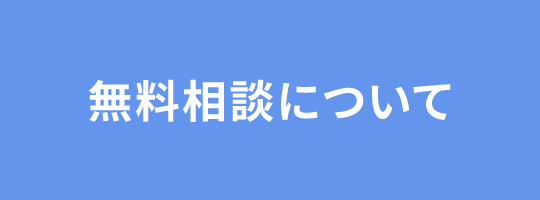このページの目次
建設業法に基づく財務諸表とは?
建設業法に基づく財務諸表とは、建設業法施行規則で定められた様式で作成される、建設業許可の申請時や決算変更届に添付する財務書類のことです。税務署に提出する決算書とは異なり、建設業に特有の勘定科目(完成工事高、未成工事支出金など)を使用し、建設業の経営状況を明確にするためのものです。
建設業に特有の勘定科目が財務諸表に使われている目的は「未成工事支出金」のような工事の進捗を表す勘定科目や、工事の完成と売上計上のタイミングが大きく異なる業界特性への対応が必要だからです。建設業法では、工事の適正な原価管理と経営状況の把握が求められており、そのための専用の勘定科目・会計基準が設けられています。
建設業会計が特殊な理由
- 工事期間の長期化
建設業は製造業などと比べて工事の開始から完成までが長期間にわたるため、受注から売上計上までの期間も長くなる対応する必要がある。 - 適切な期間損益計算の必要性
工事が長期間にわたることで、決算期末に利益が把握しにくくなるため、工事の進捗度に応じて売上と費用を分割して計上する期間損益計算が認められているため。 - 建設業法に基づく義務
建設業法では、許可申請や更新の際に「未成工事支出金」など、工事原価を「見える化」した財務諸表の提出が義務付けられているため。
決算変更届で使われる勘定科目
決算変更届は税務署に提出する決算書とは異なり、建設業許可の「決算変更届(事業年度終了届)」に添付する財務諸表は、建設業法施行規則に基づく「建設業会計」の様式に準拠する必要があります。そのため、税務署に提出した決算書の勘定科目が建設業法施行規則に準拠していない場合、組替え作業が必要になります。
組替える上での注意点はとしては、兼業を行っている場合は建設業特有の勘定科目と他の事業の勘定科目を適切に振り分ける必要があること。建設業特有の処理や勘定科目を正確に理解することが、決算変更届の作成をスムーズに進める上で重要になります。
建設業会計での特有の勘定科目について
建設業会計では、一般的な勘定科目に代わり「完成工事高(売上高)」「完成工事原価(売上原価)」「未成工事支出金(仕掛品)」「完成工事未収金(売掛金)」「未成工事受入金(前受金)」「工事未払金(未払金)」などが特有の勘定科目として使用されます。これらの科目は、工事の進捗状況や原価を適切に管理するために必要です。
具体的な建設業会計の勘定科目
- 完成工事高・・・(売上高に相当)
完成した建設工事の売上・収益を指す勘定科目で、一般の会計における「売上高」に相当します。建設業会計の独特な勘定科目の一つで、工事が完成して発注者に引き渡された時点で計上されます。 - 完成工事原価・・・(売上原価に相当)
会計年度内に完成した工事に要した直接的な費用の総額を指し、一般の会計における「売上原価」に相当します。材料費・労務費・外注費・経費の4つの要素で構成され、工事の完了時に損益計算書に計上されます。これにより、完成工事の利益が明確に把握できます。 - 完成工事総利益・・・(売上総利益に相当)
完成した工事の売上高(完成工事高)から、その工事にかかった直接的な費用(完成工事原価)を差し引いた金額を指します。これは、一般会計における売上総利益(粗利益)に相当します。 - 未成工事支出金・・・(仕掛品に相当)
まだ完成していない工事にかかった費用を計上するための勘定科目で、一般会計の「仕掛品」に相当します。建設工事は長期間に及ぶため、決算をまたぐ場合に、工事が完成するまでの材料費や労務費、外注費などを一旦この勘定科目に計上し、工事の進捗や収益認識の適正化を図ります。 - 完成工事未収金・・・(売掛金に相当)
工事が完成して引渡しが完了した後も、まだ請負代金の回収が済んでいない状態を指す資産勘定科目です。一般の企業で使われる「売掛金」に相当し、工事代金が後日支払われる場合に、まだ入金されていないお金を管理するために計上されます。 - 未成工事受入金・・・(前受金に相当)
まだ完成・引渡しをしていない工事の代金のうち、先に受け取った金額を指します。建設業で特有の勘定科目で、一般の会計では「前受金」に相当します。未成工事受入金は貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)では負債として計上され、工事が完了して引き渡されたときに完成工事高に対応する形で振り替えられます。 - 工事未払金・・・(未払金に相当)
建設工事の遂行のために発生した費用(労務費、材料費、外注費など)のうち、まだ支払いが完了していない金額を計上する負債の勘定科目です。建設業独自の勘定科目であり、一般会計における「買掛金」や「未払金」に相当します。
建設業は工事に長期間を要し、その間に費用が発生する一方で代金は後から受け取ることが多いため、一般的な会計とは異なる処理が必要になります。建設業会計では、工事の進捗状況を反映させる「進行基準」や「完成基準」が用いられ、それに伴い上記の勘定科目が使われています。
建設業会計の勘定科目を理解するには
建設業会計の勘定科目を理解するには、建設業特有の会計基準と勘定科目を一般企業の勘定科目と関連付けて理解するのが有効です。建設業経理士の資格を取得することで建設業会計の専門知識を体系的に学ぶ、建設業会計独自の用語や概念を学ぶ、専門知識を習得するために建設業会計に特化した研修を受けることや専門家によるサポートを受ける、建設業会計に対応した会計システムを導入することで、会計処理を効率化することも建設業会計の勘定科目を理解することに有効です。
建設業会計の相談場所は
建設業会計についての相談は相談内容によって異なります。税務や決算書の作成について専門的なアドバイスがほしい場合は、建設業に強い税理士に相談するのが最も確実です。 財務改善や経営戦略について、より専門的な視点からアドバイスがほしい場合は、経営コンサルタントに相談する方法もあります。経営全般やコンプライアンスに関する相談は、公的な窓口も活用できます。
行政書士小川真裕事務所では決算変更届の作成・提出業務を行っております。税務署に提出した決算書の勘定科目が建設業法施行規則に準拠していない場合は作成時に組替え作業をおこなっております。建設業許可における決算変更届に関してお困りの方は行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問い合わせください。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。