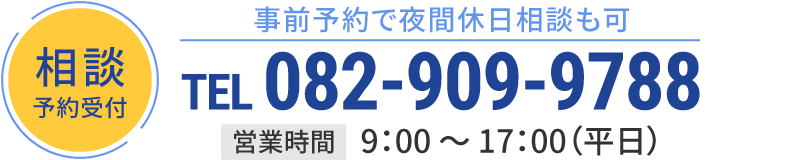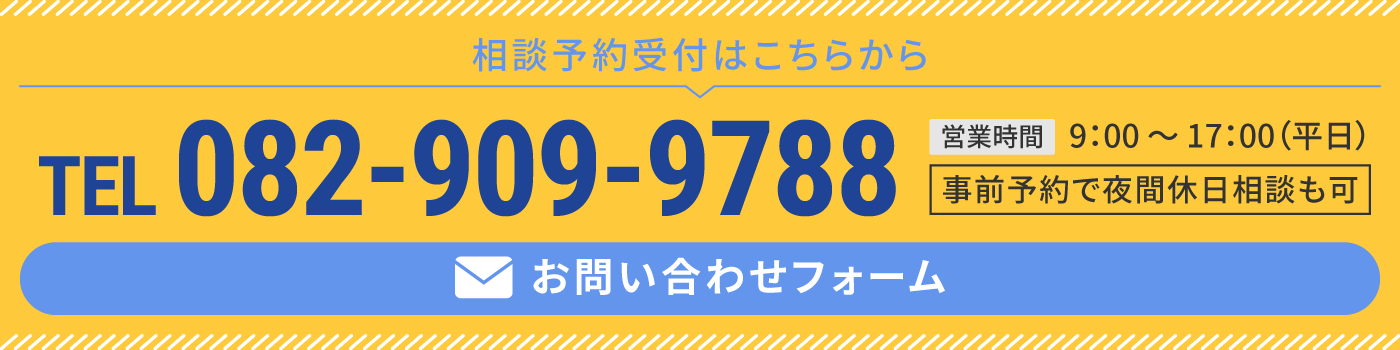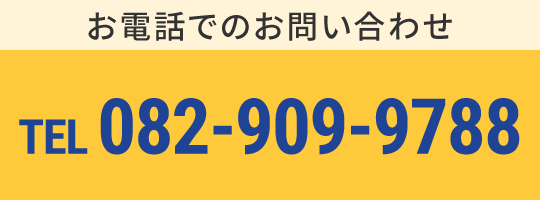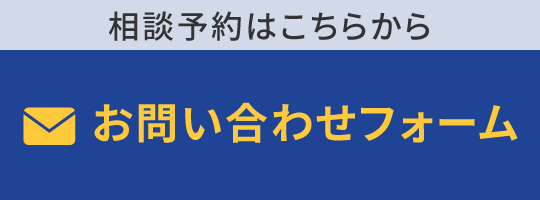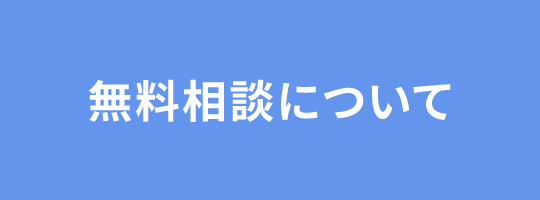建設業許可を取得した建設業者は事業年度の終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
決算変更届とは建設業許可業者(個人・法人問わず)が、その年度の工事実績や財務状況などをまとめた報告書を、許可を持つ監督官庁に提出することが建設業法で義務付けられている手続きのことをいいます。決算変更届についてまとめたコラムがこちらになります。「建設業許可取得後に届出義務が生じる決算変更届とは? 決算変更届についてまとめました。」
このページの目次
経営事項審査とは?
建設業許可における経営事項審査(経審)とは、国や地方公共団体が発注する公共工事の入札に参加する建設業者が必ず受ける必要のある審査のことをいいます。企業規模、経営状況、技術力、社会性などを客観的に審査するために指標を数値化して評価し、その結果をもとに建設業者の順位付け・格付けが行われます。
経営事項審査の目的と内容
建設業許可における経営事項審査の目的は、公共工事を発注者から直接請け負う建設業者が、国や地方自治体によって客観的・統一的な基準で評価され、適切な入札に参加できるようにするためです。この審査により、建設業者の経営規模、経営状況、技術力などを数値化し、その結果が公共工事の信頼性の確保と建設業界全体の健全な発展に貢献します。
経営事項審査の内容をまとめると以下になります。
- 公共工事入札における建設業者の成績表
公共工事の入札参加資格の取得には、経営事項審査で算出される「総合評定値(P点)」が必須となります。 - 建設業者の客観的な評価
経営事項審査を通じて、建設業者の企業規模(完成工事高、自己資本など)や経営状況、技術力、社会性(営業年数、労働福祉など)といった客観的な要素を数値化して評価します。 - 全国統一基準
経営事項審査は全国で統一された基準に基づき審査が行われるため、地域や業種に関わらず同じ評点算出式が適用されます。
経営事項審査の審査項目とは?
経営事項審査で審査される項目は、建設業者の「経営規模(X点)」、「経営状況(Y点)」、「技術力(Z点)」、「その他の審査項目(W点)」の4つの要素が審査項目となります。これらの審査項目が数値化され、その結果を総合的に評価した数値として「総合評定値(P点)」が算出されます。 このP点が公共工事の入札参加資格を判断する際の指標となります。
- 経営規模(X点)・・・建設業者の売上高(完成工事高)や自己資本、利益などを評価します。
- 経営状況(Y点)・・・経営状況分析機関が、建設業者の財務状況や経営成績など8つの指標を基に算出します。
- 技術力(Z点)・・・雇用関係にある有資格者の数や経験年数、過去の施工実績などを評価します。
- 社会性等(W点)・・・建設業の育成・確保への取り組みや防災活動への貢献、法令遵守の状況、建設機械の保有状況などが評価されます。
- 総合評定値(P点)・・・X、Y、Z、Wの各評価要素に係数を掛けて計算式に当てはめ、総合評定値(P点)が算出されます。このP点が高いほど、企業の経営基盤が安定しており、技術力も高いと判断されます。
審査項目は、公共工事の受注を希望する建設業者の能力を客観的に示し、公平で適正な入札の実施と、健全な建設業界の発展を促進することにあります。
経営事項審査と決算変更届の関係性について
決算変更届は、建設業許可業者が毎年提出する財務内容の報告書類であり、経営事項審査(経審)を受けるためには、最新の決算変更届が提出されていることが前提となります。つまり、決算変更届は経営事項審査の「前提条件」であり、最新の経営状況を把握し、経営事項審査の評点を算出するために必要不可欠な書類となります。決算変更届を提出していないと経営事項審査を受けることができません。
経営事項審査を受けるまでの流れ
経営事項審査を受けるには、まず建設業許可の取得が必要です。許可取得後、決算報告書の作成、事業年度終了届の提出を行い、その後、建設業の許可を受けた都道府県に経営規模等評価申請と総合評定値の請求を行うことで、経営事項審査の「経営事項審査結果通知書」が交付され、審査の流れが完了します。
経営事項審査を受けるための流れをまとめると以下になります。
- 建設業許可を取得する (前提)
経営事項審査を受けるためには、まず建設業許可を取得している必要があります。 - 決算報告書を作成する
会社の決算期にあわせ、決算報告書などの財務諸表を作成します。この決算日が経営事項審査の審査基準日となります。 - 事業年度終了届(決算変更届)を提出する
作成した財務諸表をもとに、建設業許可を受けた都道府県に事業年度終了届(決算変更届)を提出します。 - 経営状況分析の申請をする
国土交通大臣に登録を受けた「登録経営状況分析機関」に、経営状況分析申請を行います。分析機関から「経営状況分析結果通知書」が交付されます。 - 経営規模等評価申請と総合評定値請求をする
経営状況分析の結果通知書を受け取ったら、建設業許可を受けた都道府県(許可行政庁)へ「経営規模等評価申請書」および「総合評定値請求書」を提出します。 - 経営事項審査結果通知書の取得する
許可行政庁が経営規模等評価審査を行い、経営状況分析と経営規模等評価の結果をまとめた「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」が交付されます。
以上が経営事項審査を受けるまでの流れになります。経営事項審査を受けると交付される「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」が、公共工事の入札参加資格を得るために、自治体へ入札参加資格申請を行う際に必要となる書類になります。
経営事項審査の申請書類一覧
経営事項審査で提出する主な書類になります。
- 「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」
・法人の場合・・・損益計算書、法人税確定申告書
・個人の場合・・・損益計算書、所得税青色申告決算書又は収支内訳書 - 「工事種類別(元請)完成工事高」
・「工事種類別完成工事高業種積み上げ表」
・「工事経歴書」
・「直前3年の各事業年度度における工事施工金額」 - 「消費税等確定申告書の写し及び消費税納税証明書」
- 「技術職員名簿」
・「技術職員の常勤性確認資料」
・「技術者の資格検定合格証等の写し」
・「技術者の実務経験等内容書」 - 「その他の審査項目(社会性等)」
・「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況確認資料」
・「建設業の営業継続の状況の確認資料」
・「防災活動への貢献の状況の確認資料」
・「建設業の経理の状況の確認資料」
・「研究開発の状況の確認資料」
・「建設機械の保有状況の確認資料」
・「国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況の確認資料」 - 「経営状況分析結果報告書の原本」
前回の申請内容と照合する箇所があるため申請ではこれらの書類の他に前回の申請書類の控えを準備する必要があります。
経営事項審査の代行依頼先は?
建設業許可における経営事項審査は、公共工事の受注を希望する建設業者の経営状況や技術力などを客観的に数値化し、その信頼性を評価するための制度です。審査結果は工事の規模に応じた入札ランクの決定に使われ、発注者が適切な建設業者を選定する基準となるほか、建設業者自身も自社の強み・弱みを把握して経営改善に役立てることができます。
経営事項審査の代行依頼先は一般的には行政書士になります。行政書士に依頼するメリットとしては専門知識による書類作成の確実性と、申請手続きの迅速化、そして経営者の本業への専念があります。さらに、建設業許可取得後の手続きの管理や、入札で有利な経営事項審査の評点の最大化、専門家による継続的なサポートといった長期的な事業の発展に繋がり、事業基盤の安定化の貢献が期待できます。
行政書士小川真裕事務所では決算変更届、経営事項審査の作成・提出まで総合的に取り扱っております。総合評定値の算出方法等、決算変更届、経営事項審査についてお困りの方はお気軽に行政書士小川真裕事務所までお問い合わせください。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。