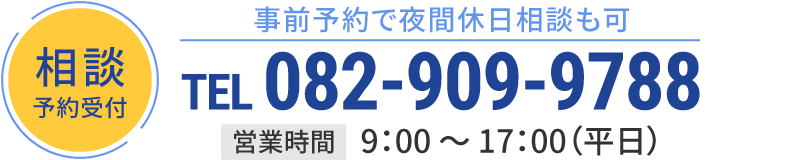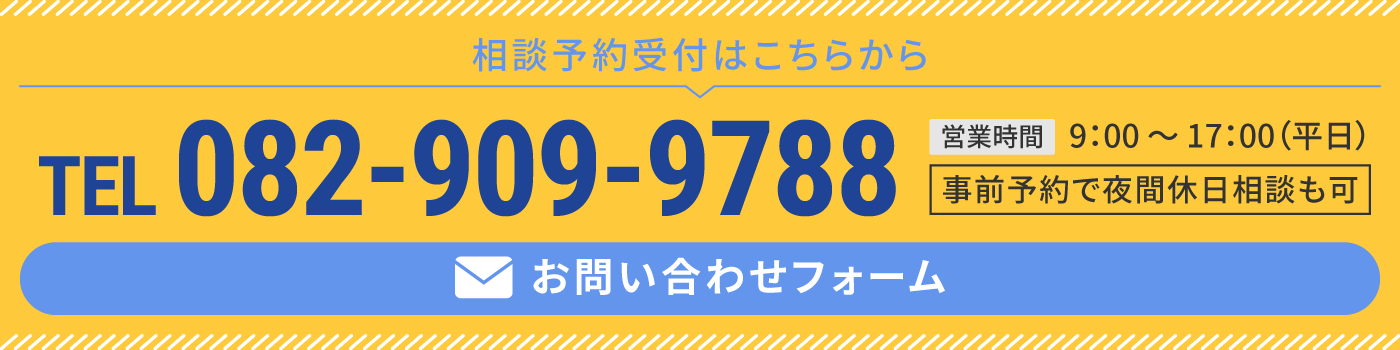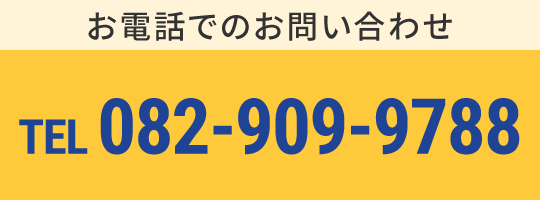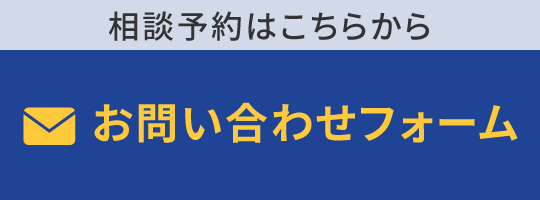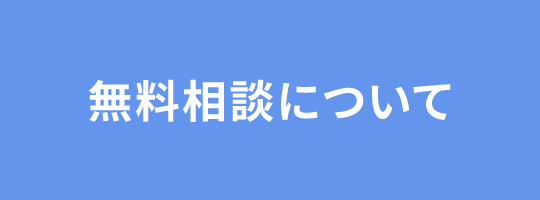Author Archive
下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」の概要①
国土交通省より標題の件につき通知がありましたので、通知内容の概要を以下にお知らせいたします。
【通達の概要(下請契約及び下請代金支払の適正化について)】
(1)下請負人が建設工事の注文者に交付する見積書
○ 見積書を踏まえた双方の協議による適正な手順にて下請代金を設定する。
○ 請負代金の額を除く請負契約書の記載事項を明示する。
○ 下請代金は、材料費、機械経費、労務費、法定福利費、安全衛生費、建退共制度の掛金、一般管理費並びに建設副産物の運搬及び処理に要する費用等の諸経費を適切に考慮し設定する。
○ 建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するため、不可欠な経費(法定福利費等)を見積書に記載する。
(2)原材料費等の高騰を踏まえた適正な請負代金の設定と適正な工期の確保
○ 価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の変更の算定方法に関する定めを契約書面に記載する。【R6.12法施行】
○ 工期又は請負代金の額を変更する際にも書面での契約変更を徹底する。
○ 請負代金に影響を及ぼす事象が発生するおそれがある場合は、受注者から注文者に対し請負契約の締結前までにその旨を通知しなければならず、当該事象の発生後受注者が請負代金の変更協議を申し出た場合は、上記通知の有無に関わらず注文者は誠実に応じること。【R6.12法施行】
○ 独禁法上の、優越的地位の濫用の要件に該当するおそれがある行為についても留意する。
(3)社会保険加入の徹底と一人親方との取引等の適正化
○ 社会保険加入が許可要件、加入状況等の施工体制台帳への記載する。
○ CCUS登録事業者を下請負人として選定することを推奨、社会保険加入状況の確認に原則CCUSを活用する。
○ 雇用する技能労働者に対し、社会保険料の本人負担分を適切に含んだ額の賃金を支払い、社会保険への加入を徹底する。
○ 請負代金内訳書に法定福利費を明示する規定を新設した建設工事標準請負契約約款等の活用する。
○ 発注者と受注者のそれぞれが「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に沿った行動を行う。
○ 「安全衛生対策項目の確認表」及び「標準見積書」を活用し、下請企業から元請企業に対して提出する見積書に安全衛生経費を内訳明示し、安全衛生経費が適切に支払われるよう取り組む。
○ 建退共制度に基づく事業主負担額等の必要な諸経費、下請負人の資金繰りや雇用確保への配慮する。
○ 建退共手続きの電子申請方式の本格実施及び証紙方式の履行確認強化によるCCUSの積極的活用・建退共制度の適切な運用する。
○ 「品確法基本方針」「入契法適正化指針」「ICT指針」に建退共手続きの電子申請方式を積極的に活用することが位置づけられたことを踏まえてCCUSと連携した電子申請方式を積極的に活用する。
(5)建設工事の請負契約の締結
○ 建設工事着工前の書面(電磁的方法を含む。)による契約締結の徹底する。
○ 建設工事標準下請契約約款又は準拠した契約書の利用する。
○ 赤伝処理をする場合は、合意に基づき契約書類に明記、指値発注の禁止する。
○ 建設リサイクル法対象工事は、必要事項を書面で相互交付する。
(6)建設業の働き方改革に向けた適正な工期設定や週休2日の推進等
○ 下請契約においても、適正な工期の確保や適正な請負代金の設定を行い、週休2日の確保や長時間労働の是正などに努める。
○ 元請負人は一人親方が現場作業に従事する際の実態を確認し、労働者に当てはまる働き方になっている場合は、雇用契約の徹底を促す。
○ 下請負人が必要経費を十分含んだ請負代金で一人親方と書面にて契約を行うよう徹底する。
(4)適正な労務費、法定福利費及び安全衛生経費等の確保
○ 建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」の適正な確保する。
○ 著しく短い工期の禁止、前工程の遅れによる後工程へのしわ寄せが生じないような工程管理する。
○ 受注者は、契約締結前又は変更契約が必要となる際に、時間外労働規制を遵守した適正な工期が確保された見積りを作成し、発注者に提出するよう努め、発注者はその内容を確認し尊重する。
○業務の繁閑が大きい場合は労使協定により1年単位の変形労働時間制を導入し、労働時間を柔軟に設定することが可能。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
人手不足を「省力化製品」の導入で解消につなげる中小企業をサポート「中小企業省力化投資補助金[カタログ注文型]」のご案内
中小企業省力化投資補助金は、経済産業省が提供する補助金のひとつで、中小企業等の人手不足解消につながるIoTやロボット等の「省力化製品」の導入費用の一部を補助する補助金です。
その特徴は、導入したい製品を自社で選定して申請するのではなく、予め用意されている「製品カタログ」に登録されている製品の中から、自社の課題、業種、業務プロセスにあった製品を選び、販売事業者と共同で申請することです。
「製品カタログ」に登録されている製品は登録時点で性能の検証がされているため、申請者は製品の性能を検証する工程が省け、比較的申請がしやすい補助金となっています。
◎目的
・省力化製品の導入で人手不足に悩む中小企業の売上拡大や生産性向上を後押しする。
・省力化投資を促進して中小企業等の付加価値の向上や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげる。
◎公募受付期間
・令和8年9月末まで
◎補助率
・1/2 以下
◎補助上限額
・従業員数 5人以下・・・200万円(大幅な賃上げを行う場合:300万円)
・従業員数 6~20人以下・・・500万円(大幅な賃上げを行う場合:750万円)
・従業員数 21人以上・・・1,000万円(大幅な賃上げを行う場合:1,500万円)
◎補助対象経費
・製品本体価格
・導入に要する費用(導入経費)
◎補助対象外となる経費
①補助事業者の顧客が実質負担する費用が省力化製品代金に含まれるもの。
②対外的に無償で提供されているもの。
③中古品。
④交付決定前に購入した省力化製品。※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
⑤公租公課(消費税)。
⑥その他、補助金の目的・趣旨から適切でないと中小企業、中小機構及び事務局が判断するもの。
◎補助対象外となる経費(導入経路)
①交付決定前に発生した費用。 また、補助事業実施期間外に発生した費用。※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
②過去に購入した製品に対する作業費用や補助対象経費となっていない製品に対する費用。
③省力化製品の導入とは関連のない設置作業や運搬費、データ作成費用やデータ投入費用等。
④省力化製品の試運転に伴う原材料費、光熱費等。
⑤補助事業者等の通常業務に対する代行作業費用。
⑥移動交通費・宿泊費。
⑦委託・外注費。
⑧補助事業者の顧客が実質負担する費用が導入設定費用に含まれるもの。(補助事業者が試作を行うための原材料費に相当すると事務局が判断するもの。)
⑨交付申請時に金額が定められないもの。
⑩対外的に無償で提供されているもの。
当該補助金は販売事業者との共同申請であり、申請後も販売事業者が申請手続きのフォローを行うため当事務所ではサポート業務は行っておりませんが、ご興味をお持ちの方はお気楽にお問い合わせください。簡単なご案内をさせていただきます。参考までに当該事業のコールセンターの連絡先をご紹介します。
中小企業省力化投資補助事業コールセンター
問い合わせ時間:9:30~17:30 / 月曜~金曜(土日祝除く)
TEL:0570-099-660

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
下請代金の支払いに関する義務について[許可取得後の留意事項の詳細⑦]
建設業法第24条の3
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
建設業における下請代金の支払いに関する義務とは、元請業者が、注文者から工事代金の支払いを受けた場合、その工事を施工した下請業者に対して、1ヶ月以内(特定建設業者の場合は、下請業者からの引渡し申出日から50日以内)に下請代金を支払う義務のことです。これは、下請業者の資金繰りを保護し、不当な取引を防止するためのものです。
(1) 元請業者の義務
・ 注文者から出来高払いまたは竣工払いを受けた場合、その工事を施工した下請業者に対して、1ヶ月以内に下請代金を支払う必要があります。(第24条の3)
・ 特定建設業者の場合、下請業者からの引渡し申出日から50日以内(特定建設業者または資本金4,000万円以上の法人である下請業者を除く)に支払う必要があります。(第24条の6)
・ 下請代金は、できる限り現金で支払うよう配慮する必要があります。(第24条の3第2項)
・ 発注者から前払金を受けた場合は、下請業者に対しても、資材購入や労働者募集など、工事着手に必要な費用を前払金として支払うよう配慮する必要があります。(第24条の3第2項)
(2) 建設業法上の規定
・ 建設業法第24条の3で、下請代金の支払期日に関する規定が定められています。
・ この規定は、契約に優先し、契約で1ヶ月を超える支払期間を定めても無効となります。
・ 支払いが遅れた場合、遅延利息が発生する可能性があります。
(3) 下請法との関係
・ 建設業法には下請法のような罰則規定はありませんが、公正取引委員会による処分を受ける可能性があります。
・ 下請法は、親事業者が下請事業者に対して、給付を受領した日から60日以内(建設業法では1ヶ月以内)に下請代金を支払うことを義務付けています。
・ 建設業では、下請代金遅延等防止法の適用はありません。
(4) 違反した場合
・ 下請代金を1ヶ月以内に支払わない場合、遅延利息が発生する可能性があります。
・ 公正取引委員会による処分を受ける可能性があります。
・ 下請法違反の場合、遅延利息の支払いだけでなく、親事業者は公正取引委員会による指導や勧告を受ける可能性があります。
(5) まとめ
・ 建設業における下請代金の支払いに関する義務は、下請業者の資金繰りを守り、不当な取引を防止するための重要な規定です。元請業者は、建設業法および必要に応じて下請法を遵守し、適正な下請取引を行う必要があります。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
工事現場における施工体制等に関する義務について[許可取得後の留意事項の詳細⑥]
建設業法第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
1. 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2. 前項の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
3. 第1項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があったときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
4. 第1項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
建設工事の施工体制等に関する義務は、建設業法によって定められており、主に以下の4点に集約されます。
①主任技術者・監理技術者の配置義務(第26条)
全ての工事現場に、工事内容に応じて主任技術者または監理技術者を配置する義務があります。(例外あり)
②専任配置義務(第26条第3項)
一定規模以上の工事では、主任技術者または監理技術者を工事現場に専任で配置し、他の工事との兼務は原則として認められません。
③一括下請負の禁止(第22条)
請け負った工事を、丸ごと他社に下請けに出す行為(一括下請負)は禁止されています。また、他社から工事を一括して下請けすることも禁止されています。
④特定建設業許可業者に関する義務
特定建設業許可業者(一定規模以上の工事を下請に出す業者)は、施工体制台帳と施工体系図を作成(第24条の8)し、下請業者への指導(第24条の7)などが課せられます。
これらの義務は、工事現場の安全確保、品質管理、適正な施工体制の確立を目的としています。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
契約締結に関する義務について[許可取得後の留意事項の詳細⑤]
建設業法第18条
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない
建設業法第19条
① 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
1. 工事内容
2. 請負代金の額
3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
4. 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
5. 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
6. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
7. 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
8. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
9. 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
10. 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
11. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
12. 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
13. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
14. 契約に関する紛争の解決方法
② 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
③ 建設工事の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
建設業における契約締結に関する主な義務は、建設工事の請負契約書を必ず作成し、工事着工前に発注者と受注者が相互に交付することです。契約書には、工事内容、請負代金の額、工期、支払条件など、法律で定められた事項を記載する必要があります。また、不当に低い請負代金での契約締結や、契約後に資材購入先を指定する行為は禁止されています。
建設業法における契約締結に関する義務の詳細(第19条)
◎書面による契約締結の義務
建設工事の請負契約は、口頭ではなく書面で契約を締結することが義務付けられています。これは、契約内容を明確にし、トラブルを未然に防ぐためです。
◎契約書に記載すべき主な項目(第19条)
・工事内容 : 具体的な工事の内容、仕様、図面などを詳細に記載します。
・請負代金の額 : 工事の総額を明確に記載します。
・工事着手の時期及び工事完成の時期 : 工事の開始日と完了日を具体的に定めます。
・工事を施工しない日又は時間帯の定め : 休業日や作業時間帯を明確にします。
・前金払又は出来高払の定め : 前払い金や出来高払いの条件、支払時期、方法を記載します。
・設計変更、工期変更、工事の中止・延期 : これらの場合の取り決め、損害負担、損害額の算定方法を明記します。
・天災その他不可抗力 : 天災などによる工期変更や損害負担、損害額の算定方法を定めます。
・価格変動 : 物価変動による請負代金や工事内容の変更ルールを定めます。
・第三者への損害 : 工事中の第三者への損害に対する賠償責任や負担を定めます。
・資材・機械の提供 : 発注者が資材や機械を提供する場合は、その内容と方法を記載します。
・検査・引渡し : 工事完成時の検査方法、検査時期、引渡時期を明確にします。
・請負代金の支払い : 工事完成後の代金支払い時期、方法を記載します。
・契約不適合責任 : 品質や種類が契約内容に適合しない場合の責任や保証について定めます。
・債務不履行 : 遅延損害金、違約金など、債務不履行時の取り決めを明記します。
・紛争解決 : トラブル発生時の解決方法を明記します。
・その他 : 国土交通省令で定められた事項や、その他特約事項があれば記載します。
◎不当に低い請負代金での契約締結の禁止(第19条の3)
元請業者は、取引上の地位を不当に利用して、下請業者に不当に低い請負代金で契約を強制してはなりません。
◎契約後の資材購入先指定の禁止(第19条の4)
元請業者は、契約後に、取引上の地位を不当に利用して、下請業者が使用する資材の購入先を指定し、下請業者の利益を害する行為を禁止されています。
◎契約書の不交付や記載不備による影響
契約書を交付しなかった場合や、記載事項に不備がある場合は、建設業法違反となり、行政指導や処分を受ける可能性があります。
◎下請負人保護(第19条の3、第20条、第24条の2等)
建設業法は、特に下請負人を保護する観点から、契約締結に関する規定を設けています。元請業者と下請業者間の契約では、取引上の地位の差が大きいため、不当な契約締結が行われやすい状況にあります。
これらの義務を遵守することで、建設工事におけるトラブルを未然に防ぎ、適正な契約関係を維持することが重要です。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
帳簿の備え付けと保存、営業に関する図書の保存義務について[許可取得後の留意事項の詳細④]
建設業法第40条の3(帳簿の備付け等)
建設業者は、営業所ごとに、 その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書を保存しなければならない。
(1) 帳簿の備え付け義務とは?
建設業許可を受けた業者は、営業所ごとに、その営業に関する事項を記載した帳簿を備え付ける必要があります。この帳簿には、請負契約の内容や工事の進捗状況、下請契約の内容など、建設業を営む上で必要な情報が記録されます。 ※本社等での一括保存は不可
(2) 帳簿の保存義務とは?
備え付けられた帳簿は、一定期間保存する必要があります。保存期間は、原則として5年間ですが、発注者と締結した住宅の新築に関する建設工事の場合は10年間と定められています。また、帳簿だけでなく、契約書や図面などの関連書類も一緒に保存する必要があります。
※帳簿の書式は事由、添付書類だけのファイリングは不可
(3) なぜ帳簿の備え付け・保存が重要なのか?
帳簿の備え付け・保存は、建設業の適正な運営を確保するために重要です。帳簿は、工事の進捗状況や費用などを記録することで、工事の透明性を高め、不正行為を防止する役割を果たします。また、紛争が発生した場合の証拠書類としても活用されます。
(4) 帳簿の記載事項
帳簿には、以下の事項を記載する必要があります。
◎ 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する以下の事項
・ 請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
・ 注文者との契約日 ・ 注文者の商号、住所、許可番号
・ 注文者による完成を確認するための検査が完了した年月日
・ 当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
◎ 下請契約に関する事項
・ 下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
・ 下請負人との契約日 ・ 下請負人の商号、住所、許可番号
・ 建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日
・ 当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
(5) 帳簿の保存方法
帳簿は、紙媒体での保存に加え、電子データでの保存も認められています。ただし、保存期間中は、いつでも帳簿の内容を閲覧できるように、適切な管理を行う必要があります。
(6) 罰則
帳簿を備え付けなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合は、10万円以下の過料が科せられることがあります。
(7) 営業に関する図書とは何か?
建設業法では、建設業者は営業所ごとに、その営業に関する事項を記載した帳簿を備え、保存することが義務付けられています。その中で、営業に関する図書とは、具体的には以下のものを指します。
完成図:
建設工事の目的物の完成時の状況を表した図面。
発注者との打ち合わせ記録:
工事内容に関する発注者との打ち合わせ内容を記録した書類で、当事者間で相互に交付されたものに限ります。
施工体系図:
(作成義務がある場合) 施工体制が明確になるように作成された図面で、一定の建設工事(公共工事における下請契約や、一定規模以上の民間工事)において作成が義務付けられています。
(8) 保存期間と保存場所
これらの営業に関する図書は、建設工事の目的物の引き渡し日から10年間、各営業所に備え付けて保存する必要があります。保存方法は、紙媒体だけでなく、データでの保存も認められています。
(9) 保存義務の対象者
営業に関する図書の保存義務があるのは、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者、つまり元請業者です。
(10) まとめ
建設業許可を持つ業者は、帳簿の備え付け・保存義務を遵守し、建設工事の適正な管理と透明性の確保に努める必要があります。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
配置技術者の設置義務について[許可取得後の留意事項の詳細③]
建設業法第26条(主任技術者・監理技術者の配置)
建設業者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として「主任技術者」を、また、元請においては下請契約の請負代金額の合計が一定以上の場合は、「監理技術者」を配置しなければならない。
(1) 配置技術者とは?
配置技術者とは、工事現場において、工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、技術者の指導監督など、工事の適正な実施に必要な技術上の管理を行う技術者のことです。主任技術者と監理技術者の2種類があります。
主任技術者: すべての建設業者(許可取得業者)が、請け負った工事現場に配置する技術者です。(軽微な工事も含む(500万円未満))
監理技術者: 元請業者が、一定額以上の下請契約を結んだ場合に配置する技術者です。(4,000千万円以上(建築一式工事:6,000千万円以上))
(2) 主任技術者・監理技術者の要件
主任技術者: 一般建設業許可で営業所技術者の要件を満たした者
監理技術者: 特定建設業許可で営業所技術者の要件を満たした者
(3) 配置技術者の専任とは?
公共性のある重要な工事では、主任技術者または監理技術者は、工事現場に専任で配置する必要があります。専任とは、他の工事現場の技術者との兼任を認めないことを意味します。(例外あり)
(4) 工事現場に専任で配置技術者を置く要件
請負金額:
1億円(建築一式工事は2億円)以上
⇒ 原則専任
4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上、1億円(建築一式工事は2億円)未満
⇒ 兼任要件を満たせば、兼任可能
4,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満
⇒ 専任不要
(5) 主任技術者等の配置技術者の兼任について
原則: 兼任はできない。
例外: 兼任要件を満たせば例外的に兼任が認められる。
(6) 営業所技術者と配置技術者の兼任について
原則: 兼任はできない。
例外: 兼任要件を満たせば例外的に兼任が認められる。
(7) 専任が必要な工事現場での兼任要件(全てに適応する必要)
■ 配置技術者が複数の現場を兼任する場合
①工事契約(法律):当該営業所において締結された工事であること
②請負金額(政令):1億円(建築一式工事は2億円)未満
③兼任現場数(政令):1工事現場
④営業所と工事現場の距離(省令):1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
⑤下請次数(省令):3次まで
⑥連絡員の配置(省令):監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建築工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
⑦施工体制を確認できる情報通信技術の措置(省令)
⑧人員の配置を示す計画書の作成、保存等(省令)
⑨現場状況を確認するための情報通信機器の設置(省令)
■ 営業所技術者と配置技術者を兼任する場合
上記①~⑨の要件と同じだが、一部内容が異なる。
①´工事契約(法律):営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
③´兼任現場数(政令):工事現場の数が1であること。
④´営業所と工事現場の距離(省令):1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内だが、工事現場間の距離ではなく、営業所から当該工事現場の距離。
⑧´人員の配置を示す計画書の作成、保存等(省令)
・営業所技術者等が所属する営業所の名称も記載
・当該建設工事に係る契約を締結した営業所の名称も記載
※営業所技術者等は、工事現場の配置技術者を兼務する場合には、当該請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある必要がある。
(8) 専任を要しない工事現場の兼任要件
■ 配置技術者の兼任の場合:無条件で複数の現場の兼任可能
■ 営業所技術者が配置技術者を兼任する場合の要件
①現場への専任が求められない工事であること
②所属する営業所で契約締結した建設工事であること
③所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
④所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること
例:ある建設会社が、営業所から1時間以内の距離にある工事現場で、専任技術者を兼任する場合、その技術者は、営業所と常に連絡を取り合い、現場の状況を把握し、必要な指示や連絡を迅速に行う必要があります。具体的には、携帯電話やスマートフォンで連絡を取り合ったり、ビデオ会議システムを利用して現場の状況を確認したりすることが考えられます。
※営業所に近接していない工事現場での配置技術者の兼務は、専任を要する工事現場の兼任要件を全て満たす場合は可能。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
標識(金看板)の提示義務について[許可取得後の留意事項の詳細②]
『建設業法第40条』
建設業許可を受けた業者は、その店舗(営業所)及び、建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(1) 提示場所
■ 店舗(営業所)の場合
・ 事務所の外観や入口付近など、誰でも見やすい場所に掲示する。
・ 事務所の内部ではなく、外部に面した場所が望ましい。
・ サイズは縦30cm×横40cm以上が一般的。
・ 記載事項
① 一般建設業又は、特定建設業の別
② 許可年月日、許可番号及び、許可を受けた建設業
③ 商号又は名称
④ 代表者の氏名
■ 工事現場の場合
・ 標識は元請に提示義務がある。
・ 工事現場の入口付近など、誰でも見やすい場所に提示する。
・ サイズは縦25cm×横35cm以上が一般的。
・ 記載事項
上記①~④
⑤ 主任技術者又は監理技術者の氏名(専任の有無、資格名、資格者証交付番号)
(2) 標識の材質
・ 材質や様式に特に規定はない。(金属、アクリル、プラスチック、紙など)
・ 一般的には耐久性があり、長時間使用できる金属製の標識がよく使われる。
・ 許可番号の変更などで標識を修正する可能性も考慮し、修正しやすい材質を材質を選ぶことも重要。
(3) 標識の入手先
・ 標識は、建設業者が自分で用意する。行政からは提供されません。
・ 標識は看板を取り扱っている店舗、又はインターネットからも入手できる。
・ 納期は店舗によって違うので事前に確認する。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
変更届の提出について[許可取得後の留意事項の詳細①]
建設業許可を取得した後、以下の変更事由に該当する場合は、届出期間内に必要書類を添付した変更届の提出が必要になりますのでご注意願います。
※各種変更届は当事務所でも作成可能ですのでご相談ください。
変更事由
1 商号・名称・・・変更後30日以内
2 営業所
①名称(従たる営業所)・・・変更後30日以内
②所在地・・・変更後30日以内
③新設(従たる営業所)・・・変更後30日以内
④廃止(従たる営業所)・・・変更後30日以内
⑤業種追加・業種廃止・・・変更後30日以内
3 資本金額・・・変更後30日以内
4 役員等
①就任・・・変更後30日以内
②辞任等・・・変更後30日以内
③代表者(建設業法上の代表者変更に限る)・・・変更後30日以内
5 個人事業主、役員等、支配人の氏名(改姓・改名)・・・変更後30日以内
6 第3条使用人
①新任・・・ 変更後2週間以内
②辞任等・・・ 変更後2週間以内
7 常勤役員等
①変更・・・ 変更後2週間以内
②削除・・・ 変更後2週間以内
8 常勤役員等を直接補佐する者
①変更・・・ 変更後2週間以内
9 健康保険等の加入状況
①変更(変更内容が従事者数のみを除く)・・・変更後2週間以内
10 営業所技術者等
①変更追加・・・変更後2週間以内
②削除・・・変更後2週間以内
11 決算変更届(毎年提出)・・・事業年度終了後4か月以内
12 廃業届・・・変更後30日以内
《留意事項》
〇 変更届の提出に当たっては、届出書様式番号の書類及び添付書類・確認資料が それそれ必要になります。
〇 届出期間は、変更した翌日から起算します。
〇 変更届等は届出期間内に提出する必要があります。未提出の変更届等がある場合、 更新申請(5年に一回)は受理されません。また、許可要件を欠くこととなった場合には、 許可の取り消しになりますのでご注意願います。
〇 変更届等を提出しなかった場合、虚偽の記載をして提出した場合には、法では罰則 (六月以下の懲役又は百万円以下の罰金)が規定されています。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
建設業許可取得後の留意事項について
建設業許可取得後の留意事項について、以下の点にご注意願います。 留意事項についてご不明点があればご連絡願います。
(1) 建設業許可の有効期間について
建設業許可はいちど取得すれば終わりではなく、5年の有効期間が定められています。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間の満了する日の30日前までに更新の申請を提出してください。(広島県の場合)
(2) 変更届について
申請書類に変更事由が発生した場合は変更届を提出します。変更届には提出期間が定めれており期間内に提出する必要があります。また、決算については、毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届を提出してください。各種変更届が未提出の場合、更新申請が受けられない。許可の取消し等の罰則が科せられる場合があります。
(3) 廃業届について
事業を廃止した場合は廃業届を提出してください。廃業届について許可を受けた建設業の全部又は一部を廃業した場合は、30日以内に廃業届を提出する必要があります。 個人の許可業者が法人成りし、建設業許可が必要な場合には、個人の許可を廃止し、法人として、新規の許可を取得してください(承継に係る認可を受ける場合を除く。)。
(4) 経営事項審査について
公共工事への入札参加を希望される場合は、経営事項審査を毎年受けてください。また、 入札参加には参加を希望する各自治体ごとに入札参加申請が必要になります。
(5) 法令遵守について
以上の留意事項の他に、許可を受けた建設業者には建設業法に定められた義務が課せられます。以下が代表的な義務になります。法令違反をした場合、許可の取消等の行政処分に繋がりますので注意してください。
・ 標識の表示義務 (建設業法第40条)
・ 配置技術者の設置 (建設業法第26条)
・ 帳簿の備え付けと保存、営業に関する図書の保存義務 (建設業法第40条の3)
・ 契約締結に関する義務 (建設業法第18条、19条)
・ 工事現場における施工体制等に関する義務 (建設業法第24条の7、8等)
・ 下請代金の支払いに関する義務 (建設業法第24条の3、6)
以上が許可取得後の主な留意事項になります。法令遵守の内容について別コラムにて説明する予定です。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。