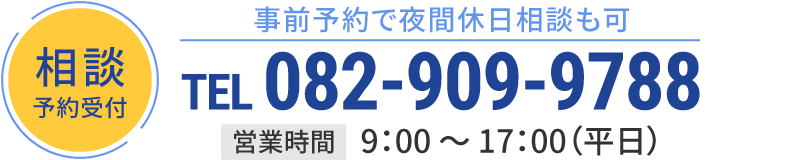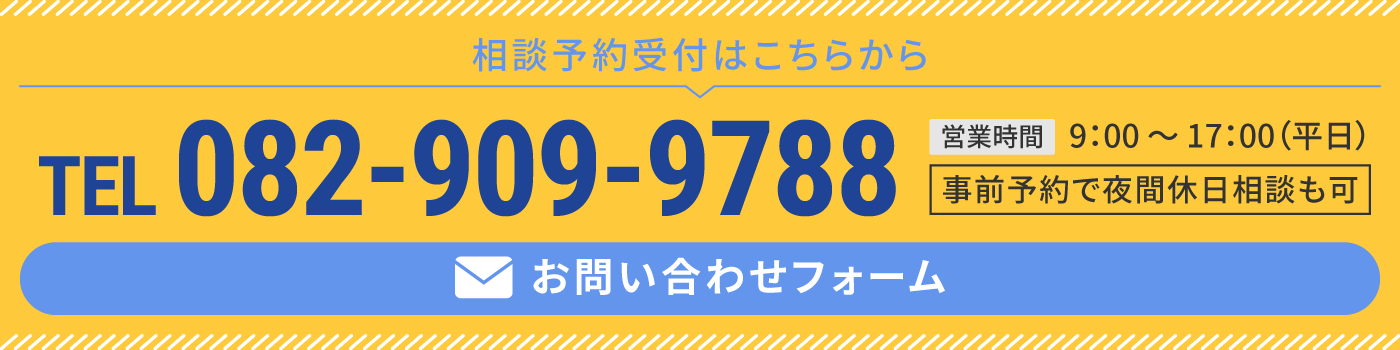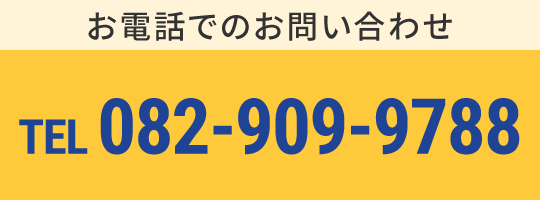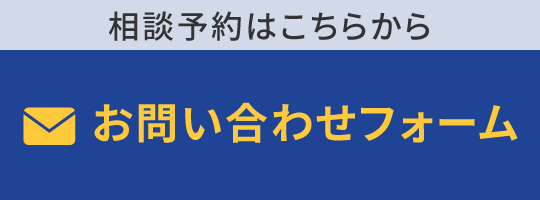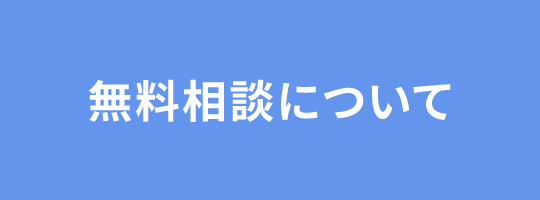お知らせ
下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」の概要②
前日のお知らせの続きになります。
【通達の概要(施工管理の徹底等について)】
(7)施工管理の徹底
○ 発注者の信頼に応えうる適切な施工計画、施工体制の十分な確保、工程管理や工事目的物・工事用資材等の品質管理、安全管理等一層を徹底する。
○ 施工体制台帳及び施工体系図(デジタルサイネージ等ICT機器を含む)の作成、備え置きを徹底する。
○ 主任技術者の専任等の取り扱いに十分留意する。
(8)検査及び引渡し
○ 工事完成通知日から20日以内で、できる限り短期間に検査を完了する。
○ 検査完了後、下請負人から申し出があったときは、直ちに引渡しをする。
(9)適切な下請代金の支払
○ 少なくとも労務費相当分(社会保険料の本人負担分を含む。)を現金払とするよう支払条件を設定する。
○ できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合には、現金の比率を高める。
○ 手形等の現金化にかかる割引料等のコストなどを十分協議した上で明示し、一方的に下請負人の負担としない。
○ 令和8年の手形の利用廃止等に向けて、振込払及び電子記録債権への移行・手形期間の短縮等の取り組みを進めていくよう努める。
○ 特定建設業者は、一般の金融機関による割引困難な手形の交付を禁止する。
○ 令和6年11月から、60日を超える手形は「割引困難な手形」に違反するおそれがあるものとして指導対象となったことに留意する。
○ 支払を受けた日から1月以内でできる限り短期間での支払をする。
○ 特定建設業者は、完成を確認した後、引渡しの申出日から50日以内で、できる限り短期間での支払をする。
○ 前払金受領時の適正な支払及び中間前金払制度の積極的な活用をする。
○ 正当な理由のない長期間の支払保留を禁止する。
(10)下請負人への配慮等
(11)技能労働者への適切な賃金の支払
○ 公共工事設計労務単価の上昇(13年連続)等を踏まえ、技能労働者に対する適切な水準の賃金を支払われるよう最大限努める。
○ 建設業との賃上げ等に関する車座対話において、技能者の賃上げについて「おおむね6%の上昇」を目標とすることを申し合わせる。
○ CCUSを活用し、建設技能者が適切に就業履歴を蓄積できるよう、カードリーダーの設置や施工体制登録等を適切に指導する。
○ 「CCUSレベル別年収」の公表を踏まえ、技能労働者が能力評価を受けるよう促し、適切な処遇を受けられるよう環境整備を推進する。
○ 品確法、新労務単価、社会保険加入対策、価格転嫁に関する相談等の窓口である「建設業フォローアップ相談ダイヤル」の活用及び周知する。
(12)免税事業者等との適正な取引
○ 自己の取引上の地位を不当に利用し、一方的に消費税相当額の一部(全部)を支払わない行為や優越した地位を濫用した行為は、建設業法、独禁法の規定に違反するため十分留意する。
○ 下請負人との取引にあたっては、消費税相当額の取引価格への反映の必要性等について、下請負人と十分な協議を行い、双方対等な立場における合意に基づいて取引価格を設定する。
(13)国土交通大臣等への通報を理由とする不利益取扱いの禁止
○ 監督行政庁への通報を理由とした取引の停止など不利益な取扱を禁止する。
(14)「駆け込みホットライン」の周知
○ (1)~(13)の建設業法上の規定に抵触する取引については「駆け込みホットライン」の活用・周知する。
○ 「駆け込みホットライン」に通報があり、通報者が匿名を希望する場合は通報者が特定されぬよう調査方法を工夫する。
(15)建設工事の関係者への配慮
○ 全ての下請負人に対し、請負代金・賃金の不払等、不測の損害を与えない。
○ 「下請セーフティネット債務保証事業」及び「地域建設業経営強化融資制度」の活用による支払の適正化。
○ 特定建設業者は、下請負人による技能労働者への賃金不払の防止に努めるなど下請契約の関係者保護に特に配慮する。
○ 下請中小企業振興法振興基準の観点から、建設工事の関係者(資材業者・賃貸業者・警備業者・運送事業者・建設関連業者等)との取引においても、振興基準に示す事項に配慮する。
○ 下請代金支払遅延等防止法が改正され、製造委託等代金の支払について、令和8年1月1日から手形の交付、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段も併せて禁止となることに留意する。
○(1)~(13)の事項に準じて配慮する。
以上になります。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」の概要①
国土交通省より標題の件につき通知がありましたので、通知内容の概要を以下にお知らせいたします。
【通達の概要(下請契約及び下請代金支払の適正化について)】
(1)下請負人が建設工事の注文者に交付する見積書
○ 見積書を踏まえた双方の協議による適正な手順にて下請代金を設定する。
○ 請負代金の額を除く請負契約書の記載事項を明示する。
○ 下請代金は、材料費、機械経費、労務費、法定福利費、安全衛生費、建退共制度の掛金、一般管理費並びに建設副産物の運搬及び処理に要する費用等の諸経費を適切に考慮し設定する。
○ 建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するため、不可欠な経費(法定福利費等)を見積書に記載する。
(2)原材料費等の高騰を踏まえた適正な請負代金の設定と適正な工期の確保
○ 価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の変更の算定方法に関する定めを契約書面に記載する。【R6.12法施行】
○ 工期又は請負代金の額を変更する際にも書面での契約変更を徹底する。
○ 請負代金に影響を及ぼす事象が発生するおそれがある場合は、受注者から注文者に対し請負契約の締結前までにその旨を通知しなければならず、当該事象の発生後受注者が請負代金の変更協議を申し出た場合は、上記通知の有無に関わらず注文者は誠実に応じること。【R6.12法施行】
○ 独禁法上の、優越的地位の濫用の要件に該当するおそれがある行為についても留意する。
(3)社会保険加入の徹底と一人親方との取引等の適正化
○ 社会保険加入が許可要件、加入状況等の施工体制台帳への記載する。
○ CCUS登録事業者を下請負人として選定することを推奨、社会保険加入状況の確認に原則CCUSを活用する。
○ 雇用する技能労働者に対し、社会保険料の本人負担分を適切に含んだ額の賃金を支払い、社会保険への加入を徹底する。
○ 請負代金内訳書に法定福利費を明示する規定を新設した建設工事標準請負契約約款等の活用する。
○ 発注者と受注者のそれぞれが「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に沿った行動を行う。
○ 「安全衛生対策項目の確認表」及び「標準見積書」を活用し、下請企業から元請企業に対して提出する見積書に安全衛生経費を内訳明示し、安全衛生経費が適切に支払われるよう取り組む。
○ 建退共制度に基づく事業主負担額等の必要な諸経費、下請負人の資金繰りや雇用確保への配慮する。
○ 建退共手続きの電子申請方式の本格実施及び証紙方式の履行確認強化によるCCUSの積極的活用・建退共制度の適切な運用する。
○ 「品確法基本方針」「入契法適正化指針」「ICT指針」に建退共手続きの電子申請方式を積極的に活用することが位置づけられたことを踏まえてCCUSと連携した電子申請方式を積極的に活用する。
(5)建設工事の請負契約の締結
○ 建設工事着工前の書面(電磁的方法を含む。)による契約締結の徹底する。
○ 建設工事標準下請契約約款又は準拠した契約書の利用する。
○ 赤伝処理をする場合は、合意に基づき契約書類に明記、指値発注の禁止する。
○ 建設リサイクル法対象工事は、必要事項を書面で相互交付する。
(6)建設業の働き方改革に向けた適正な工期設定や週休2日の推進等
○ 下請契約においても、適正な工期の確保や適正な請負代金の設定を行い、週休2日の確保や長時間労働の是正などに努める。
○ 元請負人は一人親方が現場作業に従事する際の実態を確認し、労働者に当てはまる働き方になっている場合は、雇用契約の徹底を促す。
○ 下請負人が必要経費を十分含んだ請負代金で一人親方と書面にて契約を行うよう徹底する。
(4)適正な労務費、法定福利費及び安全衛生経費等の確保
○ 建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」の適正な確保する。
○ 著しく短い工期の禁止、前工程の遅れによる後工程へのしわ寄せが生じないような工程管理する。
○ 受注者は、契約締結前又は変更契約が必要となる際に、時間外労働規制を遵守した適正な工期が確保された見積りを作成し、発注者に提出するよう努め、発注者はその内容を確認し尊重する。
○業務の繁閑が大きい場合は労使協定により1年単位の変形労働時間制を導入し、労働時間を柔軟に設定することが可能。
長文になりましたので続きは次回のコラムお知らせします。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
人手不足を「省力化製品」の導入で解消につなげる中小企業をサポート「中小企業省力化投資補助金[カタログ注文型]」のご案内
中小企業省力化投資補助金とは
中小企業省力化投資補助金は、経済産業省が提供する補助金のひとつで、中小企業等の人手不足解消につながるIoTやロボット等の「省力化製品」の導入費用の一部を補助する補助金です。
その特徴は、導入したい製品を自社で選定して申請するのではなく、予め用意されている「製品カタログ」に登録されている製品の中から、自社の課題、業種、業務プロセスにあった製品を選び、販売事業者と共同で申請することです。
「製品カタログ」に登録されている製品は登録時点で性能の検証がされているため、申請者は製品の性能を検証する工程が省け、比較的申請がしやすい補助金となっています。
中小企業省力化投資補助金の概要
◎目的
・省力化製品の導入で人手不足に悩む中小企業の売上拡大や生産性向上を後押しする。
・省力化投資を促進して中小企業等の付加価値の向上や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげる。
◎公募受付期間
・令和8年9月末まで
◎補助率
・1/2 以下
◎補助上限額
・従業員数 5人以下・・・200万円(大幅な賃上げを行う場合:300万円)
・従業員数 6~20人以下・・・500万円(大幅な賃上げを行う場合:750万円)
・従業員数 21人以上・・・1,000万円(大幅な賃上げを行う場合:1,500万円)
◎補助対象経費
・製品本体価格
・導入に要する費用(導入経費)
◎補助対象外となる経費
①補助事業者の顧客が実質負担する費用が省力化製品代金に含まれるもの。
②対外的に無償で提供されているもの。
③中古品。
④交付決定前に購入した省力化製品。※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
⑤公租公課(消費税)。
⑥その他、補助金の目的・趣旨から適切でないと中小企業、中小機構及び事務局が判断するもの。
◎補助対象外となる経費(導入経路)
①交付決定前に発生した費用。 また、補助事業実施期間外に発生した費用。※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
②過去に購入した製品に対する作業費用や補助対象経費となっていない製品に対する費用。
③省力化製品の導入とは関連のない設置作業や運搬費、データ作成費用やデータ投入費用等。
④省力化製品の試運転に伴う原材料費、光熱費等。
⑤補助事業者等の通常業務に対する代行作業費用。
⑥移動交通費・宿泊費。
⑦委託・外注費。
⑧補助事業者の顧客が実質負担する費用が導入設定費用に含まれるもの。(補助事業者が試作を行うための原材料費に相当すると事務局が判断するもの。)
⑨交付申請時に金額が定められないもの。
⑩対外的に無償で提供されているもの。
おわりに
当該補助金は販売事業者との共同申請であり、申請後も販売事業者が申請手続きのフォローを行うため行政書士小川真裕事務所ではサポート業務は行っておりませんが、ご興味をお持ちの方はお気楽にお問い合わせください。簡単なご案内をさせていただきます。参考までに当該事業のコールセンターの連絡先をご紹介します。
中小企業省力化投資補助事業コールセンター
問い合わせ時間:9:30~17:30 / 月曜~金曜(土日祝除く)
TEL:0570-099-660

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
行政書士制度PRポスターモデル(水谷隼氏)が出演するPR動画が日本行政書士会連合会より公開されました。※動画(YouTube)あり
行政書士制度PRポスターモデルの水谷隼氏(元プロ卓球選手で東京オリンピック混合ダブルス金メダリスト)が出演する行政書士制度PR動画が日本行政書士会連合会より公開されました。
本動画につきましては下記のYou Tubeチャンネルにおいて公開しておりますので是非ご覧ください。今後とも「街の頼れる法律家 行政書士」を宜しくお願いいたします。
1.YouTube動画URL:https://youtu.be/p3ZLCHfD0oc
2.公開期間:令和7年8月1日(金)10時 ~ 令和8年7月31日(金)17時
3.留意事項:本動画データの提供はできませんのでご了承ください。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
令和7年度建設業労働環境改善等助成事業のお知らせ
広島県では建設業の担い手確保を推進することを目的として、新規雇用の拡大に向けて労働環境の改善等に取り組む県内の中小建設業者に対し、設備投資等に要した費用の一部を助成する制度をおこなっています。制度の名称を建設業労働環境改善等助成事業といいます。
《助成対象事業者》
助成対象事業者は、職場の魅力向上・従業員定着などにつながる労働環境の改善等に取り組む者のされており、以下の方が該当します。
(1)広島県知事の建設業の許可を受けて建設業を営む中小企業事業主であって、県内に主たる営業所を有する者であること。
(2)建設労働者を雇用して建設事業を行っていること。
(3)ハローワーク又は広島県求人情報サイト等で、県内の営業所で雇用する建設労働者に係る求人を現に行っていること。
(4)県税の滞納がないこと。
(5)過去3年間に労働関係法令に違反する重大な事実がないこと。
《助成対象経費》
助成金の対象となる経費は、次のとおりです。なお、すべて消費税及び地方消費税を除きます。
■労働環境改善経費
助成対象事業者が実施する、建設労働者の労働環境の改善に資する次に掲げる施設もしくは設備または備品(※)の新設、増設もしくは改修または購入に要する経費
- 女性専用施設等(トイレ、更衣室、シャワー室、休憩室等)
- 熱中症対策・防寒備品等(大型冷風機・暖房器具等)
- その他労働環境の改善に資すると知事が認めるもの
※付属品等を含み、備品1点あたり総額10万円以上であるものに限る。また、公共工事において積算に含まれるもの及び発注者と受注者の協議により発注者の負担で現場に設置されるものを除きます。
■資格取得経費
助成対象事業者が建設労働者に取得させる建設関係資格の取得に要する経費(受講料、教材費、旅費(※)等)
※県外等遠方への旅費の場合、その場所ではないと受講や資格取得ができない合理的な理由があるものに限ります。
■現場見学会等開催経費
助成対象事業者が新規に入職しようとする者を対象に開催する現場見学会、講習会、体験学習及びインターンシップに要する経費(広報費、機械器具等借上料、教材費、傷害保険料、参加者用借り上げバス等)
■建設事業の生産性向上に関する講習会経費
助成対象事業者が建設労働者に受講させる、生産性向上に関する講習会に要する経費(受講料、自社開催時の講師謝金、教材費等)
ただし、以下の項目に該当する事業は、交付の対象外となります。
(1)当該年度の1月31日までに完了しない事業
(2)申請書の提出時において既に着手されている事業
(3)同一の年度において既に助成金の交付の決定を受けた者が行う事業
(4)他の助成金等の交付を受けて行われる事業
《助成率及び交付額》
助成対象経費(実費相当額)に助成率2分の1を乗じた額又は上限50万円のいずれか低い額とします。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てます。
《交付までの流れ》
(1)広島県電子申請システムから助成金支給の申請をします。
※実際の着手は、県の交付決定日以降としてください。申請の前に着手した場合は認められません。
(2)申請内容に基づく審査の開始、交付決定の通知(県)がされます。
(3)助成事業を実施、完了させます。
※交付決定の後に実施のうえ、当該年度の1月31日までに完了してください。
(4)広島県電子申請システムにより実績を報告します。
(5)助成額の確定通知(県)がされます。
(6)助成金が支払い(県)されます。
《交付申請等受付期間》
【交付申請受付期間】
令和7年5月26日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで
【実績報告受付期間】
助成事業が完了した日(領収日)から起算して30日を経過する日又は令和8年2月27日(金曜日)のいずれか早い日まで
なお、申請は先着順とし、交付決定額が予算枠に達したときは、同日以前に受付を終了します。※申請書及び添付書類がすべて提出された時点で申請を受け付けます。
《申請・実績報告の提出先》
広島県電子申請システムにて、必要書類を添付して提出します。
なお、申請の取下げ、事業内容の変更、事業の中止及び廃止を行うときは、建設産業課に連絡後、所定の様式をメールで提出します。
《提出書類》
■交付申請時
・建設業労働環境改善等助成金交付申請書
・添付書類
(共通)
ア 誓約書(様式第1-2号)
イ 事業計画書(別紙1)及び所要額調書(別紙2)
ウ 会社案内又は会社概要(資本金及び従業員規模がわかるもの)
エ 実施予定事業に係る見積書の写し(※広島県内に本社を置く複数の事業者からの見積り。困難な場合は、その理由書)
オ 県内の営業所で雇用する建設労働者に係る求人を行っていることがわかる書類(ハローワークの求人票又は広島県求人情報サイトの採用ページの写し等。交付決定後に求人活動を行う場合は、その旨の誓約書。)
カ 資格要件確認申立書(労働環境改善に資する事業のみ)
キ 当該事業を実施する場所の位置図(移動式の場合を除く)
ク 事業実施前の状態が分かる写真(移動式の場合を除く)
ケ 整備内容がわかる書類(施設・設備の構造・仕様等を示した図面・カタログ等)
■実績報告時
・建設業労働環境改善等助成金実績報告書(様式第5号)
・添付書類
ア 事業実績報告書(別紙1)及び所要額調書(別紙2)
イ 実施内容がわかる書類(施設・備品の写真、資格者証の写し、現場見学会の写真等)
ウ 費用の内訳がわかる書類(請求内訳書等の写し)
エ 費用の支払いが確認できる書類(領収書等の写し)
オ (申請時に未提出の場合)県内の営業所で雇用する建設労働者に係る求人を行っていることがわかる書類
カ 口座振替依頼書(様式第6号)
以上になります。該当する事業者様は検討してみる価値はあるのではないでしょうか。当事務所は当該制度の申請サポートをおこなっています。お気軽にご相談ください。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)の改正内容をまとめました。
品確法・建設業法・入契法の3法を一体的に改正する「第三次・担い手3法」(建設業法・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律・公共工事の品質確保の促進に関する法律)が令和6年6月に公布されましたので改正内容についてお知らせします。
改正の背景には厳しい就労条件を背景に依然として就業者の減少が著しく、持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手を確保に向けた取組を強化することが急務となっていることが挙げられます。
※品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)
※入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)
第三次・担い手3法の改正内容
これらの課題に対応するため担い手3法では「担い手確保」「生産性向上」「地域における対応力強化」を目的に改正されました。
担い手の確保
<品確法>
休日の確保の促進
- 国が実態を把握・公表し、施策を策定・実施
- 自治体内の関係部局が連携した平準化の促進
処遇改善の推進
- 労務費・賃金の支払実態を国が把握・公表し、施策を策定・実施
- 能力に応じた適切な処遇の確保
- 適切な価格転嫁対策※による労務費へのしわ寄せ防止
※スライド条項の設定、運用基準の策定、適切な代金変更
担い手確保のための環境整備
- 担い手の中長期的な育成・確保に必要な措置の実施
※訓練法人支援、学校と業界の連携、外国人など多様な人材確保 - 品質確保や担い手の活動につき国民の関心を深める広報活動
- 担い手確保に留意した調査等に係る資格等の評価・運用の検討
測量業の担い手確保【測量法】
- 測量士等の確保(養成施設や資格に係る要件の柔軟化、資格の在り方の検討規定)
- 測量業の登録に係る暴力団排除規定 等
<建設業法・入契法>
労働者の処遇改善
- 労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化
国は、取組状況を調査・公表、中央建設業審議会へ報告 - 標準的な労務費の勧告
中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告 - 適正な労務費等の確保と行き渡り
・著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止
・国土交通大臣等は、違反発注者に勧告・公表(違反建設業者には指導・監督) - 原価割れ契約の禁止を受注者にも導入
資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
- 契約前のルール
・資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化
・資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象(リスク)の情報について、契約前に、受注者から注文者に通知するよう義務化 - 契約後のルール
・資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努力義務※
※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務
働き方改革
- 長時間労働の抑制
工期ダンピング対策を強化(著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止)
<生産性向上>
<品確法等>
新技術の活用・脱炭素化の促進
- 調査等や発注から維持管理までのICT活用(データの活用、データ引継等)
- 脱炭素化の促進
- 新技術活用の適切な評価、予定価格への反映
技術開発の促進
- 技術開発の継続的な推進、民間事業者間の連携促進
<建設業法・入契法>
ICTを活用した生産性の向上
- 現場技術者に係る専任義務を合理化(例. 遠隔通信技術の活用)
- 国が現場管理の「指針」を作成(例. 元下間で工事図面等のデータを共有)
特定建設業者※や公共工事発注者に効率的な現場管理を努力義務化
※多くの下請業者を使う建設業者 - 公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化(ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可)
「地域における対応力強化」
<品確法等>
地域建設業等の維持に向けた環境整備
- 適切な入札要件等による発注
地域の実情を踏まえた適切な条件・発注規模等による発注等 - 災害対応力の強化
・災害対応経験者による被害把握
・技術力ある業者と地域の業者が連携した迅速復旧、技術移転等
・災害工事での労災保険契約の締結促進、予定価格への反映
公共工事等の発注体制の強化
- 発注者への支援充実
・発注職員の育成支援、発注事務の実態把握・助言
・維持管理を広域的に行うための連携体制構築 - 入札契約の適正化に係る実効確保【入契法】
・国が定める入札契約適正化指針の記載事項に「発注体制の整備」を追加
・指針に即した措置の実施を発注者に助言・勧告
施工期日
<品確法等>
公布日(令和6年6月19日)に施行(ただし、測量法の改正規定に関しては、令和7年4月1日に施行)
<建設業法・入契法>
処遇確保等の取組状況を国が調査する権限と、中央建設業審議会が「労務費の基準」を勧告する権限に関しては、令和6年9月1日に施行
価格転嫁協議の円滑化、ICT活用による現場管理の効率化、現場技術者の専任義務合理化等に関しては、令和6年12月13日に施行
著しく低い労務費等の禁止、受注者による原価割れ契約の禁止、工期ダンピング対策の強化等に関しては、令和7年12月頃に施行
以上になります。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
「資本性借入金」に係る経営事項審査の事務取扱いが変更されました。令和7年1月改正(国土交通省)
令和7年6月25日に国土交通省より「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて」の通知がありましたのでお知らせします。
通知の内容は経営事項審査における資本性借入金の取扱いについてです。改正前は「負債」とみなされていた資本性借入金を、令和7年1日以降の改正後からは一定の要件を満たした資本性借入金については「自己資本」とみなすことができるように変更されたことです。
資本性借入金として認められる要件
①貸出主が金融機関(政府系を含む)又は『産業復興機構による既往債権の買取制度』等の制度からの借入れであること。
②償還期限が5年を超えるもの。
残存期間が5年未満となった資本性借入金は、1年ごとに20%ずつ自己資本とみなす部分を逓減させる取扱いになります。
③金利設定が配当可能利益に応じている。
業績連動型が原則で、債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が抑えられるような仕組みが講じられている。
④法的破綻事の劣後性が確保されていること。
少なくとも法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収されない仕組みが講じられている。
⑤期限一括償還になっていること。
「資本性借入金」とみなして取り扱うことが可能なものと考えられる関係省庁等の制度
①日本政策金融公庫
・挑戦支援資本強化特例制度
・新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度
・災害対応型劣後ローン
②日本政策投資銀行・商工中金
・危機対応業務による中小・中堅・大企業向け劣後ローン
③その他
・中小企業活性化協議会版「資本性借入金」
・中小企業活性化協議会版「資本性借入金」(新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度協調型)
・産業復興機構による既往債権の買取制度
・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構による既往債権の買取制度
・農林漁業経営資本強化資金
申請方法と必要書類
①申請前の事前準備
・公認会計士等から指定様式において資本性借入金に該当する借入金であること等の証明をうける。
・証明者は公認会計士・税理士・建設業経理士1級のみに限定。在籍先(社内・社外)は不問、建設業経理士1級の場合、登録経理試験の合格年月日又は登録経理講習の修了年月日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない方に限定されます。
②登録経営状況分析機関への提出
・経営状況分析申請において、余白に資本性借入金のうち自己資本と認められる金額を記載した経営状況分析申請書等を提出する。
・添付資料:「資本性借入金」該当証明書、当該借入金にかかる契約書(契約書がない場合は該当証明書の記載事項の内容が確認できる資料)
③審査行政庁(経営事項審査)への提出
・経営規模等評価申請書の自己資本額において、資本性借入金のうち自己資本と認められる金額を加算した自己資本額を記載し、証明書の写しを添付して審査行政庁に申請する。
これまで負債としてみなされた資本性借入金が自己資本とみなされることで経営事項審査における評点の改善に繋がります。該当する可能性のある関係省庁の制度を利用されている事業主様は担当行政書士に一度ご相談されてはいかがでしょうか。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。