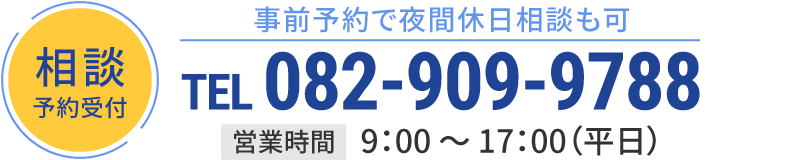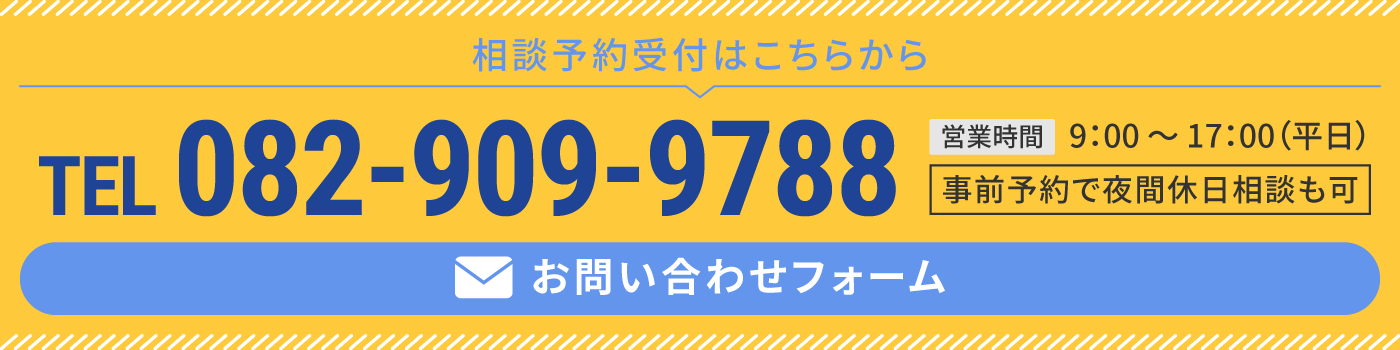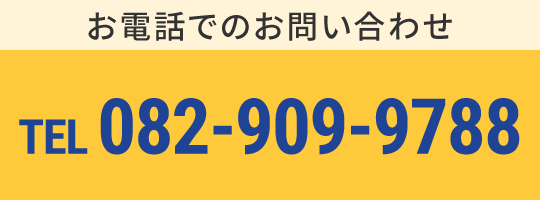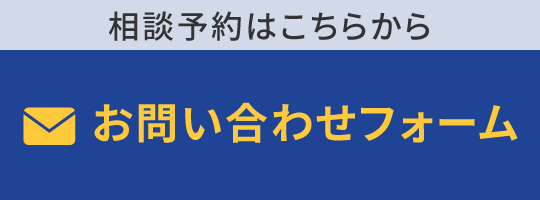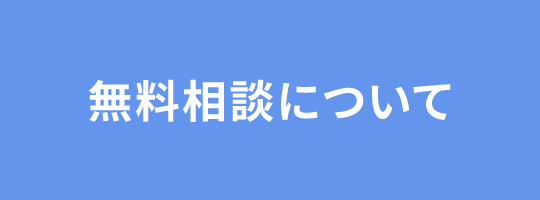コラム【建設業許可】
建設業会計とは? 決算変更届は建設業会計に基づく財務諸表で提出します。
建設業会計とは
建設業会計とは、長期の工事を主な事業とする建設業の特殊な商習慣に対応するために設けられた、建設業独自の会計処理のことです。一般的な会計とは異なり、長期工事の収益を計上する基準が「工事進行基準」か「工事完成基準」のいずれかを選択できる点や、「未成工事支出金」や「完成工事高」といった特有の勘定科目を使用する点が特徴です。建設業許可を取得する際には、この建設業会計に基づいた財務諸表の作成・提出が必要となります。
建設業会計が必要な理由としては、建設業では土木・建築工事の着工から引き渡しまで1年以上と工事期間が長期化することが多く、複数の決算期をまたぐのが一般的です。そのため、一般的な会計処理では収支状況を正確に把握することが難しくなります。 また、特殊な商習慣への対応や工事の進捗や完了のタイミングで収益と費用を計上する必要があるため、独自の会計ルールを設ける必要があったためです。
「工事進行基準」とは
工事進行基準とは、建設業などで用いられる請負契約における会計方法で、工事の進捗度に応じて売上や費用を決算期ごとに分散して計上するものです。
この基準では、工事の「工事収益総額」「工事原価総額」「工事進捗度」が合理的かつ信頼性をもって見積もれる場合に適用され、工事の収益性を早期に把握できるメリットがある一方、進捗度の測定や管理体制の整備が複雑になるデメリットもあります。なお、2021年4月からは「収益認識に関する会計基準」が導入され、従来の工事進行基準は事実上廃止されていますが、収益認識の考え方自体は新基準に引き継がれています。
「工事完成基準」とは
建設業許可における工事完成基準とは、工事が完成し、その目的物の引き渡しが完了した時点で、工事の収益と原価を一度に計上する会計方法です。つまり、工事が始まる前から完了までの期間全体で発生した費用は、工事が完成して引き渡した会計年度にまとめて売上とともに計上される方式です。
工事完成基準のメリットとしては、収益と費用が明確で、会計上の確実性が高い。工事が終了するまで売上が計上されないため、税負担を遅らせることで資金繰りに有利になる場合がある。 デメリットとしては期間業績の判定が難しく、工事の期間中の業績を正確に把握しにくい。工事期間が長期にわたる場合、途中でクライアントからの修正依頼などが発生しても、完了するまで赤字が明らかになりにくく、受注側の負担が大きくなることがあります。
「工事進行基準」と「工事完成基準」のどちらを採用するべきか
「工事進行基準」と「工事完成基準」のどちらを採用するべきかは、まずは長期大規模工事に該当するかを確認します。長期大規模工事の定義は、着工から完成までの期間が1年超、請負金額10億円超、または請負対価の1/2以上が引き渡し後1年以内に支払われる工事などです。該当する場合は工事進行基準の適用が原則になります。該当しない場合は、会計・税務における「成果の確実性」の要件を判断し、自社の実態や業務負荷を考慮して、工事完成基準か工事進行基準かを決定します。
「成果の確実性」とは
建設業許可における「成果の確実性」とは、工事収益総額、工事原価総額、そして工事の進捗度について、それぞれ信頼性をもって見積もることができる状態を指します。この確実性が認められる場合に、工事が完成する前の段階から収益を計上できる「工事進行基準」が適用可能です。
「成果の確実性」は、以下の3つの要素の確実性を評価するものです。
- 工事収益総額の確実性
最終的に、工事が完成することの確実性が必要です。 - 工事原価総額の確実性
工事契約の各段階での原価が、詳細に積み上げられ、実際の原価発生と対比して適切に見直せる状態が求められます。 - 決算日における工事進捗度の確実性
工事原価総額の信頼性があれば、進捗度の見積もりも信頼性をもって行えるとされます。
「成果の確実性」が重要が理由としては、建設業では、工事が長期にわたる場合があり、工事完了まで収益を計上できない「工事完成基準」では、期間の業績評価に不都合が生じることがあります。そのため、進捗に応じて収益を計上できる「工事進行基準」が原則とされており、その適用には、上記の「成果の確実性」が認められることが条件となるためです。
工事収益総額の確実性とは
建設業許可における「工事収益総額」とは、建設事業者が工事契約に基づいて受け取る対価の総額を指します。これは、会計上の概念であり、工事完成基準や工事進行基準を用いて収益を認識する際の基礎となる重要な要素です。具体的には、顧客との契約で定められた、工事を施工することで得られる収益の合計金額のことです。
建設業許可における「工事収益総額の確実性」とは、請け負った工事が確実に完成すること、そしてその工事で得られる収益総額が信頼性をもって見積もれることを指します。これは、工事の完成に必要な十分な能力が施工者にあること、および工事の完成を妨げる環境要因が存在しないことが前提となり、信頼性のある工事の収益(対価)を算定できる状態を意味します。
工事収益総額の確実性の具体的な内容としては、工事施工者にその工事を確実に完成させるための十分な能力があること、また、天災などの環境的な要因で工事が中断・中止される可能性が低いことが求められます。 工事契約における最終的な対価の金額や決済条件が確定しており、信頼性をもって収益が見込める見積もりができることが必要です。
この「成果の確実性」という要件を満たすことで、工事の進捗に応じて収益を認識する工事進行基準を適用できるかどうかが判断されます。要件を満たさない場合は、工事が完成した時点を収益認識のタイミングとする工事完成基準を適用する必要があります。
工事原価総額の確実性とは
建設業許可における「工事原価総額」とは、ある会計年度内に完成した工事に要した費用全体を指し、材料費、労務費、外注費、経費の4つの要素から構成されます。この金額は、工事の収益性と経営状況を評価する上で重要な指標であり、建設業許可の申請や更新時に提出する「完成工事原価報告書」に記載されるものです。
工事原価総額は、主に以下の4つの費用項目に分類されます。
- 材料費
工事に直接使用する資材(木材、鉄筋など)や部品の費用。 - 労務費
工事に携わる現場作業員の賃金、手当、福利厚生費などの人件費。 - 外注費
工事の一部を専門業者に委託した場合の費用。 - 経費
上記の費目以外で、工事の遂行に必要な費用(工具・機械のリース料、現場事務所の家賃、水道光熱費、現場管理者の人件費など)。
建設業許可における「工事原価総額の確実性」とは、工事契約に着手した後、工事の進捗に合わせて、各段階で発生する工事原価を詳細に積み上げ、その総額を信頼性をもって見積もり、さらに実際の原価発生と対比して適切に見直し・修正ができる状態にあることを指します。これは、決算時における工事原価の信頼性のある測定を可能にし、建設業許可申請の「成果の確実性」を判断する重要な要素の一つです。
工事原価総額の信頼性を確保するためのポイント
- 詳細な積上げ
工事原価見積総額は、工事の各段階における原価の積み上げとして構成されている必要があります。 - 進捗との対比と見直し
見積もりと実際の原価発生を比較し、定期的に見積もりを見直し、修正を行うことで、より確実な見積もりへと近づけることができます。 - 工事に関わるコストの正確な把握
材料費、労務費、外注費、経費など、工事に直接かかるすべての費用を正確に算出し、把握することが重要です。
建設業会計において、これらの条件を満たすことで、工事原価総額の確実性が認められ、「成果の確実性」が担保されることになります。
決算日における工事進捗度の確実性とは
建設業許可における「工事進捗度(工事進行基準)」とは、工事にかかった原価を基に、工事が全体に対してどれくらい進んでいるかを表す割合のことです。工事進行基準が適用される際に見積もられ、進捗度に応じて売上や経費を計上するために用いられます。
工事進捗度は一般的には、「原価比例法」という方法で算定されます。「原価比例法(げんかひれいほう)」とは、工事の進捗度を測定する方法の一つで、決算日までに発生した工事原価が、工事原価の総額に占める割合を計算し、その割合を工事の進捗度とするものです。この進捗度を用いて、工事進行基準に基づき、売上や経費を計上します。
- 決算日までに発生した原価を把握します。
- 工事にかかった原価の総額を把握します。
- 「決算日までに発生した原価 ÷ 原価総額」で算出し、その割合を工事進捗度とします。
原価比例法の重要性
- 工事の進捗度に応じて、工事収益や費用を計上するための「工事進行基準」を採用する際に、その進捗度を測定するために用いられる。
- 目的物の完成を待たずに、工事の進捗に応じて収益を計上することで、赤字決算を防ぎ、適切な期間損益を認識することができる。
- 工事の途中で原価総額などに変更があった場合、進捗度や収益額も修正する必要があり、定期的に見積りを更新して反映させることが重要。
建設業許可における「決算日における工事進捗度の確実性」とは、工事の進捗状況に応じて適切な収益を認識するために、工事の進捗度を信頼性をもって見積もれることを指します。これは、工事収益総額と工事原価総額の見積もりが信頼でき、さらに工事を完了させる能力や環境が整っていることが前提となります。
新収益認識基準とは
建設業許可における「新収益認識基準」とは、国際的な会計基準(IFRS15)に準拠して、収益をいつ、どのように認識・計上するかを統一的に定めた新しい会計基準です。具体的には、2021年4月1日以降に始まる事業年度から一部の大企業に適用が義務化され、従来の工事進行基準などに代わって導入されました。この基準では、契約内容を履行義務に分解し、履行義務が充足された時点で収益を計上します。
新収益認識基準の主なポイント
- 統一基準の導入
これまで企業ごとに異なっていた売上認識の基準を、国際的な基準(IFRS)と整合性の取れる形に統一された。 - 履行義務の充足
契約内容を分解し、顧客に対して「履行義務(約束した財またはサービスの提供)」が果たされたタイミングで収益を計上する、という原則が導入された。 - 工事契約基準の廃止
従来の建設業における工事契約の収益認識に関する工事進行基準や工事完成基準が、この新収益認識基準に統合され、廃止となった。 - 工事進行基準からの変更点
従来の工事進行基準における会計処理は、新収益認識基準の「一定期間で充足するもの」という考え方に引き継がれてた。また、進捗度の見積もりが困難な場合は、従来の工事完成基準ではなく、新たな会計処理として「原価回収基準」が適用される場合がある。 - 適用対象
新収益認識基準は、大会社、上場企業、上場準備会社に対しては強制適用になる。中小企業など適用対象外の企業は任意適用となる。
新収益認識基準が与える建設業への影響
新収益認識基準は、これまで主流だった工事進行基準を廃止し、顧客との契約で「履行義務」を充足した時点で収益を認識するという5ステップアプローチに基づいた会計処理に移行するため、建設業の収益計上タイミングや財務諸表の透明性が変化します。これにより、国際会計基準との整合性が高まり、資金調達や与信管理の向上、海外展開の促進といったメリットが期待される一方、契約内容の見直しや会計システム、社内体制の構築、経理担当者の教育など、企業側での対応が必要となります。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
建設業法に基づく財務諸表(決算変更届)とは? 勘定科目についてまとめました。
建設業法に基づく財務諸表とは?
建設業法に基づく財務諸表とは、建設業法施行規則で定められた様式で作成される、建設業許可の申請時や決算変更届に添付する財務書類のことです。税務署に提出する決算書とは異なり、建設業に特有の勘定科目(完成工事高、未成工事支出金など)を使用し、建設業の経営状況を明確にするためのものです。
建設業に特有の勘定科目が財務諸表に使われている目的は「未成工事支出金」のような工事の進捗を表す勘定科目や、工事の完成と売上計上のタイミングが大きく異なる業界特性への対応が必要だからです。建設業法では、工事の適正な原価管理と経営状況の把握が求められており、そのための専用の勘定科目・会計基準が設けられています。
建設業会計が特殊な理由
- 工事期間の長期化
建設業は製造業などと比べて工事の開始から完成までが長期間にわたるため、受注から売上計上までの期間も長くなる対応する必要がある。 - 適切な期間損益計算の必要性
工事が長期間にわたることで、決算期末に利益が把握しにくくなるため、工事の進捗度に応じて売上と費用を分割して計上する期間損益計算が認められているため。 - 建設業法に基づく義務
建設業法では、許可申請や更新の際に「未成工事支出金」など、工事原価を「見える化」した財務諸表の提出が義務付けられているため。
決算変更届で使われる勘定科目
決算変更届は税務署に提出する決算書とは異なり、建設業許可の「決算変更届(事業年度終了届)」に添付する財務諸表は、建設業法施行規則に基づく「建設業会計」の様式に準拠する必要があります。そのため、税務署に提出した決算書の勘定科目が建設業法施行規則に準拠していない場合、組替え作業が必要になります。
組替える上での注意点はとしては、兼業を行っている場合は建設業特有の勘定科目と他の事業の勘定科目を適切に振り分ける必要があること。建設業特有の処理や勘定科目を正確に理解することが、決算変更届の作成をスムーズに進める上で重要になります。
建設業会計での特有の勘定科目について
建設業会計では、一般的な勘定科目に代わり「完成工事高(売上高)」「完成工事原価(売上原価)」「未成工事支出金(仕掛品)」「完成工事未収金(売掛金)」「未成工事受入金(前受金)」「工事未払金(未払金)」などが特有の勘定科目として使用されます。これらの科目は、工事の進捗状況や原価を適切に管理するために必要です。
具体的な建設業会計の勘定科目
- 完成工事高・・・(売上高に相当)
完成した建設工事の売上・収益を指す勘定科目で、一般の会計における「売上高」に相当します。建設業会計の独特な勘定科目の一つで、工事が完成して発注者に引き渡された時点で計上されます。 - 完成工事原価・・・(売上原価に相当)
会計年度内に完成した工事に要した直接的な費用の総額を指し、一般の会計における「売上原価」に相当します。材料費・労務費・外注費・経費の4つの要素で構成され、工事の完了時に損益計算書に計上されます。これにより、完成工事の利益が明確に把握できます。 - 完成工事総利益・・・(売上総利益に相当)
完成した工事の売上高(完成工事高)から、その工事にかかった直接的な費用(完成工事原価)を差し引いた金額を指します。これは、一般会計における売上総利益(粗利益)に相当します。 - 未成工事支出金・・・(仕掛品に相当)
まだ完成していない工事にかかった費用を計上するための勘定科目で、一般会計の「仕掛品」に相当します。建設工事は長期間に及ぶため、決算をまたぐ場合に、工事が完成するまでの材料費や労務費、外注費などを一旦この勘定科目に計上し、工事の進捗や収益認識の適正化を図ります。 - 完成工事未収金・・・(売掛金に相当)
工事が完成して引渡しが完了した後も、まだ請負代金の回収が済んでいない状態を指す資産勘定科目です。一般の企業で使われる「売掛金」に相当し、工事代金が後日支払われる場合に、まだ入金されていないお金を管理するために計上されます。 - 未成工事受入金・・・(前受金に相当)
まだ完成・引渡しをしていない工事の代金のうち、先に受け取った金額を指します。建設業で特有の勘定科目で、一般の会計では「前受金」に相当します。未成工事受入金は貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)では負債として計上され、工事が完了して引き渡されたときに完成工事高に対応する形で振り替えられます。 - 工事未払金・・・(未払金に相当)
建設工事の遂行のために発生した費用(労務費、材料費、外注費など)のうち、まだ支払いが完了していない金額を計上する負債の勘定科目です。建設業独自の勘定科目であり、一般会計における「買掛金」や「未払金」に相当します。
建設業は工事に長期間を要し、その間に費用が発生する一方で代金は後から受け取ることが多いため、一般的な会計とは異なる処理が必要になります。建設業会計では、工事の進捗状況を反映させる「進行基準」や「完成基準」が用いられ、それに伴い上記の勘定科目が使われています。
建設業会計の勘定科目を理解するには
建設業会計の勘定科目を理解するには、建設業特有の会計基準と勘定科目を一般企業の勘定科目と関連付けて理解するのが有効です。建設業経理士の資格を取得することで建設業会計の専門知識を体系的に学ぶ、建設業会計独自の用語や概念を学ぶ、専門知識を習得するために建設業会計に特化した研修を受けることや専門家によるサポートを受ける、建設業会計に対応した会計システムを導入することで、会計処理を効率化することも建設業会計の勘定科目を理解することに有効です。
建設業会計の相談場所は
建設業会計についての相談は相談内容によって異なります。税務や決算書の作成について専門的なアドバイスがほしい場合は、建設業に強い税理士に相談するのが最も確実です。 財務改善や経営戦略について、より専門的な視点からアドバイスがほしい場合は、経営コンサルタントに相談する方法もあります。経営全般やコンプライアンスに関する相談は、公的な窓口も活用できます。
行政書士小川真裕事務所では決算変更届の作成・提出業務を行っております。税務署に提出した決算書の勘定科目が建設業法施行規則に準拠していない場合は作成時に組替え作業をおこなっております。建設業許可における決算変更届に関してお困りの方は行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問い合わせください。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
建設業許可における経営事項審査とは? 決算変更届との関係性についてまとめました。
建設業許可を取得した建設業者は事業年度の終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
決算変更届とは建設業許可業者(個人・法人問わず)が、その年度の工事実績や財務状況などをまとめた報告書を、許可を持つ監督官庁に提出することが建設業法で義務付けられている手続きのことをいいます。決算変更届についてまとめたコラムがこちらになります。「建設業許可取得後に届出義務が生じる決算変更届とは? 決算変更届についてまとめました。」
経営事項審査とは?
建設業許可における経営事項審査(経審)とは、国や地方公共団体が発注する公共工事の入札に参加する建設業者が必ず受ける必要のある審査のことをいいます。企業規模、経営状況、技術力、社会性などを客観的に審査するために指標を数値化して評価し、その結果をもとに建設業者の順位付け・格付けが行われます。
経営事項審査の目的と内容
建設業許可における経営事項審査の目的は、公共工事を発注者から直接請け負う建設業者が、国や地方自治体によって客観的・統一的な基準で評価され、適切な入札に参加できるようにするためです。この審査により、建設業者の経営規模、経営状況、技術力などを数値化し、その結果が公共工事の信頼性の確保と建設業界全体の健全な発展に貢献します。
経営事項審査の内容をまとめると以下になります。
- 公共工事入札における建設業者の成績表
公共工事の入札参加資格の取得には、経営事項審査で算出される「総合評定値(P点)」が必須となります。 - 建設業者の客観的な評価
経営事項審査を通じて、建設業者の企業規模(完成工事高、自己資本など)や経営状況、技術力、社会性(営業年数、労働福祉など)といった客観的な要素を数値化して評価します。 - 全国統一基準
経営事項審査は全国で統一された基準に基づき審査が行われるため、地域や業種に関わらず同じ評点算出式が適用されます。
経営事項審査の審査項目とは?
経営事項審査で審査される項目は、建設業者の「経営規模(X点)」、「経営状況(Y点)」、「技術力(Z点)」、「その他の審査項目(W点)」の4つの要素が審査項目となります。これらの審査項目が数値化され、その結果を総合的に評価した数値として「総合評定値(P点)」が算出されます。 このP点が公共工事の入札参加資格を判断する際の指標となります。
- 経営規模(X点)・・・建設業者の売上高(完成工事高)や自己資本、利益などを評価します。
- 経営状況(Y点)・・・経営状況分析機関が、建設業者の財務状況や経営成績など8つの指標を基に算出します。
- 技術力(Z点)・・・雇用関係にある有資格者の数や経験年数、過去の施工実績などを評価します。
- 社会性等(W点)・・・建設業の育成・確保への取り組みや防災活動への貢献、法令遵守の状況、建設機械の保有状況などが評価されます。
- 総合評定値(P点)・・・X、Y、Z、Wの各評価要素に係数を掛けて計算式に当てはめ、総合評定値(P点)が算出されます。このP点が高いほど、企業の経営基盤が安定しており、技術力も高いと判断されます。
審査項目は、公共工事の受注を希望する建設業者の能力を客観的に示し、公平で適正な入札の実施と、健全な建設業界の発展を促進することにあります。
経営事項審査と決算変更届の関係性について
決算変更届は、建設業許可業者が毎年提出する財務内容の報告書類であり、経営事項審査(経審)を受けるためには、最新の決算変更届が提出されていることが前提となります。つまり、決算変更届は経営事項審査の「前提条件」であり、最新の経営状況を把握し、経営事項審査の評点を算出するために必要不可欠な書類となります。決算変更届を提出していないと経営事項審査を受けることができません。
経営事項審査を受けるまでの流れ
経営事項審査を受けるには、まず建設業許可の取得が必要です。許可取得後、決算報告書の作成、事業年度終了届の提出を行い、その後、建設業の許可を受けた都道府県に経営規模等評価申請と総合評定値の請求を行うことで、経営事項審査の「経営事項審査結果通知書」が交付され、審査の流れが完了します。
経営事項審査を受けるための流れをまとめると以下になります。
- 建設業許可を取得する (前提)
経営事項審査を受けるためには、まず建設業許可を取得している必要があります。 - 決算報告書を作成する
会社の決算期にあわせ、決算報告書などの財務諸表を作成します。この決算日が経営事項審査の審査基準日となります。 - 事業年度終了届(決算変更届)を提出する
作成した財務諸表をもとに、建設業許可を受けた都道府県に事業年度終了届(決算変更届)を提出します。 - 経営状況分析の申請をする
国土交通大臣に登録を受けた「登録経営状況分析機関」に、経営状況分析申請を行います。分析機関から「経営状況分析結果通知書」が交付されます。 - 経営規模等評価申請と総合評定値請求をする
経営状況分析の結果通知書を受け取ったら、建設業許可を受けた都道府県(許可行政庁)へ「経営規模等評価申請書」および「総合評定値請求書」を提出します。 - 経営事項審査結果通知書の取得する
許可行政庁が経営規模等評価審査を行い、経営状況分析と経営規模等評価の結果をまとめた「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」が交付されます。
以上が経営事項審査を受けるまでの流れになります。経営事項審査を受けると交付される「経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書)」が、公共工事の入札参加資格を得るために、自治体へ入札参加資格申請を行う際に必要となる書類になります。
経営事項審査の申請書類一覧
経営事項審査で提出する主な書類になります。
- 「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」
・法人の場合・・・損益計算書、法人税確定申告書
・個人の場合・・・損益計算書、所得税青色申告決算書又は収支内訳書 - 「工事種類別(元請)完成工事高」
・「工事種類別完成工事高業種積み上げ表」
・「工事経歴書」
・「直前3年の各事業年度度における工事施工金額」 - 「消費税等確定申告書の写し及び消費税納税証明書」
- 「技術職員名簿」
・「技術職員の常勤性確認資料」
・「技術者の資格検定合格証等の写し」
・「技術者の実務経験等内容書」 - 「その他の審査項目(社会性等)」
・「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況確認資料」
・「建設業の営業継続の状況の確認資料」
・「防災活動への貢献の状況の確認資料」
・「建設業の経理の状況の確認資料」
・「研究開発の状況の確認資料」
・「建設機械の保有状況の確認資料」
・「国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況の確認資料」 - 「経営状況分析結果報告書の原本」
前回の申請内容と照合する箇所があるため申請ではこれらの書類の他に前回の申請書類の控えを準備する必要があります。
経営事項審査の代行依頼先は?
建設業許可における経営事項審査は、公共工事の受注を希望する建設業者の経営状況や技術力などを客観的に数値化し、その信頼性を評価するための制度です。審査結果は工事の規模に応じた入札ランクの決定に使われ、発注者が適切な建設業者を選定する基準となるほか、建設業者自身も自社の強み・弱みを把握して経営改善に役立てることができます。
経営事項審査の代行依頼先は一般的には行政書士になります。行政書士に依頼するメリットとしては専門知識による書類作成の確実性と、申請手続きの迅速化、そして経営者の本業への専念があります。さらに、建設業許可取得後の手続きの管理や、入札で有利な経営事項審査の評点の最大化、専門家による継続的なサポートといった長期的な事業の発展に繋がり、事業基盤の安定化の貢献が期待できます。
行政書士小川真裕事務所では決算変更届、経営事項審査の作成・提出まで総合的に取り扱っております。総合評定値の算出方法等、決算変更届、経営事項審査についてお困りの方はお気軽に行政書士小川真裕事務所までお問い合わせください。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
建設業許可取得後に届出義務が生じる決算変更届とは? 決算変更届についてまとめました。
「決算変更届」とは
建設業許可許可を取得した建設業者には申請した区分を問わず申請内容に変更があった場合は所定の期間以内に変更届を提出しないといけません。(建設業法第11条)
「決算変更届」とは、建設業許可業者(個人・法人を問わず)が事業年度終了後4か月以内に、その年度の工事実績や財務状況などをまとめた報告書を、許可を持つ監督官庁に提出することが建設業法で義務付けられている手続きです。名称に「変更届」とありますが、変更の有無にかかわらず、毎年の決算終了後に必ず提出しないといけません。
尚、決算変更届の提出を怠ると許可の更新ができません。また、経営事項審査を受けるためにも、継続して決算変更届を提出している必要があります。
「決算変更届」の目的
建設業許可における決算変更届の主な目的は、建設業許可を持つ事業者が建設業法に則り健全な経営を継続しているかを、行政が毎年の決算報告を通じて確認することです。毎年決算変更届を提出することで、建設業許可の更新や、建設業許可の継続に必要な「財産要件」を満たしていることの証明につながります。
「決算変更届」に必要な主な書類
決算変更届に必要な書類は以下になります。
- 変更届出書(決算変更届)・・・届出を行う際の表紙です。
- 工事経歴書・・・直前事業年度に完成した工事の一覧です。
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額・・・過去3年間の完成工事高を業種別にまとめたものです。
- 財務諸表・・・建設業法に沿った形式で作成された貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書などです。
- 事業報告書・・・株式会社のみ
- 納税証明書・・・法人事業税 または 個人事業税
その他、変更があった場合のみ提出する書類
- 使用人数・・・使用人数に変更があった場合に提出します。
- 令3条使用人の一覧表・・・令3条使用人に変更があった場合に提出します。
- 定款・・・定款の内容に変更があったっ場合に提出します。
- 健康保険等の加入状況・・・健康保険等の加入状況に変更があった場合に提出します。
建設業法に沿った形式で作成された財務諸表とは?
建設業許可の決算変更届では、名称に決算が使用されていますが税理士や会計士が作成した決算書をそのまま提出するのではなく、建設業法に定められた様式に書き換える必要があります。
例えば、売上高は「完成工事高」と「兼業売上高」に、原価は「完成工事原価」と「製造原価」に分けて記載し、金額表示は「千円単位」で「税抜き表示」が原則です。また、直前3年の工事施工金額と財務諸表の数字に不整合がないか注意し、未払い金などの勘定科目も建設業法に沿って統一する必要があります。
尚、決算変更届が通常の会社決算書と異なるのは、建設業法に定められた様式で、建設業の売上・原価・その他の事業のものとを明確に区別して、建設業の「経営状況」を把握・判断するためです。
建設業を営みつつ、その他の事業(例えば、不動産賃貸業など)も行っている場合、通常の決算書ではこれらの売上や費用が合算されています。これらを建設業にのみかかる売上高や原価と、その他の事業にかかるものを明確に分けて記載することで、建設業のみの「経営状況」を把握・判断することができるようになります。
そのため建設業法に沿った財務諸表は建設業会計の基準に基づいた勘定科目の分類や、記載方法で作成する必要があります。
「決算変更届」の代行依頼先は行政書士事務所が一般的です。
決算変更届は建設業許可を取得した建設会社に提出義務が生じるため、建設業許可申請を取り扱っている行政書士事務所が代行の主な依頼先になります。提供するサービス範囲(書類作成のみか提出まで含むか)は行政書士事務所によって異なるため、複数の事務所で見積もりを取ることをお勧めします。
決算変更届の提出期限は事業年度終了後4ヶ月以内であり、期日を過ぎてしまった場合でも、相談可能な事務所はあります。 行政書士小川真裕事務所は決算変更届の作成・提出の代行業務も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。期日を過ぎた場合でも相談を受け付けております。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
建設業許可における適切な社会保険に加入するとは? 加入すべき社会保険をまとめました。
建設業許可における社会保険とは?
建設業許可において申請者は適切な社会保険に加入することが要件として定められています。
建設業許可における「社会保険」とは、原則として健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つを指します。2020年10月の建設業法改正により、これらの保険への加入が建設業許可の新たな要件となったため、未加入の場合、許可を取得できなくなりました。5年毎の許可の更新事にも社会保険の加入状況が確認され、未加入の場合は許可申請ができない、または許可を失うおそれがあります。尚、労働保険の一部である労災保険は、この時点では許可要件とされていません。
社会保険の加入が義務化された背景には、労働者が病気、ケガ、失業などのリスクに直面した際に、適切な補償を受けられない状況が問題となっており、建設業業界全体の労働環境を改善し、働きやすさを向上させるといった背景があります。
社会保険加入義務者と適用除外者について
建設業許可を取得するためには、法人なら常時加入義務のある「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」への加入が必要です。個人事業主の場合は従業員を常時5人以上雇用している場合は義務化されており、5人未満の場合は国民健康保険や国民年金に加入していれば問題ありませんが、従業員を一人でも雇用している場合は雇用保険の加入が必要です。
健康保険等の加入義務等
法人、個人事業主が加入すべき社会保険の一覧表になります。
|
事務所の形態 |
常用労働者 |
就労形態 |
医療保険 |
年金保険 |
雇用保険 |
|
法人 |
1人~ |
常用労働者 |
協会けんぽ 健康保険組合等 ※1 |
厚生年金 |
雇用保険 |
|
ー |
役員等 |
※2 |
|||
|
個人事業主 |
5人~ |
常用労働者 |
協会けんぽ 健康保険組合等 ※1 |
厚生年金 |
雇用保険 |
|
1人から4人 |
事業主 一人親方 |
国民健康保険 |
国民年金 |
||
|
ー |
ー ※2 |
※1 健康保険の適用除外をの承認をうけることにより、国民健康保険(全国土木建築国民健康保険組合等)に加入する場合があります。
※2 法人の代表者の同居家族、個人事業主の同居親族などについて適用が除外されます。
社会保険の確認書類は?
建設業許可申請時に必要な社会保険加入確認書類は、加入している保険の種類によって異なり、主に健康保険・厚生年金保険の領収証書や納入証明書、労働保険の概算・確定保険料申告書の控えと領収済通知書などです。これらの書類の写しを提出する際は、事業所整理記号や労働保険番号などの情報が記載された直近のものが求められます。
健康保険・厚生年金保険の確認書類 (以下のいずれか)
- 保険料の納入に係る領収証書(写) もしくは納入証明書(写) 又は、納入確認書(写)
- 被保険者資格取得確認又は標準報酬決定書(写)
雇用保険(労働保険)の確認書類 (以下のいずれか)
- 労働保険概算・確定申告書(写)、及びこれに申告した保険料の納入に係る領収済通知書(写)
- 労働保険加入・保険料等納付証明書
これらの書類が社会保険の確認書類になります。
おわりに
以上になります。建設業許可においては適切な社会保険への加入が必須要件と定められていますので、許可取得を検討されている建設業者様に本コラムが参考になればと思います。尚、社会保険の確認書類についてご不明点があれば行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問い合わせください。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
建設業許可における「誠実性」とは? 該当する対象者、不正な行為等をまとめました。
「誠実性」とは?
建設業許可申請には「誠実性」が要件とされています。「誠実性」とは建設工事の請負契約において、不正や不誠実な行為をする恐れがないこととされています。
建設業許可で誠実性が求められるのは、建設業が社会の公共性と公益性が高く、不正行為や不誠実な行為を防ぎ、発注者を保護するためです。社会的な信頼の基盤を築く建設業界において、許可を受けた事業者が不正な契約や工事を行うことを未然に防ぎ、建設工事全体の適正な施工と建設業の健全な発展を促進することが目的です。
「誠実性」の対象者
建設業許可における誠実性の対象者は以下になります。
法人申請の場合
- 法人自体:申請する法人そのもの。
- 役員等:取締役、執行役、相談役、顧問など、建設業の営業取引において重要な地位にある者。
- 令第3条使用人:法人の支店または営業所の代表者(支店長や営業所長など)。
個人申請の場合
- 個人事業主本人:申請を行う個人事業主。
- 支配人(令第3条使用人):個人事業主の支配人。
誠実性の判断基準
誠実性の判断基準は、請負契約の締結や履行にあたり、詐欺、脅迫、横領、文書偽造、請負契約違反などの不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことを指します。過去に建設業法や関連法令(建築士法、宅建業法など)で免許取消処分や営業停止処分を受け、その最終処分から5年を経過していない者も、誠実性の要件を満たさないものとされます。
「不正行為」「不誠実な行為」とは?
では、不正行為や不誠実な行為とは具体的にどういった行為を指すのでしょうか。「不正行為」とは建設業法に違反する行為全般を指し、主に許可申請の際に虚偽の記載をすること、工事請負契約における詐欺・脅迫・横領などの法律違反、また工事内容の不良や契約不履行、虚偽の施工体制台帳の作成などが該当します。一方、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担など、請負契約の内容に違反する行為全般を指します。
不正行為に該当する具体的な行為
許可申請等に関する虚偽行為
- 建設業許可申請書、変更届、経営状況分析申請書などに虚偽の記載をして提出すること。
- 許可基準を満たさなくなったにも関わらず、その事実を届け出なかったり、虚偽の届出をすること。
無許可営業
- 建設業許可を取得せずに、500万円以上の規模の工事を請け負うこと。
- 建設業許可を受けた業者と誤認されるような表示をして、無許可で営業すること。
建設工事の請負に関する不正行為
- 工事の手抜きなど安全基準を満たさない施工を行うこと。
- 架空請求や過大請求といった不適正な工事代金の請求を行うこと。
- 下請けへの一方的な費用負担の強制や、極端に安い請負報酬での発注。
名義貸し
- 他人の建設業許可を借りて工事を請け負うこと。
発注者やその他の関係者に対する不正行為
- 発注者への不当な要求や、工事代金の支払いを正当な理由なく遅延させること。
- 談合や贈収賄を伴う入札行為、不正入札をすること。
その他
- 営業停止処分を無視して営業を継続すること。
- 必要な標識(建設業の許可票)を掲示しないこと。
不誠実行為に該当する具体的な行為
工事内容の違反
- 契約通りの品質や仕様で工事が行われないこと。
工期に関する違反
- 契約で定められた工期に遅延が生じ、その責任が明確にされないこと。
天災などによる損害負担の違反
- 契約に反して、天災等不可抗力による損害を一方的に負担させるなどの行為。
その他契約違反
- 請負契約に明記されている事項に違反するすべての行為。
「誠実性」の確認書類は?
建設業許可における「誠実性」を確認する書類は特にありません。特定の「確認書類」を提出するわけではなく、申請者や役員等が「不正または不誠実な行為」をしていないことが許可行政庁により審査され、その判断は過去の行政処分歴や不祥事の有無などで判断されます。また、確認書類として身分証明書や登記されていないことの証明書などがありますが、これらは「欠格要件」に該当しないことを示すものであり、誠実性そのものを直接証明する書類ではありません。
「誠実性」に違反した場合のペナルティー
建設業許可における「誠実性」に違反していることが発覚した場合、許可の取り消しや更新申請の拒否、新規申請の却下といった処分を受けます。違反の程度によっては営業停止処分もあり、許可を取り消された後は5年間は新規申請をすることができません。また、建設業法等の違反により罰金刑に処されたり、虚偽申請が発覚した場合も同様に不利益な処分を受けることがあります。
おわりに
建設業許可における「誠実性」についてまとめてみました。建設工事は、完成までに長期間を要し、代金の支払いや取引の進め方で発注者と受注者の信頼関係が前提となる特殊な性質を持っています。そのため、不正や不誠実な行為をする者には許可を与えず、建設業全体を健全に保つために申請者には誠実性が求められています。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
建設業許可申請における常勤性と専任性の違いは? 常勤性と専任性についてまとめました。
「常勤性」「専任性」とは?
建設業許可にて経営業務管理責任者や営業所技術者に求められる「常勤性」とは、原則として休日以外の日は毎日営業所に通勤し、所定の勤務時間を務めることを指します。
「専任性」は建設業を営む営業所に常勤し、専らその業務に従事することを意味します。具体的には、営業所から著しく遠距離に居住していない、他の営業所や他の建設業者の専任技術者など、法令で専任性が求められる職務と兼任していないことが求められます。
これらの要件が建設業許可において求められる理由は、建設業法が名義貸しを防ぎ、建設工事の適正な実施を確保するためです。常勤性は会社業務に毎日従事し報酬を得ていることを、専任性は他の兼務をしないことを指し、これらを満たすことで、経営業務管理責任者や営業所技術者が実際に会社に貢献し、技術的な責任を果たしていることが証明されます。
「常勤性」「専任性」が認められない例
建設業許可で「常勤性」「専任性」が認められない例としては以下の例が挙げられます。
- 住居と営業所が著しく遠距離で通勤が不可能である場合
- 他の建設業者の常勤の取締役や経営業務管理責任者・営業所技術者となっている場合
- 建築士事務所の管理建築士や宅建業の専任の宅地建物取引士など、他の法令で専任が要求される兼業をしている場合
- 他に個人事業を営んでいる場合
- 国会議員や地方公共団体の議員である場合
尚、要件を満たせば経営業務管理責任者と営業所技術者を同一人物がなることは可能です。
「常勤性」「専任性」の確認書類
「常勤性」「専任性」の確認する代表的な書類は以下の書類が挙げられます。(広島県の場合)
法人の場合
- 社会保険標準報酬決定通知書(写)
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)資格取得届(写)
個人事業主本人 又 は支配人の場合
- 申立書(常時申請者の業務に従事しており、他の営業や他社への勤務をしていない旨を記載する書面)
尚、75歳以上の方が経営業務管理責任者、営業所技術者になる場合の「専任性」「常勤性」確認書類は上記に挙げた書類と変わってきますので注意が必要です。
虚偽申請をした場合のペナルティー
経営業務管理責任者や営業所技術者の常勤性、専任性は建設業許可の要件のひとつです。仮に虚偽の申請をした場合、建設業法第50条違反となり、許可の取消、および6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。法人にも罰金刑が科され、さらに今後5年間は許可の取得が禁止される場合があります。
虚偽申請にあたるケースの例
- 実際には他の営業所にいるのに、その営業所の営業所技術者として虚偽の申告をする。
- 許可申請書や添付書類に、本来満たすべき要件を偽って記載する。
- 実際には常勤して現場の主任技術者・監理技術者となっているにもかかわらず、営業所での専任性があると偽って記載する。
などが挙げられます。
おわりに
以上になります。法人が建設業許可申請をする場合は社会保険の加入が必須となっていますので「常勤性」「専任性」の確認書類は揃えやすくなりました。「常勤性」「専任性」についてご不明点があれば行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問い合わせください。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
特定建設業許可の営業所技術者になるための技術要件をまとめました。
特定建設業許可の営業所技術者の技術要件とは?
特定建設業許可における営業所技術者の技術要件は以下になります。
- 許可を受けようとする業種に応じた国家資格取得者であること
- 1級の技術検定試験の合格者であること
- 監理技術者の資格所持者であること
- 一般建設業の営業所技術者の要件を満たした上で、かつ4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験があること(指定建設業の営業所技術者は、指導監督的実務経験だけではなれない)
- 国土交通大臣の特別認定者であること
上記のうち、いずれかの条件を満たす必要があります。
技術検定試験とは?
「技術検定試験」とは、技術者の技術水準を客観的に評価し、その向上と確保を目的とする国家検定制度のことです。1級試験と2級試験があり、試験に合格すると「技士」の称号が与えられ、1級技士は「監理技術者」、2級技士は「主任技術者」になることができます。監理技術者は特定建設業許可の営業所技術者の要件を満たします。
監理技術者とは?
「監理技術者」とは、建設業法に基づき、4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の下請契約が発生する工事現場に配置され、工事全体の技術上の管理を行う技術者のことをいいます。元請業者(特定建設業者)に配置が義務付けられていて、監理技術者は施工計画の作成や工程・品質・安全管理、下請業者の指導監督など、工事現場における総合的な役割を担います。
指導監督的実務経験とは?
「指導監督的実務経験」とは、元請から請け負った工事代金が4,500万円以上(税込)の工事において、工事現場の主任や監督の立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことをいいます。単に工事に従事したり、下請工事としての経験は該当せず、発注者から直接請け負った工事で、合計2年以上の実務経験が必要となります。
指定建設業とは?
「指定建設業」とは、土木一式、建築一式、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事の7業種のことをいいます。
国土交通大臣の特別認定者とは?
「国土交通大臣の特別認定者(大臣特任者)」とは、建設業許可における営業所技術者と同等の能力があると大臣が認定した人を指します。主に、海外での実務経験や学歴、資格を持つ人を、日本の建設業の経験や資格に置き換えるための手続きを得て認定された者を指します。
特定建設業許可の営業所技術者の確認書類は?
特定建設業許可の営業所技術者の確認書類は以下になります。
所定の国家資格取得者、一級技士の場合
- 合格証、免許証、免状等の写し(広島県では原本提示が必要)
一般建設業許可の営業所技術者要件を満たし、かつ指導監督的実務経験による場合
- 一般建設業許可の営業所技術者の確認資料
- 指導監督的実務経験証明書
- 実務経験の内容欄に記載した工事全ての契約書(写)及び当該契約の施工体制が確認できる資料
上記全ての書類を揃える必要があります。
監理技術者の場合
- 監理技術者資格者証(写)(広島県では原本提示が必要)※必要に応じて卒業証明書や免状等の写しを提示する場合があります。
大臣特別認定者の場合
- 認定書(写)(広島県では原本提示が必要)
おわりに
以上になります。特定建設業許可の営業所技術者の要件としては、他に専任性が求められます。こちらは一般建設業許可の営業所技術者と条件は変わりませんので今回は割愛しています。
特定建設業許可の営業所技術者の要件を満たす技術者は建設業界では貴重な人材です。建設業界に携わる方はキャリアアップのためにも資格取得を目指して日々勉強に勤しんでおられるのではないでしょうか? 特定建設業許可の営業所技術者の要件についてご不明点があれば行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問い合わせください。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
一般建設業許可と特定建設業許可の財産要件の違い。要件と提出書類をまとめてみました。
建設業許可の財産要件とは
建設業許可における財産要件とは、事業の経営安定性や資材・機械の購入、労働者の確保などの資金力があることを示す要件です。建設業許可に財産要件が設けられているのは、建設業が資材購入や労務費、機械の購入に多額の資金が必要であり、事業を安定的に継続するための十分な資金力(財産的基礎)が求められるからです。また、特定建設業許可においては、下請け業者を保護し、請負代金の不払いを防ぐ目的も大きいため、より厳しい要件が課せられています。
財産要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。一般建設業では「自己資本500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力」または「直前5年間の継続した営業実績」のいずれかを満たすことが必要です。一方、特定建設業では「資本金2,000万円以上」などのより厳しい要件が課されます。
一般建設業許可の財産要件
一般建設業許可の財産要件では、①直前の決算書で自己資本が500万円以上であること、または②銀行が発行する500万円以上の残高証明書などにより資金調達能力があることを証明する必要があります。資本金の額に要件はなく、会社設立直後の場合は資本金を500万円以上にするか、資金調達能力を証明する形で要件を満たせます。
財産的基礎を証明する方法について(一般建設業許可)
一般建設業許可の財産的基礎の要件を満たすには、以下のいずれかの方法で500万円以上の財産的基礎があることを証明します。
自己資本が500万円以上あること
- 法人(会社)の場合
直前の決算書にある「純資産合計額」が500万円以上あることを証明します。 - 個人事業主の場合
期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計から事業主貸勘定を控除した額(またはそれに引当金・準備金を加えた額)が500万円以上あることを証明します。 - 新規設立の会社の場合
創業時の貸借対照表や、設立時に資本金を500万円以上に設定したことを証明します。
500万円以上の資金調達能力があること
- 預金残高証明書
申請時点(または申請から1ヶ月以内の日付)の預金残高証明書で、申請者名義の預金残高が500万円以上あることを証明します。 - 融資可能証明書
金融機関が発行する融資可能証明書で、申請者に対して500万円以上の融資が可能であることを証明します。
特定建設業許可について
建設業許可の申請区分には一般建設業許可と特定建設業許可の2種類あります。ふたつの大きな違いは元請業者(発注者から直接工事を請け負う立場)として、下請業者に発注する金額の規模によって決まります。
具体的には、工事1件につき4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の下請契約を締結する可能性がある場合は「特定建設業」許可が、それ未満の場合は「一般建設業」許可が必要となります。そのため特定建設業許可は、下請業者を保護するために、営業所技術者要件、財産的要件など一般建設業許可よりも厳しい許可要件が課せられています。
一般建設業許可と特定建設業許可の財産要件の違い
一般建設業許可の財産要件は、「自己資本が500万円以上」か、「500万円以上の資金調達能力があること」のいずれかを満たすことですが、特定建設業許可では以下の要件を全て満たす必要があります。
①欠損比率・・・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率・・・75%以上であること
③資本金の額・・・2,000万円以上であること
④自己資本(純資産)の額・・・4,000万円以上であること
これらの要件を許可の申請時だけでなく、更新申請にも審査されるため、継続的に財務状況を保つことが必要になります。
各用語の意味と確認方法
①「欠損比率」
建設業許可における「欠損比率」とは、申請直前の決算期において、法人の場合は欠損額が資本金額の20%を超えていないことを指します。計算式は[繰越利益剰余金の負の額(正の額に置換)-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(準備金、積立金))÷資本金](法人の場合)で、この割合が20%以下である必要があります。欠損額が資本金の20%を超える場合、企業の経営が不安定と判断され、特定建設業許可は取得できません。
確認方法は「貸借対照表」、「繰越利益剰余金」、計算式に当てはめて確認します。「繰越利益剰余金」がプラスの場合は欠損比率の要件を満たしており、マイナスの場合はマイナスの場合は、マイナスの金額が資本剰余金、利益準備金、任意積立金の合計額を上回っているか確認します。
・「欠損額」
「欠損額」とは、貸借対照表上のマイナスの繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回った場合に、その超過した額を指します。
・「繰越利益剰余金」
建設業許可における「繰越利益剰余金」とは、会社の過去からの利益を積み重ねて、当期の利益を加えて算出された「過去の利益の累計額」を指します。
・「資本剰余金」
建設業許可における「資本剰余金」とは株主からの出資金から「資本金」や「資本準備金」に充当されなかった部分、あるいは自己株式の処分などにより生じた剰余金を指します。
・「利益準備金」
建設業許可における「利益準備金」とは、会社法によって株主への配当時に積み立てが義務付けられている利益剰余金の一種で、会社の財務基盤を強化し債権者を保護する目的があります。建設業許可申請における財産要件の「利益準備金」という項目は存在せず、建設業許可申請時に必要となる資金要件は「自己資本」の額であり、その中に利益準備金は含まれます
・「任意積立金」
建設業許可における「任意積立金」は、建設業者が自己資本を強化するために、会社の利益の一部を留保して積み立てることです。
②「流動比率」
特定建設業の許可要件である流動比率とは、「流動資産(1年以内に現金化できる資産)を流動負債(1年以内に支払うべき負債)で割った割合」のことで、75%以上であることが必要です。この数値は企業の短期的な安全性を表す指標です。直前決算期の貸借対照表で確認することができます。
③「資本金」
特定建設業許可の財産要件における資本金とは、法人の出資額や払込資本金、個人の場合は期首資本金のことを指します。法人が申請時に資本金不足でも、申請日までに増資すれば要件を満たせる場合がありますが、その取り扱いは都道府県によって異なるため、事前に確認が必要です。法人の場合は直近の決算書「貸借対照表」や、「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」で確認することができます。
④「自己資本(純資産)」
特定建設業の許可申請における自己資本とは、法人の場合は決算書で確認できる「純資産合計」の金額を指します。これは返済義務のない資産のことであり、「資産 − 負債」で計算されます。直前の確定した決算書における貸借対照表の「純資産合計」の金額で確認します。
尚、自己資本と資本金の違いは、自己資本は返済義務のない会社のお金の総称で、資本金は自己資本の一部です。自己資本は、株主からの出資金である「資本金」と、利益の蓄積である「利益剰余金」などで構成される貸借対照表の純資産を指します。一方、資本金は法人設立時に株主から出資された資金であり、その額は増資などがない限り、会社の経済活動で変動することがないという違いがあります。
財産的基礎を証明する方法について(特定建設業許可)
特定建設業許可において財産要件を証明する書類として「直近の決算で作成された貸借対照表」が必要になります。注意点として特定建設業許可では、一般建設業許可で認められる預金残高証明書や融資証明書は財産要件を証明する書類として使用できません。
まとめ
以上になります。特定建設業許可の財産要件が一般建設業許可と比較して厳しく設定されているのは、下請業者の保護のためです。特定建設業許可業者は下請け業者に対して多額の請負金額で工事を発注する元請けの立場にあるため、不景気などで経営が悪化しても下請け業者に工事代金が支払われなくなる事態を防ぐ必要があります。そのため、財産的にも安定していることを証明する要件が一般建設業許可よりも厳しく設定されています。
尚、財産要件を満たさない建設業者は更新許可を受けることができません。そのため特定建設業許可業者は許可維持を維持するために定期的に財務状況を確認する必要となります。特定建設業の財産要件についてご不明点があれば行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問い合わせください。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
どういった要件を満たせば営業所として認められるのか、営業所要件をまとめてみました。
建設業許可申請の要件のひとつに適切な営業所を構えることが求められています。この営業所は事務所スペースがあればどのような建物や部屋でも認められるわけではなく、一定の要件を満たすことで営業所として認められます。
建設業許可における「営業所」とは?
建設業許可における「営業所」とは、本店や支店、または建設工事の請負契約を常時締結する事務所を指します。単なる登記上の本店ではなく、見積もりや入札、契約締結といった実質的な行為が行われている事務所や、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に関する営業に実質的に関与する事務所も含まれます。
「常時請負契約を結ぶ事務所」の判断基準
「常時請負契約を結ぶ事務所」の判断基準は実質的な判断が重要で、事務所の名称が「本店」「支店」などでなくても、建設工事の請負契約の実体的な行為(見積もり、入札、契約締結など)が継続的に行われている場合は、法上の「営業所」となります。
また、その事務所の契約書の名義人も問われません。契約書の名義人がその事務所を代表する者であるか否かは関係なく、実質的に契約締結が行われているかどうかが判断されます。営業所の最低限度の要件としては契約締結に関する権限を委任されており、かつ、事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等の設備を備えていることが必要になります。
「営業所」に該当しない例
営業所に該当しない例としては、登記上では本店であっても実質的な営業活動を行っていない事務所、単なる連絡機能のみで、請負契約の締結に一切関与しない事務所や、単に資材置き場は「営業所」とはみなされません。また、会社の経理作業のみを行い、建設工事の請負契約には一切関与しない事務所も「営業所」には該当せず、他の営業所と共用していて区画が不明確な場所も「営業所」と認められません。
「営業所」として認められるための要件とは?
「営業所」として認められるには以下の要件を満たす必要があります。
①実体的な業務の実施
来客を迎え入れ、請負契約の締結や見積り、入札などの業務を行うこと。
②事務室としての機能
電話、机、各種事務台帳などを備え、契約締結ができるスペースがあること。
③独立性
居住部分や他の法人・個人事業主の事務室とは、間仕切りなどで明確に区分され、独立性が保たれていること。
④使用権原
営業所として使用する物件の所有権または賃貸借契約があること。
⑤責任者の常勤性
経営業務の管理責任者や建設業法施行令第3条使用人が常勤していること。
⑥営業所技術者の常勤性
建設業法で定める専任技術者が、その営業所に常勤していること。
⑦外部表示
看板や標識などで、外部から建設業の営業所であることがわかるように表示されていること。
自宅兼事務所が「営業所」として認められるには?
自宅兼事務所を建設業許可の営業所として認めてもらうには、事務所スペースと居住スペースが明確に区分され、独立性が保たれていることが必要になります。具体的には、住居スペースを通らずに事務所へ入れる動線があることや、事務机や電話などの備品が備わっていること、そして玄関や事務所のドアに会社名が掲示されていることなどが求められます。許可申請時には、これらの状況がわかる間取り図や写真の提出が必要となります。
また、賃貸物件の場合は賃貸契約書に「事務所利用可」など営業所として使用が明記されていたり、貸主からの使用承諾書が必要になることがあります。尚、申請する都道府県によって営業所要件の判断基準が異なりますので事前に許可行政庁の担当窓口で確認する必要があります。
マンションや公営住宅、レンタルオフィスは「営業所」として認められるか?
建設業許可における営業所としてマンションを認めるかは、マンション内で営業所と居住スペースが明確に区別されており、かつ独立性が保たれているかどうかで判断されます。具体的には、自宅のワンルームマンションや、玄関からリビングを通らないと事務所に入れないなどの場合は営業所として認められない可能性が高いです。一方、玄関を開けてすぐの部屋や、居住部分と完全に遮断された部屋であれば認められる場合があります。
公営住宅(市営住宅、県営住宅など)については建設業許可における営業所としては原則として認められません。これは、公営住宅の賃貸借契約で事務所としての使用が認められないことが理由であり、許可を得るための事務所要件を満たすことが困難なためです。
建設業許可における営業所としてレンタルオフィスが認められるかは、レンタルオフィスの設備や賃貸契約の内容、そして管轄の行政庁の判断によります。単に住所を借りるバーチャルオフィスでは認められず、独立した個室や固定電話、長期(年単位)の賃貸契約など、事務所としての実体と独立性が満たされている必要があります。レンタルオフィスで申請する場合はその他手続きが煩雑になるため許可行政庁の担当窓口への確認が必須といえます。
まとめ
以上になります。建設業許可申請では経営業務管理責任者や営業所技術者の要件を満たしていても、賃貸物件で貸主の使用承諾書が得られなかった、集合オフィスで独立性が認められなかったといった理由で営業所要件を満たせず許可が下りない場合もあります。事務所として使用していれば必ず営業所として認められわけではありませんので、申請時には注意深く確認する必要のある要件といえるのではないでしょうか? 営業所要件についてご不明点があれば行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問合せください。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。