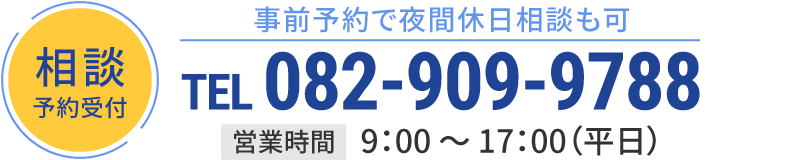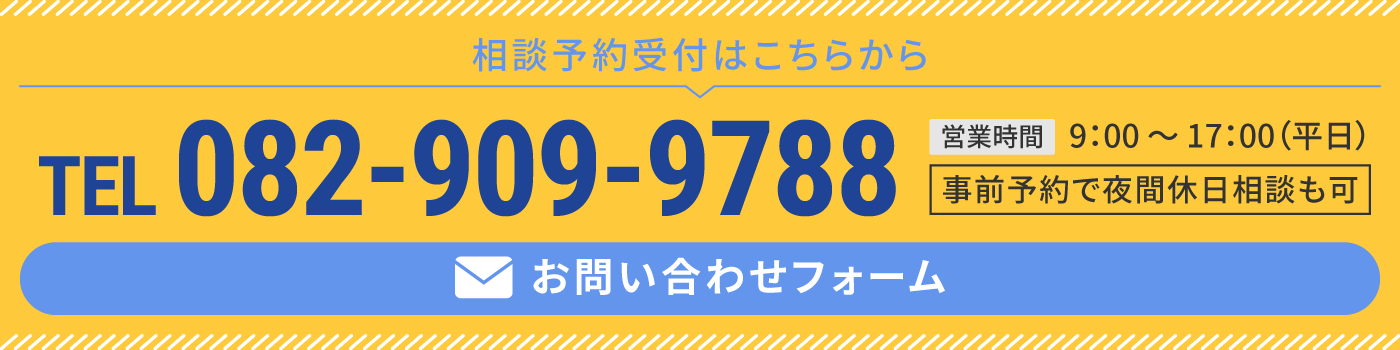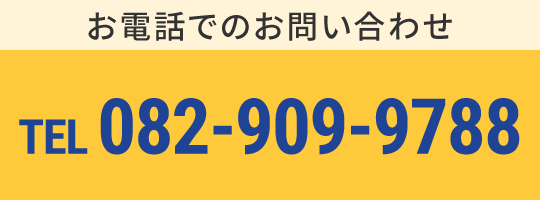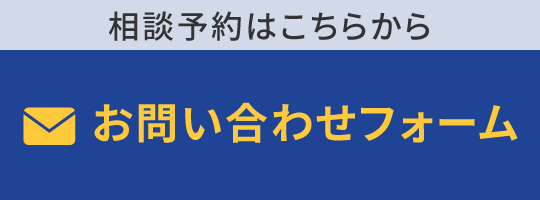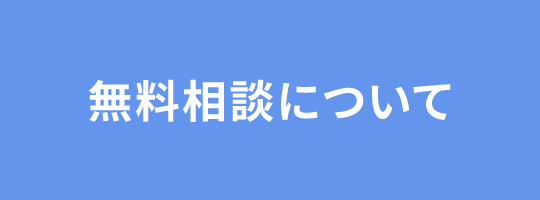コラム【建設業許可】
技術検定試験の受験資格が緩和されたことはご存じでしょうか? 無資格、指定学科を卒業していなくても、1次試験に合格すれば営業所技術者の実務経験年数を短縮できます。
技術検定試験とは?
技術検定試験のことをご存じの方は多いと思いますが、技術検定試験とは技術者の技術力や知識について客観的に評価し、証明する試験制度全般を指します。試験合格者には専門的な称号や資格が付与されたり、実務経験年数の短縮などのメリットがあります。
建設分野だと、7種目それぞれ1級と2級の区分があり、国土交通大臣の指定した試験機関が実施しています。以下が検定種目になります。(国土交通省のHPから参照しています)
| 検定種目 | 指定試験機関(問合せ・申込先) | 電話番号 |
| 土木施工管理 (1級・2級*) | (一財)全国建設研修センター https://www.jctc.jp/ | 042-300-6860 |
| 建築施工管理 (1級・2級*) | (一財)建設業振興基金 https://www.kensetsu-kikin.or.jp/ | 03-5473-1581 |
| 電気工事施工管理 (1級・2級) | (一財)建設業振興基金 https://www.kensetsu-kikin.or.jp/ | 03-5473-1581 |
| 管工事施工管理 (1級・2級) | (一財)全国建設研修センター https://www.jctc.jp/ | 042-300-6855 |
| 造園施工管理 (1級・2級) | (一財)全国建設研修センター https://www.jctc.jp/ | 042-300-6866 |
| 建設機械施工管理 (1級・2級*) | (一社)日本建設機械施工協会 https://jcmanet.or.jp/ | 03-3433-1575 |
| 電気通信工事施工管理 (1級・2級) | (一財)全国建設研修センター https://www.jctc.jp/ | 042-300-0205 |
*2級土木は「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」、2級建築は「建築」「躯体」「仕上げ」の3種別にそれぞれ分かれています。
*2級建設機械は「第1種」~「第6種」の6種別に分かれています。
技術検定試験の合格者に付与される「技士」と「技士補」について
技術検定試験は1級、2級共に1次試験(学科試験)と2次試験(実務試験)があり、1次試験と2次試験に合格すると「技士」の称号が付与され1級技士は監理技術者、2級技士は主任技術者になることができます。それが令和3年4月1日の改正建設業法の施工により1次試験の合格者には、新設された「技士補」の称号が付与されるようになりました。
技士補は営業所技術者になることはできませんが、実務経験を積むことで営業所技術者になることができます。(1級技士補は3年、2級技士補は5年)この制度を利用することで資格の取得が難しい業種の営業所技術者や、実務経験による営業所技術者の占める割合の高い業種(機械器具設置工事業等)、すでに実務経験を積んでいる労働者の方は資格の取得ではなく技術検定試験の1次試験の合格を目指すという選択肢も有効ではないでしょうか?
尚、指定建設業である土木工事業、建築工事業、舗装工事業、鋼構造物工事業、管工事業、電気工事業、造園工事業の7業種と電気通信工事業はこの制度から除かれており、この制度を利用して営業所技術者等になることはできないので注意が必要です。
緩和された受験資格について
この技術検定試験の受験資格が令和6年度より大幅に緩和されました。旧受験資格では1級試験の1次試験は学歴と実務経験、2次試験は学歴と実務経験、2級試験合格者は実務経験かつ1級1次試験合格者、2級試験の1次試験が17歳以上、2次試験は学歴と実務経験、が必要だった受験資格が以下のように緩和されています。
新受験資格
1級試験
1次試験: 19歳以上(受検年度末時点)
2次試験: 1級1次試験合格+実務経験 もしくは
2級2次試験合格+実務経験
2級試験
1次試験: 17歳以上(受検年度末時点)
2次試験: 2級1次試験合格+実務経験3年以上(建設機械種目については2年以上) もしくは
1級1次試験合格+実務経験1年以上
おわりに
この変更によって受験資格を有する者が大幅に増えたと思われます。営業所技術者になれる選択肢が増えたことは建設業界で働く労働者の方にとっても、人材確保と育成に努める建設会社様にとっても手助けになるのではないでしょうか?

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
設備の撤去工事をするときに、「解体工事」の許可をあらかじめ取得しておく必要はあるか?
設備の撤去工事とは
設備の撤去工事とは、建物の一部に残る不要な設備や構造物を取り除き、新しい工事や土地に備えるための作業をいいます。建物全体の解体工事とは異なり、内装材や配管、照明、キッチン設備、庭のフェンスなど、一部の特定された対象物を対象とします。撤去工事には専門的な知識と技術が必要になります。撤去工事の例としては、
- 足場の撤去工事
- 床材、壁材、天井材などの撤去工事
- エアコン、照明器具、キッチン、給排水設備、ガス管などの撤去工事
- 間仕切りの撤去工事
- フェンス、庭石、街灯などの撤去工事
などが挙げられます。一方、解体工事とは、既存の建物や構造物を取り壊し、廃棄物を適切に処理して土地を整地する作業を指します。工事目的からして撤去工事とは異なります。
解体工事とは
解体工事は平成28年6月1日に施工された建設業法等の一部を改正する法律により、元々、とび・土工・コンクリート工事に該当していたものが、分離独立した新しい業種として創設されました。改正法施行前まではとび・土工・コンクリート工事に分類されていた解体工事は、解体工事業許可を取得していなければ500万円以上の解体工事を請け負うことができなくなりました。
解体工事は工作物の解体を行う工事であり、工作物とは土地に定着する人工物全般を指し、建築基準法では「建築物」と「工作物」を区別していますが、解体工事では広く建物も含まれます。解体工事の例としては、
- 建物解体工事
- 外構解体工事
- 土木構造物解体工事
- 内装解体工
が挙げられます。ただし、総合的な企画、指導、調整が必要になるような高層ビルや、橋やダム等の解体工事などは解体工事ではなく、建築一式工事や土木一式工事が該当します。
撤去工事と解体工事の業種判断に関しては、解体工事は「工作物の解体を行う工事」ですので、工作物以外の解体撤去工事については解体工事に該当しないことになります。具体的には、
- 足場の撤去工事・・・とび・土工・コンクリート工事
- マンションの一室のみの内装の撤去工事・・・内装仕上工事
- 信号機のみの撤去工事・・・電気工事
などがあります。
まとめ
各専門工事が設置した設備についての解体・撤去については、それのみを解体・撤去する工事に関しては各専門工事と同じ業種の建設業許可を取得していれば行うことができ、事前に「解体工事」の許可を取得しておく必要はないことになります。広島県が作成した建設業許可申請の手引きにも同様の記載がありますが、具体例が書かれておらずわかりにくいと思いましたので、参考までにコラムで書かせていただきました。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
経営業務管理責任者になるための実務経験5年を短縮する方法はあるのか?
建設業許可申請の検討をされている事業主様の頭を悩ますのが経営業務管理責任者と営業所技術者の専任ではないでしょうか?
経営業務管理責任者の役員経験について
経営業務管理責任者の要件のひとつに建設業の役員経験5年があります。以前は申請する業種と同じ業種の建設業の役員経験だけが実務経験として認められていましたが、現在は建設業の役員経験であれば申請する業種と異なる役員経験でも実務経験として認められるように制度が変更されています。
この変更によって建設業の役員経験が5年さえあれば経営業務管理責任者になれますので、建設業許可の取得を検討するときに外部から人材を招きやすくなったり、複数の会社での役員経験を合わせることで5年という期間を満たすといった選択肢も加わったのではないでしょうか。
役員経験5年を短縮する条件とは?
建設業であれば他業種の役員経験が認められるようになったとしても5年という期間は必要になります。この建設業の役員経験5年を短縮する方法があります。それは
・建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理または業務運営を担当する者に限る)として経験を有する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者を置くこと
になります。この条件では建設業に関する役員経験は2年に短縮することができますが、別に5年以上の役員経験か役員等に次ぐ職制上の地位での経験が必要になります。建設業以外の役員経験でも認められる点に柔軟性がありますが、役員の経験期間としては合計7年になります。建設業の役員経験5年を短縮することはできますが、役員の経験期間の長さの合計は7年と長くなってしまいます。
もうひとつの条件である当該常勤役員等を直接に補佐する者を置くこととは、役員とは別に財務管理、労務管理、業務管理に関して経験を有する者で役員を直接補助しなければならないという規定であり、組織的な体制が求められることを意味しています。尚、実際の申請では当該役員だけでなく、直接補佐する者たちの実務経験を確認する書類も必要になります。
まとめ
以上のことから、経営業務管理責任者の実務経験5年を短縮することはかなり条件が複雑といえるのではないでしょうか。
現状では建設業の役員経験5年で経営業務管理責任者の要件を満たして建設業許可を取得される方が大半だと思われます。それでも条件が緩和されたとしては確認書類として「許可通知書」が加わったことでしょうか、許可取得済みの会社での役員経験であれば確定申告書や請負契約書ではなく許可通知書だけで確認書類の要件を満たすことができるようになりました。役員経験の証明についてご不明点があれば行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問い合わせください。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
「欠格要件」について、わかりやすく要点をまとめてみました。
建設業許可申請における欠格要件
本記事では「欠格要件」の要点だけを記載したいと思います。
以下に該当する場合は建設業許可を取得することができず、取得済みの場合は許可の取消し対象になります。
① 許可申請書およびその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている場合
② 破産者で復権を得ない場合
③ 不正の手段により許可を受けた場合、または営業停止処分に違反したこと等により建設業の許可を取り消されてから後5年を経過しない場合(許可取り消しを免れるため、廃業届を提出した者を含む)
④ 建設業の営業停止、または禁止期間が経過しない場合(適切な工事をしなかった、請負工事に関し不誠実な行為をしたこと等による処分)
⑤ 禁固以上の刑または次の法令違反で、罰金以上の刑に処せられて5年を経過しない場合(建設業法、刑法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律等)
⑥ 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない場合
⑦ 心身の故障により建設業を適切に営むことができない場合(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者)
⑧ 未成年者であってその法定代理人が上記いずれかに該当する場合
⑨ 役員等、支配人、従たる営業所の代表者のうちに上記事項に該当する者がいる場合
⑩ 暴力団員等がその事業活動を支配する場合
欠格要件の対象者
「欠格要件」について補足すると、欠格要件の対象者は以下になります。
個人事業主の場合
- 個人事業主本人
- 営業所の所長
- 支配人
法人の場合
- 当該法人
- 取締役(非常勤含む)
- 執行役
- 業務を執行する社員(個別に判断)
- 組合の理事長(法人格あり)
- 令3条使用人(支店長、営業所長)
- 顧問
- 相談役
- 株主
欠格要件のよくある疑問
参考として欠格要件でよくある疑問が以下になります。
Q 執行猶予は欠格要件に該当しますか?
A 執行猶予期間中は欠格要件に該当しますが、執行猶予期間満了後は該当しません。また、期間満了後は5年経過しなくても許可申請は可能です。禁固以上の刑になった場合が、刑期を終えて5年間になります。
Q 交通違反は欠格要件に該当しますか?
A 駐車禁止や速度の出し過ぎといった軽い交通違反で反則金を支払った場合は建設業法関連の罰金刑ではないので該当しません。ただし、期日を過ぎても支払いをせずに放置したなど悪質性がみとめられる場合は罰金刑に該当する可能性が高まります。
Q 破産はしていないが、ブラックリストは該当しません?
A ブラックリストは欠格要件と定めていないので該当しません。
Q 営業所技術者が欠格要件に該当した場合はどうなるのでしょうか?
A 営業所技術者は欠格要件の対象者ではないので、例えば許可が取消された会社で営業所技術者をしていても欠格要件には該当せず、許可を取得することができます。
おわりに
建設業許可を取得しても欠格要件に該当することが判明した場合は、許可取消しになり、取消し処分後5年を経過しなければ許可を再取得することができません。そのため申請時に欠格要件に該当するおそれが少しでもある場合は、私は担当窓口で確認してから業務に着手するようにしています。欠格要件についてご不明点があれば行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問い合わせください。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
「欠格要件」をご存じでしょうか? 該当した場合は建設業許可を取れない、取消しになります。
「欠格要件」に該当するとは?
建設業許可を取得するときに「欠格要件(けっかく ようけん)」があることをご存じでしょうか? 欠格要件に該当すると建設業許可を取得することができず、許可取得後に欠格要件に該当した場合は許可の取消しになります。
「欠格要件」とは、事業の許認可を受けることができない、またはすでに受けた許認可を取り消されることになる条件のことです。これは、法に従った適正な事業遂行が期待できない申請者を排除することを目的としており、一般的には、心身の故障、破産、または法令違反による刑罰の適用などが含まれます。
建設業許可(国土交通大臣許可、都道府県知事許可)を受けようとする場合に、以下の(1)から(14)のいずれかに該当するとき、又は申請書類もしくは添付資料中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 第29条第1項第7号または第8号に該当することにより一般建設業の許可または特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(3) 第29条第1項第7号または第8号に該当するとして一般建設業の許可または特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日または処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
(4) 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員もしくは政令で定める使用人であった者または当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(5) 第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6)許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
(7) 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(8) この法律、建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項および第32条の11第1項の規定を除く)に違反したことにより、または刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(10) 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
(11) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号また次号(法人でその役員等のうちに(1)から(4)までまたは(6)から(10)までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
(12) 法人でその役員等または政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)まで、または(6)から(10)までいずれかに該当する者((2)に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から(3)または(4)に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から(6)に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等または政令で定める使用人であった者を除く)のあるもの
(13) 個人で政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)までまたは(6)から(10)までいずれかに該当する者((2)に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、(3)または(4)に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、(6)に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く)のあるもの
(14) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
これから建設業許可の取得を検討されている事業主様は欠格要件について調べられていると思います。ご紹介した条文の内容ではわかりづらいとおもいますので、内容を要約してまとめたものがこちらになります・・・「「欠格要件」をわかりやすく要点をまとめてみました」

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
『電気工事』で建設業許可を取得すれば、電気工事だけでなく、機械の設置など関連する工事のすべてを行えるのか?
業種確認の重要性について
建設業許可取得を検討するとき、経営業務管理責任者や営業所技術者の専任要件を満たしているかを確認することはとても重要ですが、私は最初に申請しようとする業種を確定することから始めています。
例えば太陽光パネルの設置工事が主な業務の建設会社が建設業許可申請をしようとした場合、屋根一体型の太陽光パネルであれば『屋根工事』に該当し、太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当します。どちらも電気配線工事を伴う作業ですので「電気工事士」の資格の保持者が現場作業を行います。そのため『電気工事』に該当するイメージがありますが実際は異なります。申請する業種が異なれば営業所技術者の要件は変わってきます、あとで間違ってましたでは取返しがつきませんので、少しでも曖昧な場合は私は必ず担当窓口で確認するようにしています。
特に実務で曖昧になりやすい業種のひとつが『機械器具設置工事』です。機械器具を設置する場合、単独で器具を設置することは少なく電気配線工事や配管工事を伴う場合が多くなります。広島県が作成した「建設業許可申請の手引き」では『機械器具設置工事』を以下のように記述しています。
1 『機械器具設置工事』には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれているため、機械器具の種類によっては『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』等と重複するものであるが、これらについては原則として『電気工事』それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
と記述があります。まずは専門工事に該当するかどうか検証しなさいということですが、建設業許可を申請する事業主様の大半は専門分野をすでにお持ちですので、専門分野について申請する業種が曖昧になる事業主様は少ないのではないでしょうか。
注意していただきたいのは、専門としている工事に関連した工事や、附帯工事を行うときです。建設業許可を取得しても施工できる工事は取得した業種の範囲内であり、軽微な建設工事に該当しない工事を施工することはできません。この場合は取得している建設業許可とは別に、該当する業種の建設業許可を取得するか、許可を取得している建設業者に外注することになります。※軽微な工事に該当しない工事が含まれていても請け負うことはできます。
まとめ:建設業許可を取得しても関連する工事の全てを自社施工できるとは限らない。
これから建設業許可取得を検討されている事業主様で、申請する業種以外の業種に当てはまる可能性がある工事をしている場合は申請時に注意が必要です。どちらの業種でも500万円以上の工事を請け負う予定がある場合はそれぞれの業種で営業所技術者を専任する必要があります。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
県外の仕事を請け負うには、「国土交通大臣許可(大臣許可)」でないとダメなのか?
建設業許可の申請区分には「都道府県知事許可(知事許可)」と「国土交通大臣許可(大臣許可)」の2つの区分があります。2つの違いは営業所が複数ある場合に都道府県内に全ての営業所の所在地があるか、2つ以上の都道府県に所在地が分かれているかになります。2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可、営業所が1つの都道府県にある場合には知事許可になります。知事許可の申請は営業所の所在地がある都道府県に行います。
知事許可業者は、県外で建設工事を行うことができるのか?
結論から述べると、知事許可業者でも県外で建設工事を行うことができます。広島県知事許可の建設業者でも、他県の建設工事を行うことができます。
もし、建設業許可を取得すると県外の建設工事を請け負うことができない、もしくは県外の建設工事を請け負うには大臣許可の取得が必要と思われている事業者様がおられましたらご安心ください。知事許可を取得しても県外の工事を請け負うことができます。大臣許可はあくまでも営業所の所在地が他の都道府県にある場合に必要な許可になります。
知事許可と大臣許可の取得要件に違いはあるのか?
知事許可と大臣許可の要件に大きな違いはありません。経営業務管理責任者は営業所が2つ以上存在したとしても一人になります。ただし営業所技術者ついては各営業所に専任する必要があるため、営業所の数だけ営業所技術者を申請することになります。建設業法でいう「営業所」とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいい、単に労働者の詰所や請負契約を締結しない事務所は営業所とはいいません。
結論:知事許可でも他県の建設工事を請け負うことはできます。
以上になります。実務面でも誤解されている方がおられましたのでコラムで書かせてもらいました。誤解で許可取得が遅れるのは経営的にも勿体無い話です。知事許可でも他県の工事を請け負うことはできますので安心して許可取得の検討をなさってください。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
「設計業務」や「アルバイトでの実務経験」は営業所技術者の実務経験として認められるか?
建設業許可を取得するためには営業所技術者を専任する必要があります。営業所技術者についてはこちらの記事に詳しく記述していますので参照していただければと思います。「営業所技術者の要件と実務経験の証明方法」
営業所技術者は営業所に常駐し、適正な請負契約が締結されるよう技術的観点から契約内容の確認を行ったり、請負契約の適正な履行が確保がされるよう現場の配置技術者等のバックアップやサポートを行う技術者です。そのため営業所技術者には高度な知識や技術力を所持していることが要求されます。
◎営業所技術者の実務経験として認められるもの
営業所技術者に認められる実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験であって、工事施工のための指揮・監督や建設機械の操作等、建設工事の施工に直接携わった経験は当然実務経験として認められます。
他にも、見習中の者が技術の習得のために行う技術的な経験も認められます。具体的には、実際の工事の作業に参加し、または現場監督者や先輩の指示を受けて補助的な作業を行うことで、設計、施工、管理など、その技術分野に必要な技術を身につけるプロセスが実務経験に含まれます。
したがって「設計業務」や「アルバイトでの実務経験」の経験も実務経験に含まれることになり、この実務経験は、建設工事の請負人としての立場で行った経験だけでなく、建設工事の注文者として、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計業務に従事した経験も含まれます。
◎営業所技術者の実務経験として認められないもの
実務経験として認められるものが幅広くある一方で、実務経験として認められないものがあります。例えば、建設工事の現場に出入りはしていても、現場の単なる雑務を行っていた経験は実務経験として認められません。他には建設工事に関係のない事務作業(営業活動、経理処理、書類作成)や、建設工事に関係のない保安業務(現場の警備員、交通誘導員)も実務経験として認められません。
◎その他の注意点
営業所技術者の実務経験として注意すべき点は他にもあり、営業所技術者の実務経験としてみとめられるのは、申請する業種と同じ業種の経験のみであって、申請する業種以外の経験は認められません、また、異なる業種の技術者として申請する場合は、実務経験の期間は重複できないことにも注意が必要です。
他には一定の資格が無いと実務経験として認められないものもあります。電気工事及び消防施設工事はそれぞれ電気工事士免状や消防設備士免状等の交付を受けていなければ現場で作業をすることができないため、免状や資格が無い者の経験は実務経験としては認められません。
また、解体工事は、建設リサイクル法施行後の経験に関しては、とび・土木工事業の許可がある業者での経験又は、建設リサイクル法い基づく解体工事業登録を行っている業者での経験でなければ、実務経験として認められません。
おわりに
どんな実務経験が営業所技術者の実務経験として認められるのかをまとめてみました。しかし実務面でコメントすると実務経験の確認書類である契約書や注文書の写しを揃えることが自社証明であれば容易ですが、転職した際は他社証明となるため書類を揃えるためには先方との交渉が必要になります。行政書士小川真裕事務所では行政書士の方から先方の担当者に説明させていただくことも可能です。他社証明でお困りの方は行政書士小川真裕事務所にお問合せください。必要な書類の種類や枚数について説明させていただきます。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
「部長」の経験が経営業務管理責任者の実務経験として認められる条件について。
建設業許可の要件のひとつに経営業務管理責任者の専任があります。経営業務管理責任者の詳細についてはこちらを参照してもらえばと思います。「経営業務の管理責任者とは?要件と注意点」
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」として経験を有する者に「部長」は含まれておらず、部長を5年以上勤めても経営業務管理責任者の実務経験としては認められません。
役員以外で経営業務管理責任者の実務経験として認められる者とは
部長としての経験は経営業務管理責任者としての実務経験に認められませんが、次に該当する場合は経営業務管理責任者の実務経験として認められる可能性があります。
- 経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)にあった者
- 経営業務の管理責任者の補佐経験があった者
経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)にあった者とは、具体的には取締役会設置会社において
- 取締役会の決議(特定事業の業務執行権限の委譲)がある。
- 代表取締役の指揮、命令の元に業務執行の経験がある。
の両方に該当する必要があります。
経営業務の管理責任者の補佐経験として認められるには補佐経験と職制上の地位が必要になります。職制上の地位とは、営業上対外的な責任者の直属の補佐であること、法人の場合は部長制の場合は部長、部長制が無い場合は課長、職制がない場合は、その地位に次ぐと客観的に認められる者とされており、部長は該当します。 しかし補佐経験とは経営業務を補佐した経験であって、建設工事に関する
- 資金の調達
- 技術者及び技能者の配置
- 下請業者との契約等の経営業務に従事した経験
の3つうちいずれかを指し、単に部長として業務に当たっていただけでは補佐経験として認められません。 また、補佐経験の確認資料としては、
- 使用者の申立書
- 組織図
- 取締役会議事録+登記事項証明書(経験必要期間分)又は、当時の役員の過半数の申立書+登記事項証明書(経験必要期間分)
- 建設業の経験証明資料
の全てが必要となります。
おわりに
以上これらの要件を考慮すると、部長での経験で経営業務管理責任者の実務経験の要件を満たすのはまだまだハードルが高いといえるのではないでしょうか。なお要件や確認資料に関してご不明があれば行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問い合わせください。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。
建設業者が守るべき下請代金の支払いに関する義務についてまとめました。[許可取得後の留意事項の詳細 7/7]
下請代金支払いについて
建設業法で下請代金支払いに関して定められている理由は、下請負人を保護し、手抜き工事や事故を防ぎ、建設工事の適正な施工を確保するためです。具体的な目的として、下請代金の支払いを遅延させることで元請負人が不当に不利益を与える行為を防ぎ、下請負人の資金繰りを安定させて経営を守ることで、結果として建設工事全体の品質向上と国民経済の健全な発展に貢献することを目指しています。
下請代金支払いルールの主な目的
- 下請負人の保護
下請負人が元請負人から不当に圧迫されたり、代金の支払いが遅延したりすることを防ぎます。 - 適正な工事の確保
下請代金が適正に支払われることで、下請負人が十分な資材調達や労働者の確保ができ、手抜き工事や労災事故の防止につながります。 - 公正な取引の実現
下請法(下請代金支払遅延等防止法)の主旨とも重なりますが、発注者(元請負人)と下請業者との間の取引を公正にし、国民経済の健全な発展に寄与します。
具体的な規制内容の例
- 支払期日のルール
元請負人が注文者から工事代金を受け取った場合、速やかに下請代金を支払う義務があります。また、特定建設業者の場合、工事目的物の引渡しを受けた日から50日以内など、一定の期間内での支払いが義務付けられています。 - 前払金の適切な配慮
発注者から前払金を受け取った場合は、下請負人にもその費用を前払いするなど、建設工事の着手に必要な費用を適切に支払うよう配慮することが求められます。 - 現金払いの原則
下請代金は、できる限り現金で支払うことが原則です。手形での支払いも可能ですが、手形期間は120日以内とし、できるだけ短い期間とする必要があります。
建設業法第24条について
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければなりません。
建設業における下請代金の支払いに関する義務とは、元請業者が、注文者から工事代金の支払いを受けた場合、その工事を施工した下請業者に対して、1ヶ月以内(特定建設業者の場合は、下請業者からの引渡し申出日から50日以内)に下請代金を支払う義務のことです。これは、下請業者の資金繰りを保護し、不当な取引を防止するためのものです。
建設業法第24条には元請人の下請代金の支払いに関しての規定が定められています。内容をまとめると以下になります。
(1) 元請業者の義務について
・ 注文者から出来高払いまたは竣工払いを受けた場合、その工事を施工した下請業者に対して、1ヶ月以内に下請代金を支払う必要があります。(第24条の3)
・ 特定建設業者の場合、下請業者からの引渡し申出日から50日以内(特定建設業者または資本金4,000万円以上の法人である下請業者を除く)に支払う必要があります。(第24条の6)
・ 下請代金は、できる限り現金で支払うよう配慮する必要があります。(第24条の3第2項)
・ 発注者から前払金を受けた場合は、下請業者に対しても、資材購入や労働者募集など、工事着手に必要な費用を前払金として支払うよう配慮する必要があります。(第24条の3第2項)
(2) 建設業法上の規定
・ 建設業法第24条の3で、下請代金の支払期日に関する規定が定められています。
・ この規定は、契約に優先し、契約で1ヶ月を超える支払期間を定めても無効となります。
・ 支払いが遅れた場合、遅延利息が発生する可能性があります。
(3) 下請法との関係について
・ 建設業法には下請法のような罰則規定はありませんが、公正取引委員会による処分を受ける可能性があります。
・ 下請法は、親事業者が下請事業者に対して、給付を受領した日から60日以内(建設業法では1ヶ月以内)に下請代金を支払うことを義務付けています。
・ 建設業では、下請代金遅延等防止法の適用はありません。
(4) 違反した場合のペナルティーについて
・ 下請代金を1ヶ月以内に支払わない場合、遅延利息が発生する可能性があります。
・ 公正取引委員会による処分を受ける可能性があります。
・ 下請法違反の場合、遅延利息の支払いだけでなく、親事業者は公正取引委員会による指導や勧告を受ける可能性があります。
まとめ
建設工事では、元請負人が下請負人に代金を支払うまでに、資材の調達や人件費の支払いで一時的に大きな負担が生じます。この支払いが遅れると、下請負人の資金繰りが悪化し、経営が不安定になるリスクがあります。下請代金が適正に支払われないと、下請負人は資金不足から手抜き工事を行ったり、安全対策を怠って労災事故を誘発したりする可能性があります。
建設業における下請代金の支払いに関する義務は、下請業者の資金繰りを守り、不当な取引を防止するための重要な規定です。元請業者は、建設業法および必要に応じて下請法を遵守し、適正な下請取引を行う必要があります。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。