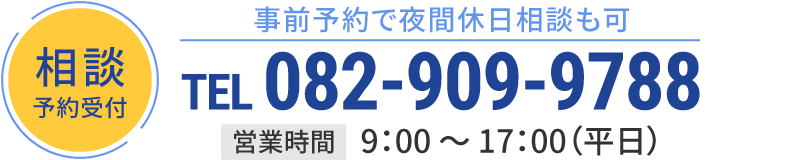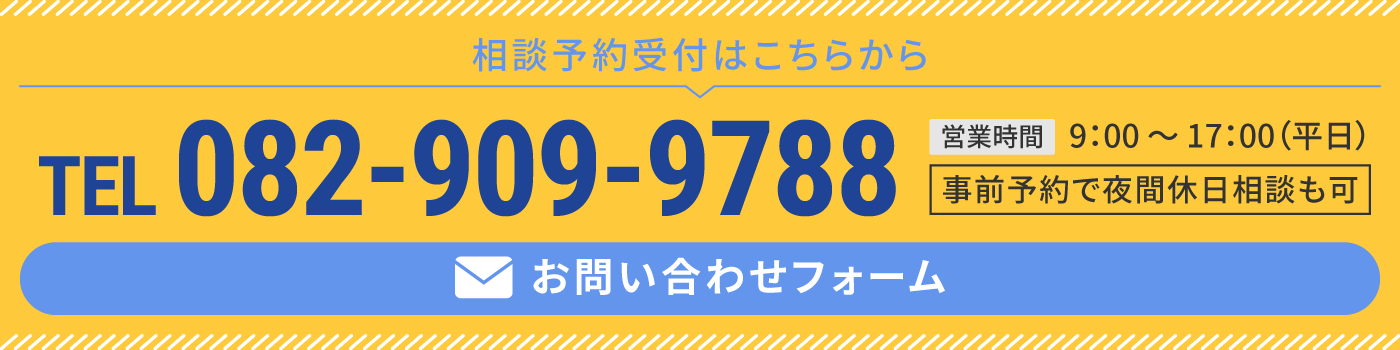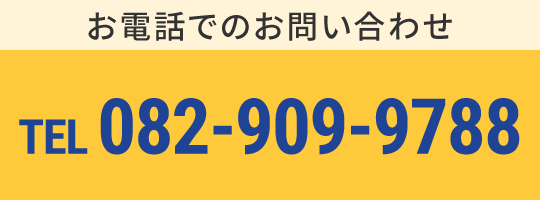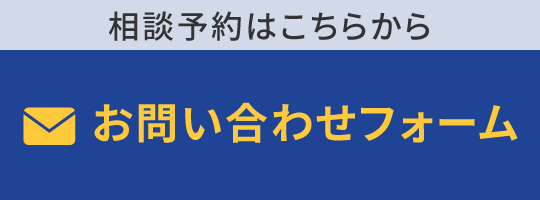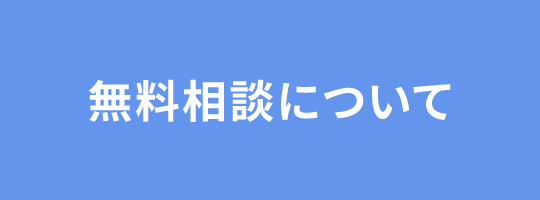このページの目次
建設業とインボイス制度について
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、令和5年(2023年)10月1日から始まった消費税額の計算に関する新しいルールです。
インボイス制度では消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)等の保存が必要になり、適格請求書を交付するためには、「適格請求書発行事業者」の登録申請を行い登録される必要があります。
消費税の仕入税額控除とは、課税事業者が納税すべき消費税を計算する際に、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて計算することによって、消費税の二重課税を解消することができる制度です。
インボイス制度下では、インボイスの非登録事業者に支払った消費税の「仕入税額控除」が認めてもらえないので、インボイス非登録者へ支払った消費税を、税務署にも支払うことになり、消費税の二重払いとなってしまいます。
仕入税額控除が適用されない分は自社で負担することになるため、結果的に、免税事業者など非適格請求書発行事業者とは取引が難しくなる可能性があります。
インボイス制度が建設業に与える影響は小さくなく、建築業者の中でも、特に一人親方は免税事業者であるケースが多く、適格請求書を発行できないため仕入税額控除を受けられなくなります。そのため、一人親方は適格請求書発行事業者への登録を検討する必要があります。
消費税を免税される建設業者について
消費税が免税される免税事業者とは、消費税の申告や納付を免除されている事業者のことです。前々年度(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が1,000万円以下の事業者が該当します。
そのため、前々年度の実績がないので、起業したての事業者は、原則的に免税事業者となります。免税事業者は消費税を受領しますが、インボイス対応の領収書は発行できません。インボイスを発行できる事業者は、適格請求書発行事業者に限られています。
インボイス対応の領収書を発行することは違法となるので注意が必要です。免税事業者を継続すると、これまで通り消費税を納税せずにいられます。課税事業者になると消費税を納税する必要があるため、利益として計上できていた額が減ることになります。
また、一度課税事業者に登録すると2年間は免税事業者に戻れません。インボイス制度後も、課税事業者にならず免税事業者を継続することは可能です。
なお、個人あるいは法人であっても、免税事業者であり、かつインボイス登録事業者でない場合は、消費税の納付が免除されますが、しかしながら、取引先にはインボイスを発行できないので、取引先は仕入税額控除が受けられず、税負担、事務負担が増加します。
その結果として、課税事業者との取引では取引の制限を受けたり、報酬のカットや契約の終了。新規の取引では免税事業者であることが理由で契約がとりにくいといったリスクが想定されます。
適格請求書発行事業者の登録をするには
適格請求書発行事業者に登録していない免税事業者は、適格請求書発行事業者として認められないため、適格請求書の発行ができません。そうすると、課税事業者との取引において課税事業者は仕入税額控除ができず、消費税の負担が高くなります。
適格請求書発行事業者になるには「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署に提出し、税務署の審査に通過する必要があります。審査に通過すると「登録通知書」が発行され、適格請求書発行事業者の登録番号を受け取ることができます。
また国税庁のホームページからe-TAXによる登録申請手続きをすることも可能です。登録にかかる手数料は無料です。
適格請求書発行事業者として登録申請を行われた場合、登録処理が完了するまでの平均期間は、紙による申請の場合は2か月、e-Taxによる申請の場合は3週間です。受付状況によって前後する可能性もあるため期間に余裕をもった申請が重要です。