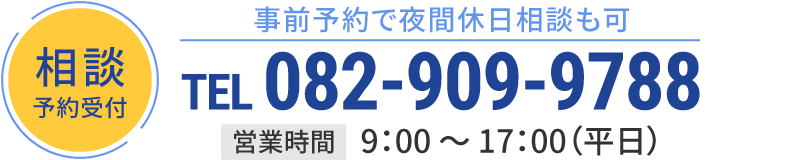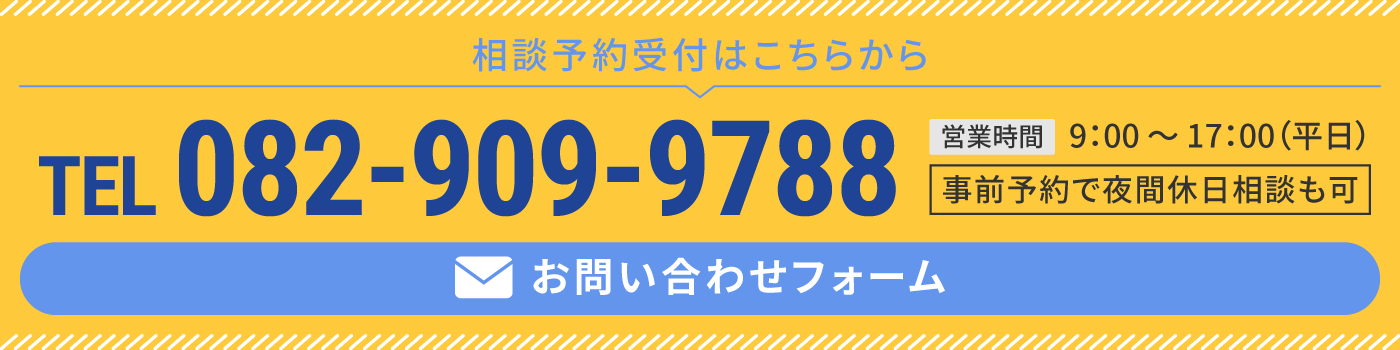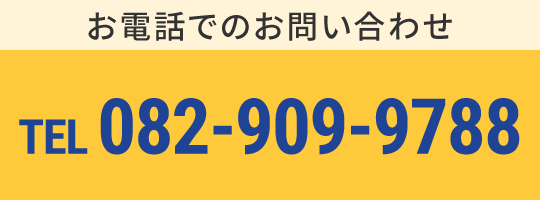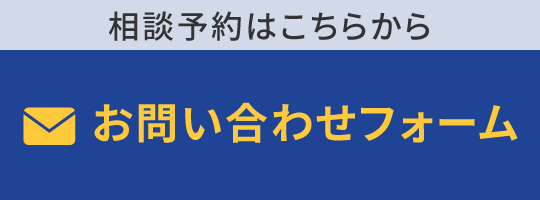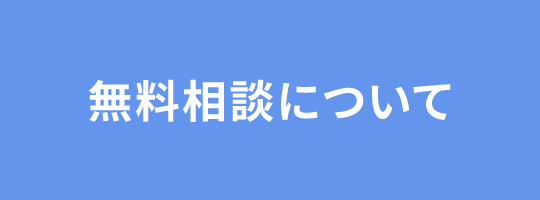このページの目次
建設業許可が必要なケースとは?
このページでは、建設業許可が必要なケースについて、事例をあげながら説明したいと思います。
まず前提として、建設業許可が必要となるのは一定の金額以上の工事を請け負う場合になります。建設業許可を受けずに工事を請け負った場合は無許可で工事となりますので、工事業者様は請負代金の金額に注意が必要です。
では許可が必要となる一定の金額を具体的に述べると原則として、請負代金の金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積が150㎡以上)の工事を請け負う場合は許可が必要な工事となります。
ただし、軽微な工事(請負代金が500万円未満など)のみを請け負う場合は許可は不要です。
今後この請負代金の金額以上の工事を請け負う予定のある事業者様は、建築業許可を必ず取得することになります。建設業許可の取得には諸々の条件を満たす必要があり、申請から取得まで想定以上の日数がかかる場合があります。
広島県の場合、申請した書類の内容を審査する標準処理期間が30日となっており、申請してから許可がおりるまで約ひと月かかることになります。この標準処理期間には補正の期間は含まれていませんので、申請書類の内容について審査行政機関から補正を指摘された場合は、更に許可取得までの日数が伸びることになります。
申請書類を揃えるための期間も考慮すると、許可取得を検討中の事業者様は余裕をもって早めに準備されることを推奨いたします。
建設業許可が必要な例とは?
参考までに建設業許可が必要な代表的な例を挙げておきます。
1. 請負金額が500万以上の工事を請け負った場合
例1)550万円の給排水工事を請け負ったとき。
例2)500万円の消防設備工事を請け負ったとき。
請負金額が500万円の工事も許可が必要です。また消防設備の工事も建設業許可が必要です。
専門工事では、施工に必要な資格の取得+建設業許可の取得の両方が必要になる場合があります。(電気工事では電気工事士の資格が必要な場合等)資格のみでは該当する作業を行えたとしても、建設業許可が必要な場合は工事そのものができませんので注意が必要です。
2. 建築一式工事で、請負金額が1,500万円以上の工事を請け負う場合
例)1,700万円の戸建住宅の新築工事を請け負う場合は建設業許可が必要になります。
ただし、木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の場合は、1,500万円以上の工事だとしても許可が受けなくてもいい場合があります。
建築一式工事とは、原則として元請業者としての立場で建築物の建設にあたり総合的な企画、指導、調整をする工事業種のひとつであり、複数の下請業者によって施工される複雑な工事のことをいいます。
なお、建築一式工事の許可を取得していれば他の専門工事を単独で請け負えるわけではないので、注意が必要です。建築一式工事で軽微な工事の範囲を超える大工工事や左官工事のみの工事を請け負うときは、専門工事となるため、建築一式工事の許可のみでは請け負うことができず、対応する建設業の許可が必要になります。
大工工事であれば大工工事業、左官工事であれば左官工事業の許可が必要になります。この場合はそれぞれの許可を取得して自社施工する、許可を取得している工事業者に外注するといった対応が必要になります。
軽微な工事について
軽微な工事とは、建設業許可を取得しなくて施工できる工事のことをいいます。建築一式工事であれば1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事になり、その他の工事であれば1件の請負代金の額が500万円に満たない工事になります。
ただし、以下の点に注意してください。
- 請負愛金の額は、取引に関わる消費税の額を含みます。
- 注文者が材料を提供した場合の請負代金の額は、支給材料代(市場価格+運送費)を請負代金の額に加えた金額になります。
- 目的が同一の物件であった場合、工事の完成を②以上の契約に分割して請負っているときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額を合計した金額を請負代金の額として判断されます。