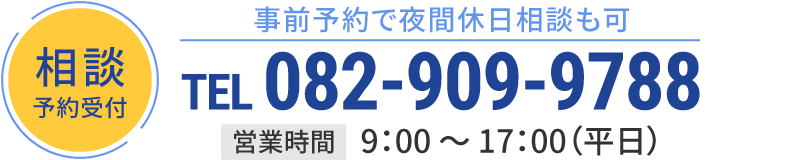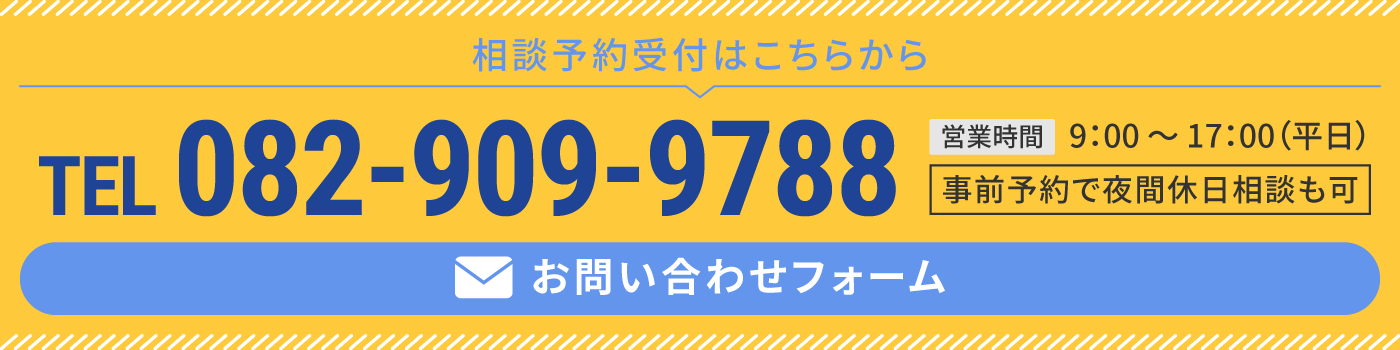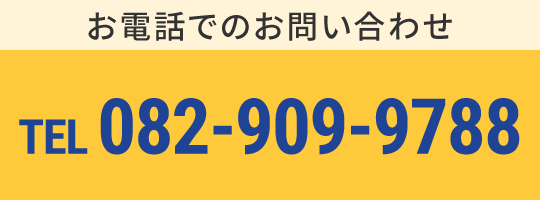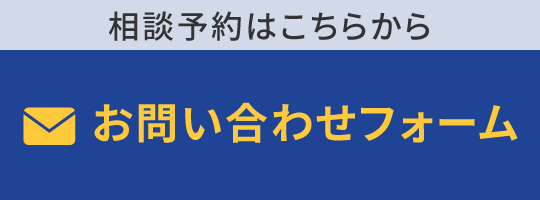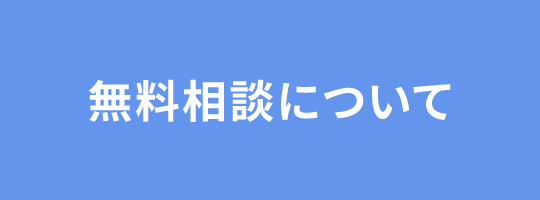このページの目次
建設業と社会保険の関係性について
建設業で働く労働者の生活を安定させ、業界全体の働きやすさを向上させるため、建設業許可の取得要件として社会保険加入が義務化されました。
その背景には、建設業の社会保険未加入問題が深刻化し、労働者が十分な医療や年金を受けられない、あるいは災害時に十分な補償を受けられないといった状況が問題視されていました。
社会保険の加入が義務化された背景
多重下請け構造問題
建設業は、元請けから下請けへと連なる多重構造になっており、社会保険の加入状況を一元管理することが難しい状況でした。
労働者の高齢化と人手不足解消
建設業界では、高齢化と若年層の減少により、労働力不足が深刻化していました。社会保険加入を義務化することで、より多くの人が安心して働ける環境を整備し、労働者の確保を目指します。
労働者の生活不安の改善
社会保険未加入の労働者は、病気や怪我で十分な医療を受けられない、老後の生活資金が不足するなどのリスクを抱えていました。安心して働ける環境を整備するため社会保険の加入が義務化されました。
業界全体の底上げ
社会保険加入を徹底することで、建設業界全体の労働環境を改善し、より質の高い建設サービスの提供を目指しています。
社会保険の種類について
健康保険
健康保険は、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。 サラリーマンなど、民間企業等に勤めている人とその家族が加入する医療保険制度です。 健康保険は被保険者と事業主が保険料を負担しあって運用されています。
厚生年金保険
厚生年金保険は、老後の生活を支えるための年金を支給する保険です。厚生年金は、会社員や公務員の人が国民年金に上乗せして加入する年金制度で、厚生年金保険料は、就職時から納付する義務があり、勤務先と加入者が半分ずつ負担しなくてはなりません。
国民年金と違って、勤務先が加入者に代わって納付するため、給与や賞与から天引きされる形で納付します。
雇用保険
雇用保険は、労働者の失業時や継続的な雇用が困難な事由が発生した際に、労働者の生活と雇用の安定を図る目的で設けられた公的保険です。
失業手当や育児給付金、教育訓練給付金など労働者の生活と雇用継続を保障するさまざまな給付金が用意されています。
労災保険
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
建設業における社会保険の加入は、労働者だけでなく、業界全体の持続可能性を高めるための重要な取り組みです。
労働保険の加入義務とは
労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業所は強制適用事業所であり、加入手続を行う義務があります。
なお、一般的に労働保険とは、労災保険・雇用保険のことをいい、社会保険は、健康保険・厚生年金保険をいいます。社会保険は年金事務所・協会けんぽで手続きを行い、労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークへ、それぞれ手続きを行います。
建設業許可における保険加入義務について
建設業では建設業法の改正をうけ、2020年(令和2年)10月1日から建設業許可を取得するために健康保険など社会保険への加入が実質的に義務化されました。これらの保険は、建設業を営む全ての事業者、つまり法人、個人事業主、一人親方など、従業員を雇用している場合に加入義務が生じます。
社会保険の加入について以下の点に注意が必要です。
一人親方の場合
一人親方の場合、原則として労災保険の特別加入制度を利用する必要があります。
従業員を雇用している場合
従業員を雇用している場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の全てに加入する必要があります。
加入義務のある事業所
一定の条件を満たす事業所は、社会保険への加入が必須となります。
未加入の場合
社会保険に加入していない場合、建設業許可の申請ができないだけでなく、許可の更新もできなくなります。
適切な加入とは
建設業許可の取得には、適切な社会保険に加入していることが求められます。つまり、加入義務のある従業員が一人も漏れることなく加入している必要があります。
建設業許可を取得・維持するためには、社会保険への適切な加入が不可欠です、建設業許可取得の際は詳細を確認し、加入状況について逐次把握を怠らないことが重要です。