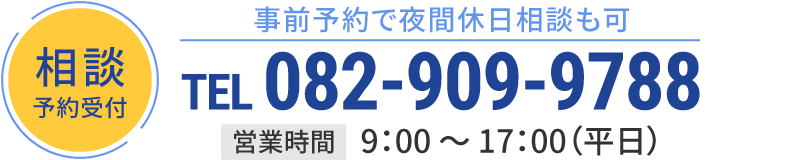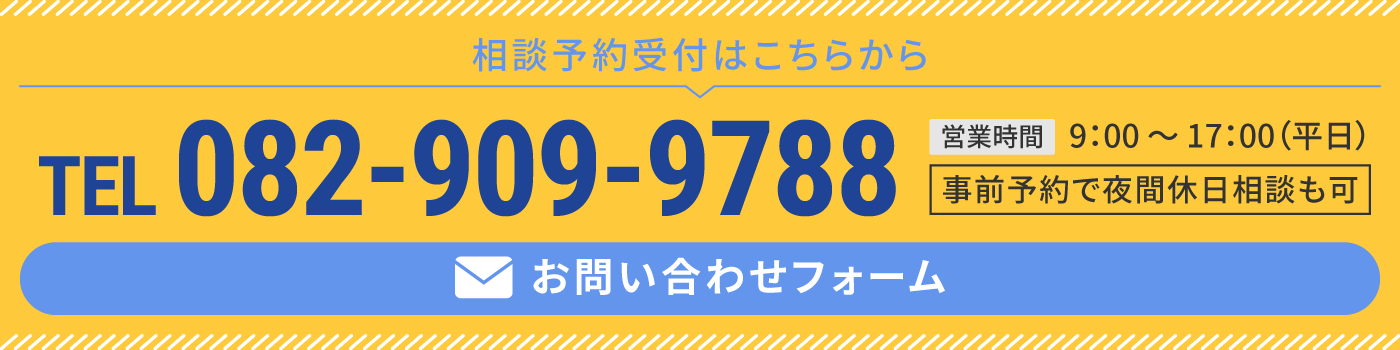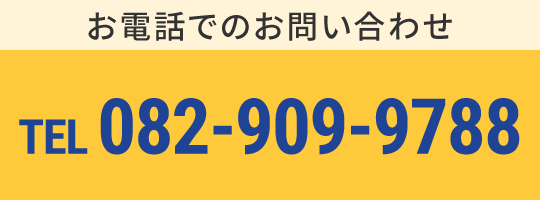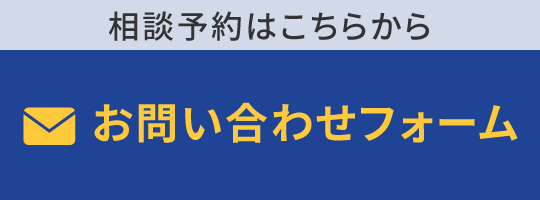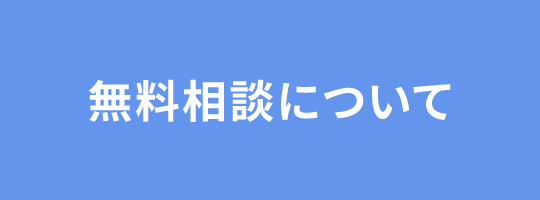建設業許可申請を検討している事業主様に向けて、このページでは建設業許可について、詳細な説明は省いて概要を説明しています。
このページの目次
建設業許可とは?
建設業(建設工事の完成を請け負うことを営業とする者)を営もうする者は、請負金額が500万円未満の軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2)のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければならないとされています。(建設業法第3条第1項)。
建設業許可とは、500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負う建設業者が取得すべき「建設業法第3条」に基づく法的許可のことを指します。
建設業許可は、発注者(注文者)の保護と建設業の健全な発展を目的としており、この許可制度では一定規模以上の建設工事を行う事業者には資質向上のための要件が課せられ、手抜き工事や施工不良、工事途中の倒産といったリスクから発注者を守り、安心して工事を依頼できるようにし、建設業者に一定の技術的・経営的な能力を求めることで、建設業界全体の資質を向上させ、健全な成長を促します。
建設業許可制度では、許可を受けずに所定の請負金額以上の工事を請け負うことは法律で禁止されています。許可を取得せずに工事を請け負った場合は建設業法違反となり「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科される可能性があります。
さらに、過去5年間は建設業許可が取得できず、建設業者としての信用失墜、公共工事の入札参加不可、業務停止処分、営業禁止処分などの行政処分を受けるリスクもあるため、無許可での営業には注意が必要です。
建設業許可の種類とは?
所定の金額以上の工事を請け負うには建設業許可の取得が必要になります。建設業許可では申請区分が分かれており、申請手続きの種類と、請け負う工事の規模および工事の場所によって決まります。
申請手続きの種類は、「新規」、「許可換え新規」、「般・特新規」、「業種追加」、「更新」の5種類あり、請負の形態による区分では、下請への発注総額で「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます。また、営業所の所在地により「大臣許可」と「知事許可」に区分され、それぞれ申請する行政庁が異なります。
申請手続きの種類
「新規申請」
- 現在有効な建設業許可をどこの行政庁からも受けていない場合、または許可を一度廃業した後に再度許可が必要な場合に行う申請。
「許可換え新規」
- 現在有効な許可を持っている建設業者が、許可行政庁を換えたい場合などに行う申請(例:都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ)。
「般・特新規」
- 一般建設業許可のみの許可業者が、特定建設業許可を新たに取得したい場合や、特定建設業許可のみの許可業者が、一般建設業許可を新たに取得したい場合に行う申請。
「業種追加」
- すでに建設業許可を受けている建設業者が、許可している業種に加えて他の業種の許可を申請する場合に行う申請。
「更新」
- 建設業許可の有効期間が満了する前に、引き続き建設業を営むために許可を更新する場合の申請。
請負の形態による区分
建設業許可における請負の形態による区分とは、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類に分けられ、元請として発注者から直接受注した工事において、下請契約で引き出す工事代金の総額によって区分されます。
「一般建設業許可」
- 請け負った工事を発注者から直接請け負う工事の規模にかかわらず、下請けに出す工事の代金の合計額が「建築一式工事で7,000万円未満」、それ以外の工事では「4,500万円未満」である場合に必要となる許可。
「特定建設業許可」
- 元請業者として発注者から直接工事を請け負った際に、下請けに出す工事代金の合計額が一定金額以上(4,500万円以上、建築一式工事の場合は7,000万円以上)になる場合に必要となる許可。
「特定建設業許可」は下請業者への支払額に制約がある元請業者向けの許可であり、取得には「一般建設業許可」よりも厳しい要件が定められています。
- 「一般建設業の許可」・・・合計で4,500万未満までしか下請に出すことはできません。(建設一式工事については7,000万円未満まで)
※金額はいずれも消費税を含む額です。元請人が提供する材料等の価格は含めません。また、自社の請負額に制限はありません。 - 「特定建設業の許可」・・・下請に出す請負金額に制限はありません。
営業所の所在地による区分
建設業許可における営業所の所在地による区分とは、「国土交通大臣許可(大臣許可)」と「都道府県知事許可(知事許可)」の2種類があることを指します。
営業所の所在地が「一の都道府県内のみ」であれば都道府県知事が許可を行う知事許可に、「二以上の都道府県にまたがって」営業所がある場合は国土交通大臣が許可を行う大臣許可に区分されます。
「国土交通大臣許可(大臣許可)」
- 建設業を営む事業者の営業所が2つ以上の都道府県に存在する場合に、国土交通大臣(実際にはその委任を受けた地方整備局長など)が発行する建設業許可。
「都道府県知事許可(知事許可)」
- 建設業を営む営業所がすべて一つの都道府県内にのみある場合に、その都道府県知事から受けられる建設業許可。
建設業許可の申請場所は、大臣許可か知事許可かで異なります。大臣許可の場合は、営業所の所在地を管轄する国土交通省の地方整備局へ直接申請します。知事許可の場合は、主たる営業所を置く都道府県の都道府県庁の建設業担当課へ提出します。
※実際の提出場所は各都道府県によって異なります。申請書類を提出する場合は各都道府県の「建設業許可の手引き」で提出場所を確認してから提出してください。
広島で建設業許可申請について相談するには?
建設業許可申請は、上記の区分に合わせて各要件が定められており、各要件を満たさなければ許可を取得することができないようになっています。
建設業許可取得のために必要な主な要件は6つあります。
①経営業務の管理責任者がいる。
②営業所技術者がいる。
③誠実性を有すること。
④財産的基礎または金銭的信用があること。
⑤欠格要件に該当しないこと。
⑥適正な社会保険に加入していること。
これらの要件は、建設工事を適正かつ安定的に行うために必要とされており、許可の種類や営業所の場所によって具体的な内容が異なります。
広島で許可取得を検討している事業主様は、広島県のホームページからダウンロードできる広島県建設産業課の「建設業許可申請の手引き」を参照することになりますが、内容は専門的であり複雑に感じる事業主様も多いと思います。
早期に許可を取得したい、とても自分たちでは申請書類を準備することができないと思われている事業主様は、行政書士小川真裕事務所までお気軽にご相談ください。行政書士が建設業許可取得の可否の判断、申請書類の作成、要件を満たすために必要な確認書類の収集等の作業を事業主様に代わって行います。
行政書士小川真裕事務所は広島県内及び近隣地域を業務エリアとしている「建築業許可申請」を主業務としている行政書士事務所になります。建設業許可申請に関してお困りの方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
広島市以外のエリアももちろん対応可能です。建築業許可申請を検討されている事業主様には、初回相談無料の面談もしておりますので、まずはお問い合わせください。
行政書士小川真裕事務所について
- 取扱業務を知りたい方はこちらから・・・「対応業務について」
- 料金を知りたい方はこちらから・・・「料金一覧」
- 事務所の概要を知りたい方はこちらから・・・「事務所概要・アクセス」